カサンドラ症候群とは?職場でASDのある方と周囲が互いにより良くはたらくための対処法

ASDのある方がはたらくにあたって、その障害特性により、身近な上司や同僚、部下などがカサンドラ症候群に苦しみ、体調不良やパフォーマンスの低下につながる可能性があります。カサンドラ症候群を予防するためには、ASDのある方本人だけではなく、職場全体で知識や情報を共有し、相互理解を深めることが重要です。
今回の記事では、カサンドラ症候群の症状の特徴と、障害者側ができる対応策を解説します。職場で円滑な人間関係を築き、気持ち良くはたらきたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
-
・職場内カサンドラ症候群について
- ・そもそもカサンドラ症候群とは?
- ・職場内カサンドラ症候群によくある症状
- ・カサンドラ症候群の原因
- ・職場でカサンドラ症候群になりやすい人の特徴
- ・職場内カサンドラ症候群の治療法
-
・職場内カサンドラ症候群を防止するためにASDのある方自身ができること
- ・本人・周囲の双方が障害特性への理解を深める
- ・発達障害の専門機関に相談する
- ・ASDのある方が職場の人間関係や環境に限界を感じたら転職する道もある
- ・ASDのある方および周囲がより良くはたらくにはカサンドラ症候群になりにくい職場づくりが肝心!
職場内カサンドラ症候群について
まず、職場内カサンドラ症候群とはどのようなものなのか、その症状を発症の原因や治療法を踏まえて解説します。
そもそもカサンドラ症候群とは?
カサンドラ症候群とは、ASD(自閉スペクトラム症)のある方とのコミュニケーションがうまくいかないストレスから、心身に不調をきたしている状態のことです。特に、社内の発達障害のあるメンバーを原因とする心身の不調を「職場内カサンドラ症候群」といいます。
なお、この病名は、ギリシア神話に登場するトロイの王女「カサンドラ」が由来です。身近な人が原因となる不条理な状況および周囲の無理解を表すとして、心理療法家のシャピラ氏によって名づけられました。
ただし、カサンドラ症候群は正式な診断名ではなく、あくまで症状の通称です。そのため「カサンドラ状態」や「カサンドラ情動剥奪(じょうどうはくだつ)障害」などと呼ばれる場合もあります。
職場内カサンドラ症候群によくある症状
職場内カサンドラ症候群の症状は、身体的および精神的の2種類の不調に分類されます。
カサンドラ症候群による身体的な不調の例
・ 頭痛
・ 動悸
・ めまい・立ちくらみ
・ 継続的な疲労感
・ 不眠
・ 食欲および体重の増減
カサンドラ症候群による精神的な不調の例
・ 抑うつ
・ 無気力感
・ 不安感
・ 孤独感
・ 気分の変調
・ 自信喪失
・ 罪悪感
ただし、症状の出方や程度は人それぞれです。症状が長期および常態になると、うつ病などの精神疾患に発展することもあるため、防止対策および早期の対処や治療が推奨されます。
カサンドラ症候群の原因
ASDなどの発達障害のある方やそのグレーゾーンの方は、他者に共感することが難しいといわれています。ゆえに、他者との円滑なコミュニケーションに支障をきたす場合も少なくありません。
そのため、ASDのある方と仕事や職場などで身近に接する方は、意思疎通や信頼関係の構築がうまくいかず、大きなストレスを抱えてしまうことがあります。その結果、カサンドラ症候群になってしまうというメカニズムです。
職場でカサンドラ症候群になりやすい人の特徴
カサンドラ症候群は、ASDのある方と関わりが多い人ほど発症の可能性が高く、症状もひどくなりがちです。また、気質的な特徴としては、次のような性格に該当する人はカサンドラ症候群になりやすいといえます。
- 真面目で責任感が強い人
- 我慢強い人
- 几帳面で完璧主義な人
- 面倒見の良い人
上記のような性格の人は、職場で自分と関わる人と真正面から向き合おうとします。そのため、うまくコミュニケーションが取れなくても「自分が面倒を見なければ」「きちんと対応しなければ」と考えるあまり、ストレス過多になってしまうのでしょう。
さらにわだかまりがあっても、自分の中に溜め込みやすく、職場でのストレスをうまく発散できず、カサンドラ症候群の発症につながりやすい傾向にあります。
職場内カサンドラ症候群の治療法
一般的に、カサンドラ症候群の治療は対症療法です。具体的には、カウンセリングおよび症状に応じた薬物療法、認知行動療法などが行われます。なお職場内カサンドラ症候群は、職務上のストレスを原因とする精神障害として、症状によっては労災と認定される場合もあるようです。
ただ、治療はあくまでもその場しのぎにしかならないケースが多く、根本的な原因を取り除かなければ意味がありません。したがってカサンドラ症候群を発症した本人だけではなく、障害者本人を含む職場全体で解決に取り組むことが不可欠です。
職場内カサンドラ症候群を防止するためにASDのある方自身ができること

ASDのある方本人が周囲と円滑な関係を構築しようと努力することで、職場内カサンドラ症候群のリスクが軽減できるうえ、自らのより良い働き方にもつながります。日頃周囲となかなかうまくいかないと悩んでいる方は、次の2つのポイントを心がけてみてください。
本人・周囲の双方が障害特性への理解を深める
ASDのある方本人が自らの障害を深く理解し、さらにそれをあらかじめ周囲に伝えておくことは、職場でのカサンドラ症候群予防の近道です。職場への障害特性の周知は義務ではありませんが、より良い人間関係と働き方を実現するためには重要な場合もあります。
例えば、ASDがある人は相手の気持ちを理解したりあいまいな言い回しから真意を汲み取ったりすることが苦手な方が多く、言葉の選び方も独特です。また特定の物事へのこだわりが強く、自らの意に反する言動や、突然の予定変更などにうまく対応できないこともあるでしょう。ASDのある方本人が悪気なくやった行為でも、相手に迷惑をかけたり傷つけたりする可能性があります。
したがって、発達障害のある方とのコミュニケーションには、適切な距離感や特性に応じた配慮が欠かせません。あらかじめ周囲に障害特性を理解してもらうことで、接し方や伝え方、距離感などに適切な配慮が期待できるので、お互いのためになるでしょう。
なお、同じ発達障害でも、得手不得手は人によってさまざまです。だからこそ、自らの障害特性への理解を深め、それに応じて具体的にどのような配慮を必要とするのかを説明しておくことが大切だといえます。
発達障害の専門機関に相談する
精神科や心療内科などの医療機関への受診および発達障害の支援機関、行政の専門窓口などへの相談が、特性緩和の大きな一歩になるはずです。
ASDなどの発達障害があると、場の空気を読んだ行動や、相手の気持ちが理解しづらい傾向にあります。とはいえ、訓練次第でうまく適応できるようになるかもしれません。
発達障害の専門家から適切な対処法や環境調整を学べることに加え、状態に応じて投薬による治療も受けられます。さらに、認知行動療法やSST(ソーシャルスキルトレーニング)などの訓練を受ければ、社会適応能力が格段に高まるでしょう。
また発達障害のある方は、周囲とのコミュニケーションの行き違いから、うつ病などの二次障害を発症するケースも珍しくありません。そのため、心身の不調を感じたらすみやかに受診することが早期回復および現状改善につながります。
まだ周囲に障害をオープンにしていないなら、まずは職場の上司や専門の窓口などに相談することから始めてみるとよいでしょう。
ASDのある方が職場の人間関係や環境に限界を感じたら転職する道もある
先述のとおり、職場内カサンドラ症候群の防止に最も効果的な方法は、本人や周囲がASDの特性を理解したうえ、職場全体および専門機関と協力しながら環境調整や配慮を徹底することです。具体的には、以下のような対応策が挙げられます。
- 業務内容や指示の出し方などを特性に応じて改善する
- ASDのある方および密接に関わる人が休憩・リフレッシュできる環境を確保する
しかし、こうした環境調整は、ASDのある方個人の努力だけは難しい場合もあるでしょう。適切な理解が得られないと互いにストレスを抱えることになり、職場内カサンドラ症候群や、ASDのある方のニ次障害につながる恐れがあります。
努力してもうまくいかず、職場の人間関係や環境に限界を感じたら、心身に不調をきたすまえに転職を検討するのも一つの道です。思い切って合理的配慮が徹底されている職場に転職すれば、ぐっとはたらきやすくなるでしょう。
なお合理的配慮とは、障害者と健常者の公平な社会参加を実現するための措置のことです。障害のある方が合理的配慮がある環境を見つけることで、本人がはたらきやすいのはもちろん、一緒に過ごす周囲の気持ちも安定しやすい傾向にあります。
また、障害者雇用枠で採用される仕事もおすすめです。障害特性に応じた環境に身を置くことで、職場すべてのメンバーのより良い就業が実現するでしょう。
発達障害のある方の仕事探しの際は、障害者雇用専門の窓口や転職・就職エージェントといった、知識・実績の豊富な就活支援サービスにぜひ相談してみてください。自らの適性や障害特性に応じて活き活きとはたらける職場が、きっと見つかるはずです。
ASDのある方および周囲がより良くはたらくには、カサンドラ症候群になりにくい職場づくりが肝心!

ASDのある方が仕事をする中で、考えや理解の行き違いから周囲の人がカサンドラ症候群を発症することもあるかもしれません。しかし、ASDのある方本人と周囲が障害特性をきちんと理解し、職場全体が協力して環境調整を行えば、カサンドラ症候群は防げます。
とはいえ、周囲からの理解が得られなかったり、調整が難しい場合もあるでしょう。そんなときは、無理して心身のバランスを崩す前に、より良くはたらける職場に転職することも一つの方法です。
障害者のための転職エージェント「dodaチャレンジ」は、長年培ってきた障害者雇用の知識・ノウハウを最大限に活かし、ASDの特性に合った仕事探しを全力でバックアップします。「職場にうまく馴染めない」「仕事が長続きしない」などの悩みを抱えている方は、ぜひ一度ご相談ください。
お仕事をしていて
こんなお悩み
ありませんか?

-

コミュニケーションが
うまくいかない -
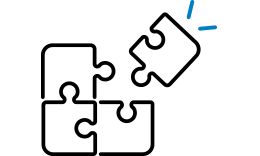
職場の人間関係が
よくない -

業務量が多すぎる
-

心身が不調
-
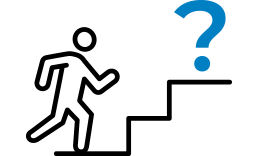
キャリアアップが
イメージできない -

自分に合う仕事が
わからない
転職について不安なことも
障害者雇用の知りたいことも
キャリアドバイザーが親身にお話をうかがいます
公開日:2025/1/29
- 監修者:木田 正輝(きだ まさき)
- パーソルダイバース株式会社 人材ソリューション本部 キャリア開発支援事業部 担当総責任者
- 旧インテリジェンス(現パーソルキャリア)に入社後、特例子会社・旧インテリジェンス・ベネフィクス(現パーソルダイバース)に出向。採用・定着支援・労務・職域開拓などに従事しながら、心理カウンセラーとしても社員の就労を支援。その後、dodaチャレンジに異動し、キャリアアドバイザー・臨床心理カウンセラーとして個人のお客様の就職・転職支援に従事。キャリアアドバイザー個人としても、200名以上の精神障害者の就職転職支援の実績を有し、精神障害者の採用や雇用をテーマにした講演・研修・大学講義など多数。
- ■国家資格キャリアコンサルタント
- ■日本臨床心理カウンセリング協会認定臨床心理カウンセラー/臨床心理療法士
 記事をシェアする
記事をシェアする
