障害者雇用における不採用の理由とは?採用を勝ち取るコツを紹介
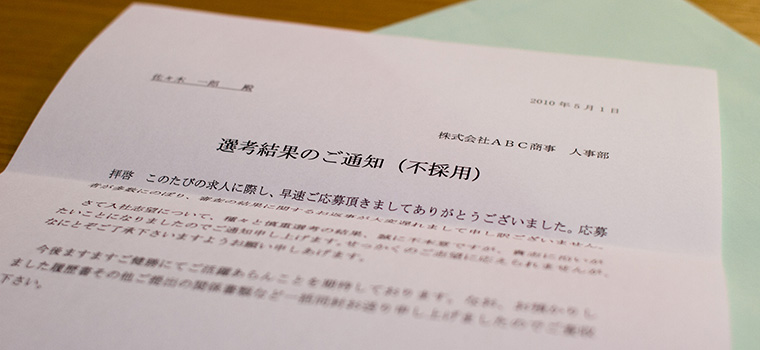
障害者雇用枠の求人に応募して不採用通知を受け取ったとき、不採用になった理由を知りたいですよね。結論からいうと、不採用理由が開示されることはほぼありませんが、主な不採用理由と対策を知っておくことで、採用を勝ち取れる可能性が高まります。そこで本記事では、障害者雇用枠における代表的な不採用理由や、採用されるための対策を解説します。
目次
障害者雇用において不採用の理由は開示されない
就職・転職活動で不採用になったとき、なぜ不採用だったか知りたくなるでしょう。しかし次のような理由から、一般雇用枠・障害者雇用に関わらず、企業が不採用の理由を明らかにするケースはまれなので、問い合わせは避けるのが無難です。
- 選考基準の機密性を確保するため
- トラブルのリスクを回避するため
選考基準の機密性を確保するため
各企業には明確な採用基準や評価基準がありますが、それは企業活動の根幹に関わる情報です。企業機密を保護するために、不採用の理由を開示することは避けられる傾向があります。
トラブルのリスクを回避するため
不採用の理由を明かすことで、応募者からの反発や法的措置など、何らかのトラブルに発展するリスクがあるため、採用に関する情報開示は避けられます。また、採用活動は企業のイメージにも直結することからも、問い合わせによる情報開示は期待できません。
障害者雇用における代表的な不採用理由
前述したように、障害者雇用の不採用理由が企業から直接明かされることは基本的にありませんが、代表的な理由として次のようなものが考えられます。
- 「職業準備性」が整っていない
- スキルや能力がミスマッチである
- 障害受容や障害理解が不足している
- 提示した配慮事項の実現が困難である
- 質問に適切に回答できていない
「職業準備性」が整っていない
「職業準備性」とは、就労に欠かせない準備が整っている状態のことで、主に次の5つの要素が重視されます。
- 健康管理
- 日常生活管理
- 対人技能
- 基本的労働習慣
- 職業適性
障害者雇用において職業準備性を重視する企業は多く、例えば「生活リズムが不安定」「自己管理ができていない」などの場合、安定した就労への不安があると見なされてしまいます。
スキルや能力がミスマッチである
企業が求めるスキルを満たしていない、経験が不足しているなどの場合、採用される可能性は低くなります。逆に、ご自身の経験・スキルに見合うポジションを企業側が用意できない場合もミスマッチです。条件を満たしているにも関わらず不採用になった場合は、履歴書や面接などで十分にアピールできなかった可能性が考えられます。
障害受容や障害理解が不足している
「自身の障害を受け入れられていない」「障害特性について理解できていない」など、自己分析や自分自身への理解が不足しているという理由で不採用になることもあります。企業側は従業員に対して安定就労を期待するため、ご自身の障害特性を理解したうえで、障害と付き合いながらはたらき続けられることが大切です。
提示した配慮事項の実現が困難である
企業に求める「合理的配慮」の内容が原因で不採用になる可能性もあります。合理的配慮の提供は2016年の障害者雇用促進法の改正により雇用主に義務化されているため、それを求めたからといって不採用になることはありません。
ところが「あまりにも過剰な配慮事項の要求」や「職務内容と配慮事項とのアンマッチ」などがある場合は、企業側が対応できないものもあります。ご自身の障害特性を理解したうえで、はたらくために必要不可欠な配慮事項をまとめて企業に提示しましょう。
質問に適切に回答できていない
面接の担当者の質問に適切な回答ができていない場合は、コミュニケーション能力に疑問点が生じ、不採用になってしまうことがあります。例えば、質問の趣旨と違う回答をしてしまうなどです。事前に面接練習を繰り返して、質疑応答に慣れておく必要があります。
障害者雇用での就職・転職で不採用にならないための対策

障害者雇用で不採用にならないためには、次のようなポイントを意識することが大切です。
- 職業準備性を高める
- 業務スキルや資格を習得する
- 面接対策を丁寧に行う
- 必要な配慮事項をまとめる
職業準備性を高める
障害者が就労するためには職業準備性、つまり安定してはたらくために必要な状態を整えることが大切です。主治医などのアドバイスを受けて生活習慣を整えることで、障害特性と付き合いながらはたらく体制が整い、面接の際も就労への意欲としてアピールできます。
業務スキルや資格を習得する
求人内容を確認して必要なスキルや資格を習得することで、ミスマッチが原因の不採用を減らせます。スキルや資格を身に付けるために学んだ実績は、就労意欲や企業貢献への意識の高さのアピールにつながるでしょう。
面接対策を丁寧に行う
模擬面接を行ったり想定問答集を作成したりして、面接対策を行うことも重要です。面接で自分自身についてアピールできなければ、せっかくのスキルや経験をアピールできず、採用を勝ち取ることができません。どんな質問をされてどのように答えるかを想定し、第三者に模擬面接をしてもらってフィードバックを受けることで、本番の面接に備えることができます。
必要な配慮事項をまとめる
前述したように、必要な配慮事項を明確化することは、障害者雇用で不採用を避けるために欠かせません。障害特性を把握して「何ができないか」「どんな配慮があれば会社に貢献できるか」をまとめることで、「障害と向き合っている姿勢」もアピールできます。
障害者雇用で転職するための支援機関・サービス
障害者雇用で理想の転職をかなえるためには、次のような支援機関やサービスを利用するのがおすすめです。
- ハローワークの障害者関連窓口
- 就労移行支援事業所
- 障害者向けの転職エージェント
ハローワークの障害者関連窓口
全国のハローワークには、障害がある人のための「障害者関連窓口」が設けられており、障害のある方が就労に関するさまざまな相談ができます。専門知識がある担当者の対応が受けられるため、ご自身の障害特性や適正に合った求人を探すことが可能です。履歴書作成や面接対策など、転職活動に必要なサポートも受けられるので、安心して転職活動に臨めるでしょう。
就労移行支援事業所
就労移行支援事業所は、はたらくための知識・スキルの習得に加えて、転職活動のサポートを提供している機関です。就労のためのサポートを受けることで、職業準備性を整えて採用の可能性を高めることができます。
パーソルダイバースの「ミラトレ」は、障害のある方の就労をかなえるための就労移行支援事業所です。理想のはたらき方を実現するために、さまざまな支援を行っておりますので、まずはお気軽に見学・ご相談ください。
障害者向けの転職エージェント
障害のある方が自分に合う求人を見つけるためには、「障害者向けの転職エージェント」の活用がおすすめです。さまざまな障害に関する専門知識とサポート実績のあるキャリアアドバイザーに相談することで、ご自身の障害特性や配慮事項を把握し、適職を探しやすくなります。
障害者雇用で採用を目指すなら「dodaチャレンジ」にご相談を

障害者雇用枠で不採用になる理由として、スキルや経験のミスマッチや、障害理解や合理的配慮の課題などが挙げられます。障害者向けの転職エージェント「dodaチャレンジ」では、ご自身に合った求人の紹介や、はたらきやすい環境を手に入れるために欠かせない「配慮事項」の明確化など、さまざまなサポートが受けられます。
また、一人で転職活動を行う際の大きなハードルが「面接対策」でしょう。dodaチャレンジでは、キャリアアドバイザーから入念な面接対策を受けることができます。応募企業に応じた面接対策や、面接後のフィードバックを得ることができるため、採用を勝ち取れる可能性が高まるはずです。dodaチャレンジの利用は無料なので、転職をお考えの方はこの機会にぜひご相談ください。
まずは、キャリアアドバイザーに転職相談を

電話orオンライン
でお気軽にご相談ください
転職について不安なことも
障害者雇用の知りたいことも
キャリアドバイザーが親身にお話をうかがいます
公開日:2025/9/26
- 監修者:戸田 幸裕(とだ ゆきひろ)
- パーソルダイバース株式会社 人材ソリューション本部 事業戦略部 ゼネラルマネジャー
- 上智大学総合人間科学部社会学科卒業後、損害保険会社にて法人営業、官公庁向け営業に従事。2012年、インテリジェンス(現パーソルキャリア)へ入社し、障害者専門のキャリアアドバイザーとして求職者の転職・就職支援に携わったのち、パーソルチャレンジ(現パーソルダイバース)へ。2017年より法人営業部門のマネジャーとして約500社の採用支援に従事。その後インサイドセールス、障害のある新卒学生向けの就職支援の責任者を経て、2024年より現職。
【保有資格】- ■国家資格キャリアコンサルタント
- ■障害者職業生活相談員
 記事をシェアする
記事をシェアする
