【障害者雇用】退職届の書き方|退職届の例文・テンプレートと気を付けたいポイント
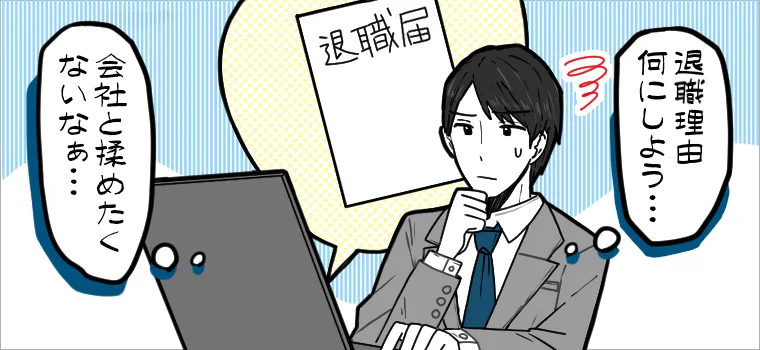
障害者雇用であっても、一般雇用であっても、現職を何らかの理由で退職するとき必要になるのが「退職届」です。具体的な書き方や注意すべきポイントなど、本記事では、退職届の書き方を例文・テンプレート付きで解説します。
目次
「退職届」とは
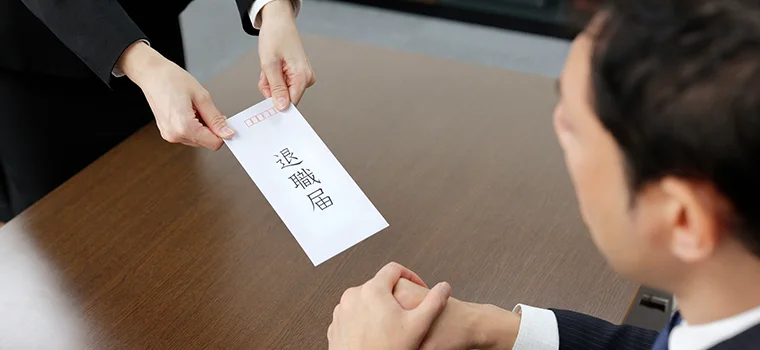
「退職届」とは、退職への承諾を会社から得たあとで、その旨を正式に届け出るための書類です。
退職届と混同されやすい書類に「退職願」と「辞表」があります。「退職願」は、会社に労働契約の解除を願い出るための書類で、前述した退職届の前に提出します。必ずしも書類で提出する必要はなく、口頭で伝えても構いませんが、書面で提出することで退職意思の強さを示し、「言った言わない」などの無用なトラブルを減らせます。また、「辞表」は会社役員や公務員が役職を辞める場合の書類で、一般の会社員が提出する必要はありません。
退職届を提出する流れ
障害者雇用で退職届を提出するときは、次のような流れで進めるといいでしょう。
- 1. 退職意思 を固める
- 2. 口頭もしくは退職願で退職意思を上司に伝える
- 3. 承認後に退職日を決める
- 4. 退職届を作成・提出する
なお、退職意思は退職希望日の1~2ヶ月前に、直属の上司に伝えるのが望ましいです。退職意思の伝え方については、こちらの記事も併せてご参照ください。
【障害のある方向け】退職の切り出し方|正しい退職意思の伝え方と注意すべきポイント
事前に就業規則を確認しておきましょう
退職届を書く前に、会社の「就業規則」を確認しておくことが大切です。退職手続きに関する項目では、例えば「退職希望日の2ヶ月前までに退職届を直属の上司に提出する」など、退職届を提出すべき期限が明記されていることが一般的です。
就業規則の規定がある場合は、退職届を遅れて提出すると受理されず、退職手続きが難しくなってしまうこともあります。また、企業によっては退職届の所定フォームが設けられていることもあるので、退職手続きを行う前に詳細を確認しておきましょう。
退職届の例文・書き方テンプレート
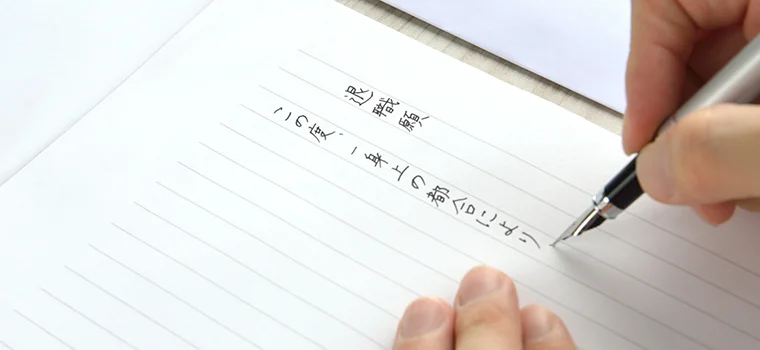
障害者雇用の場合も、退職届の書き方は一般雇用と変わりません。企業によって所定フォームが指定されている場合もありますが、ここでは一般的な退職届の見本と例文をご紹介します。退職届を書く際の参考にしてみてください。
退職届
私儀
このたび、一身上の都合により、誠に勝手ながら◯年◯月◯日をもって退職いたします。
◯年◯月◯日
(所属する部署名)
(氏名)
(退職する会社名)
代表取締役社長(氏名)殿
退職届の書き方で意識しておきたいポイントを次の項目に分けて解説します。
- タイトル
- 書き出し
- 本文(退職理由・退職日)
- 提出日
- 所属・氏名・捺印
- 宛名
タイトル
タイトルは「退職届」とします。なお「退職願」として作成すれば、そのまま退職の承認を得るための退職願の書類になります。
書き出し
書き出し(前文)として「私儀(わたくしぎ)」と記載します。これは「私事ではございますが」を意味する表現であり、あくまで個人的事情に基づく退職であることを示すために重要な項目です。
本文(退職理由・退職日)
本文には「このたび一身上の都合により、誠に勝手ながら○年○月○日をもって退職いたします」などと記載します。重要なポイントは「退職理由」と「退職日」の2つを盛り込むことです。
退職理由については「一身上の都合」とすることが多く、体調不良や転職など詳細な理由を書くことは基本的にありません。そのため、この部分も定型文と考えておくとよいでしょう。退職日には、事前に上司や人事担当者と合意した退職年月日を記入します。年については、基本的には西暦と和暦のどちらでも構いません。ただし、会社の規定で例えば「和暦を使うこと」と決められていればそれに従い、規定がなければ西暦を使うのが一般的です。
提出日
提出日の部分には、上司に退職届を提出する日付を記載します。先ほどの退職日とは異なるため、混同してしまわないように注意しましょう。
所属・氏名・捺印
退職届の末尾には正式な部署名を記載したうえで、氏名をフルネームで記入します。捺印が必要な場合はいわゆる「シヤチハタ」ではなく、公的に通用する実印を使用するのがマナーです。
宛名
最後に宛名を記載しますが、社名と会社の代表者・最高執行責任者として、役職名を添えてフルネームを記載することが重要です。先ほどのご自身の名前より上に配置し、敬称は「様」もしくは「殿」を用いましょう。
「文書の形式」と「提出方法」の基本
障害者雇用における退職届の書き方と併せて、次のような文書の形式や提出の仕方も確認しておきましょう。
- 文書の形式
- 記載する用紙
- 折り方と封筒
文書の形式
退職届は縦書きが一般的ですが、前述した必要事項が含まれていれば横書きでも問題ないため、ご自身が書きやすい形式を選びましょう。書き方については、直筆で作成する場合は黒インクのペンではっきり記載し、パソコンで作成する場合はプリンターで印刷します。ただし、会社の規定がある場合はそれに従ってください。
記載する用紙
用紙についてはB5サイズ(182mm×257mm)が一般的ですが、A4サイズ(210×297mm)が使用されることもあります。直筆で作成する場合は罫線が引かれた便箋、パソコンの場合は白い用紙のほうが作りやすいのでおすすめです。なお、ほかの項目と同じく、就業規則にて指定がある場合はそちらに沿って作成しましょう。
折り方と封筒
退職届は封筒に入れて提出するのが一般的です。前述したように、退職届の用紙にはB5もしくはA4を使用しますが、どちらの場合でも封筒は「長形3号(120×235mm)」がおすすめです。退職届を封筒に入れるときは、用紙の長辺を三つ折り、つまり三等分するように折ってから入れるようにしましょう。
障害のある方が退職手続きで気を付けたい5つのポイント
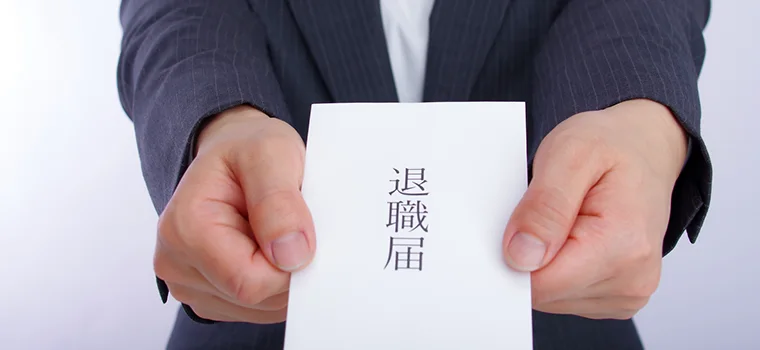
障害者雇用であっても一般雇用であっても、退職の手続きを行う際はできるだけスムーズに進めたいはずです。そこで、次のようなポイントを意識してみましょう。
- 退職意思が固いことを伝える
- 受け入れられやすい退職理由を伝える
- 受け入れられやすい退職希望日にする
- 自発的に動いて手続きを進める
- 退職後の手続きも忘れずに行う
退職意思が固いことを伝える
スムーズに退職手続きを進めるためには、「退職の意思が固いこと」を明確に伝えることが大切です。企業が退職希望者の引き止めに動くことも少なくありません。例えば、「給与を上げる」「昇進の話がある」「チームが回らなくなる」などを理由にされるケースがあります。
意思表示がはっきりしない場合は、こうした引き止めが繰り返される可能性があるので、「お引き止めいただけるのはありがたいですが退職の意思は変わりません」のように、いかなる場合も意思は変わらないことを伝えましょう。
受け入れられやすい退職理由を伝える
退職について会社に打診するときは、「体調悪化」や「障害特性」もしくは「家庭の事情」など、上司や人事部の納得が得られやすい理由を選ぶ必要があります。
「会社への不満」については、伝えたからといって改善されるものではないうえに、残りの日を会社で過ごしづらくなる恐れがあるため避けるほうが無難です。「お役に立てない」「力不足かもしれない」のような内容は、退職の意思が曖昧に感じられるため適切ではありません。退職理由の伝え方については、こちらの記事も併せてご参照ください。
【障害のある方向け】退職の切り出し方|正しい退職意思の伝え方と注意すべきポイント
受け入れられやすい退職希望日にする
退職希望の旨を申し出るときは、退職日とセットで交渉するようにしましょう。一方的に伝えるのではなく、就業規則で定められている期限日を尊重することや、業務の引き継ぎ状況を踏まえることが大切です。転職先が決まっている場合は、入社予定日から逆算して早めに手続きを始めましょう。
自発的に動いて手続きを進める
退職手続きはご自身で積極的に進めることを意識したいです。会社側から退職の流れや日程を調整してくれることは基本的になく、むしろ前述したように再考を求められることがほとんどです。そのため、ご自身で手続きを進める日時を提案したり、退職の合意後すぐに退職届を提出したりするなど、自発的に進める必要があります。
退職後の手続きも忘れずに行う
退職後は公的手続きが必要になるため、退職届の書き方と併せて意識しておくことも大切です。現在の健康保険と年金を国民健康保険や国民年金に切り替えるか、転職先がすでに決まっている場合は新規の社会保険に加入することを忘れないようにしましょう。これから転職先を探す場合は、生活のために失業保険を申請することも必要です。
障害者雇用における退職届の書き方について、よくある質問
退職届の書き方のよくある質問についてまとめました。障害者雇用においても一般雇用と差はありませんが、実際に手続きを進める際の参考にしてみてください。
- 一度提出した退職届は撤回できる?
- 上司が退職の申し入れを受理してくれない場合は?
- 退職届はメール形式でも提出できる?
- 退職前に有給休暇は消化できる?
- 障害者雇用でよりよい職場を探す方法は?
一度提出した退職届は撤回できる?
退職願は責任者が承認した時点で退職が確定し、退職届は上司が受理した時点で労働契約解除となります。したがって、退職願も退職届も原則として提出後は撤回できないと考えて、慎重に手続きを進めるようにしましょう。
上司が退職の申し入れを受理してくれない場合は?
直属の上司が退職願を受理してくれない場合は、上司と話し合いの場を設けて退職意思を再度伝えるか、上司のさらに上の役職者に相談してみてください。例えば、「直属の上司に退職願を提出したが取り合ってもらえない」と相談すると、スムーズに進みやすくなります。ちなみに無期契約の場合は、「退職の申し入れから2週間経過すると雇用契約が終了する」ことが、民法第627条第1項によって定められています。
退職届はメール形式でも提出できる?
法律上は口頭やメールでも退職の意思表示が成立することになっていますが、一般的には就業規則などで「書面での提出」が求められています。なお、療養などで休職中の方や遠方でリモートワークをしているなど直接での手渡しが難しい場合は、メール形式で問題ないか上司に確認しておきましょう。
退職前に有給休暇は消化できる?
労働基準法第39条により、労働者には有給休暇を取得する権利があります。退職前に有給休暇を消化したい場合は、事前に上司や人事担当者に相談してスケジュールを調整する必要があります。有給の消化を拒否することは法律上認められていませんが、円満に退職するためには繁忙期や引き継ぎに配慮することが大切です。
障害者雇用でよりよい職場を探す方法は?
今の仕事を退職後、障害者雇用でよりよい職場を探すためには、障害者向けの転職支援サービスを活用するのがおすすめです。障害者雇用にはさまざまな求人がありますが、ご自身の障害特性や体調、スキルや経験に合った仕事を独力で探すのは簡単ではありません。
今回解説したように、退職届には手続きの手順や書き方など、注意すべき点が多く手間がかかります。退職や転職を繰り返さず、「はたらきやすい環境」での就労を叶えるために、ぜひプロのサポートを受けてみてください。
理想の転職をかなえるために!円満退社で次のステップへ

障害者雇用の退職届の書き方で気を付けるポイントは、「タイトル」「書き出し」「本文(退職理由・退職日)」「提出日」「所属・氏名・捺印」「宛名」の6つの項目です。また、退職意思が固いことを伝えたり、ご自身で積極的に動いて退職手続きを進めたりすることがとても重要です。理想のキャリア実現のために、退職届の書き方や退職の手続きについてしっかり確認して、円満退職を心がけましょう。
- 監修者:戸田 幸裕(とだ ゆきひろ)
- パーソルダイバース株式会社 人材ソリューション本部 事業戦略部 ゼネラルマネジャー
- 上智大学総合人間科学部社会学科卒業後、損害保険会社にて法人営業、官公庁向け営業に従事。2012年、インテリジェンス(現パーソルキャリア)へ入社し、障害者専門のキャリアアドバイザーとして求職者の転職・就職支援に携わったのち、パーソルチャレンジ(現パーソルダイバース)へ。2017年より法人営業部門のマネジャーとして約500社の採用支援に従事。その後インサイドセールス、障害のある新卒学生向けの就職支援の責任者を経て、2024年より現職。
【保有資格】- ■国家資格キャリアコンサルタント
- ■障害者職業生活相談員

