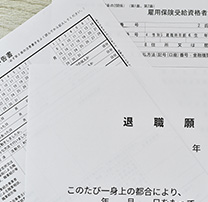【障害のある方向け】退職の切り出し方|正しい退職意思の伝え方と注意すべきポイント

今の仕事を辞めることになった際、スムーズに退職できるかどうかは伝え方にかかっているといっても過言ではありません。誤った切り出し方をしてしまうと、引き止めにあったり、トラブルに発展したりしかねないからです。特に、転職先が決まってからの退職を申し出る場合には慎重な判断が欠かせません。
本記事では、退職意思の正しい伝え方を解説します。円満退職に向けてやるべきこと・やってはいけないことを順序立ててまとめました。すでに転職先が決まっている方はもちろん、これから転職活動を始める方もぜひご一読ください。
目次
退職の意思を伝える流れ
まず、退職の意思を会社へ伝える際の流れを2つのステップに分けて説明します。
1.直属の上司に口頭で伝える
退職の意思を固めたら、まずその旨を会社に口頭で伝えましょう。退職意思をはじめに伝えるべき相手は、直属の上司です。直属の上司の合意を得た後、上位役職者、人事担当者の順で伝わるのが一般的な流れとなります。
順序を誤ると、退職交渉や手続きがスムーズにいかないだけではなく、直属の上司の管理能力が問われ思わぬトラブルに発展しかねません。メールだと意思や意図が正しく伝わらない恐れがあるため、抵抗感を覚える方もいるかもしれませんが、口頭で伝えるのが望ましいです。
テレワークなどで直接対面する機会がないときは、電話のほか、Web会議ツールを通して伝える方法もあります。いずれの場合も、感情的・攻撃的な言動は控え、誠実かつ落ち着いた態度と伝え方を心がけてください。
2.退職届を提出する
口頭で退職の合意を得たら、退職届を作成します。なお、公務員およびそれに準ずる仕事に就いている方や、役付きの方が退職する場合は「辞表」という表現を用います。
そもそも法的には、口頭だけでも退職は可能です。しかし、会社の就業規則・慣習などに則り書面の作成が必要な場合があるほか、退職届の提出は社会通念上のマナーでもあります。
退職届に記載する内容は、主に次の4項目です。
- 退職理由
- 退職日
- 書面の作成日
- 署名・捺印
基本的には、会社の就業規則に準じた書式で作成し、指定の部署・担当者へ提出すれば問題ありません。特に形式に関する決まりがない場合は、上記内容を記載した退職届を、口頭で伝えたときと同じく直属の上司に手渡しするのが一般的です。
退職届の書き方はこちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひ併せてチェックしてみてください。
退職を切り出すタイミング

退職を切り出すタイミングは、その時点での転職先の有無や伝える相手によって異なります。ここでは、よくある3つのケースに分け、適切なタイミングをみていきましょう。
転職先が決まってから退職する場合:内定後すぐ
転職先が決まっている場合は、内定後に退職を切り出します。ただし、退職の意思を伝える適切なタイミングは、手元に内定通知書が届き正式に入社の意思を先方に伝えた後です。
採用が確定するのは、内定が書面で通知され、それを応募者が受諾したときとなります。確定前に早まって退職を申し出てしまうと、万が一内定取り消しとなったときに取り返しがつかなくなることがあるので注意してください。
まだ転職先が決まっていない場合:希望する退職日の約1ヶ月前
転職先が決まるより先に退職の意思を伝えるときは、退職希望日の約1ヶ月前までには申し出るのが基本です。ただし、企業によっては、退職に関する就業規則が定められていることがあります。また、担当している業務内容によっては、1ヶ月では引き継ぎが完了しないこともあるでしょう。特に決まりがない場合は、1ヶ月を目安とし、後任者へ余裕を持って引き継ぎできる期間を確保してください。
同僚・後輩や取引先に退職を伝える場合:退職が正式に決定してから
同僚や後輩、取引先などに退職することを伝えるのは、会社との交渉を終え、正式に退職が決定したタイミングです。まだ話がまとまっていない段階で第三者に伝えた場合、現場の混乱を招いたり、人間関係が悪化したりしかねません。
上司とも相談のうえ、引き継ぎから退職のスケジュールが明らかになった段階でチーム全体に報告するのがベストです。取引先へは、プロジェクトが一段落した段階や、引き継ぎが完了したタイミングで上司の承諾を得てから連絡することをおすすめします。
退職届を出す前に伝えておくべき内容

現在の仕事を辞めるときは、退職届を出す前に、次の2点を伝えておきましょう。
- 退職の意思・理由
- 退職の希望日
退職の意思・理由
退職を決心したら、まずその意思を現在の勤め先に伝えます。退職を決意するに至った理由を、具体的かつ簡潔に伝えましょう。
大切なのは、退職意思の強さを態度や言葉で明確に示すことです。あいまいな理由を告げたり、迷っている様子を見せたりすると、引き止めにあうかもしれません。
とはいえ、意思や希望を一方的に告げるのは避けましょう。また、嘘をつくと、思わぬところから伝わる恐れがあるので、退職理由と伝え方は慎重に考えてください。会社への不満といったネガティブな退職理由ばかり告げることも、会社や上司、同僚との関係が悪化し、スムーズな退職の妨げになるかもしれないので控えましょう。
企業名など転職に関する詳細は伝える必要はないので、聞かれても返答を断って構いません。病気や障害を理由とする退職の場合も同様です。特に退職理由が体調不良や障害の症状悪化の場合は、強い引き止めにあうことがストレスにもなりかねません。退職の意思が強いことを伝えたうえで、辞めるにあたっての詳細な条件に関しては交渉の姿勢をみせることが円満退職のコツだといえます。
例文
ここでは、会社が納得し、受け入れてもらいやすい3つの退職理由とその伝え方を解説します。
- 例1:家庭の事情による退職の伝え方
- 実家の両親の体調が悪く、しばらく様子を見る必要があります。いつまでかかるか見通しが立たず、会社に迷惑もかけられないので、一旦退職をして看病に専念したいです。
- 例2:体調不良による退職の伝え方
- 最近、休んでも疲れが取れず、十分なパフォーマンスが発揮できていない状態です。主治医からも、自宅療養を指示されました。休職も考えましたが、会社に迷惑をかけるのは忍びなく「早く戻らなければ」という精神的なプレッシャーも感じてしまいます。一旦退職して、体調を整えさせていただきたいです。
- 例3:転職による退職の伝え方
- この度、私が希望していた企業より内定をいただき、退職を考えております。次の転職先では、柔軟なワークスタイルが実現でき、また新たなチャレンジが出来るポジションを用意いただいており、家族にも賛成してもらっています。しっかりと引継ぎを行い、なるべくご迷惑をかけないように調整いたしますので、〇月末にて退職とさせてください。
逆に、次のような退職理由は引き止めにあいやすいので避けるほうが無難です。
- 引き止めにあいやすい例1:会社への不満を退職理由にする
- 現在の仕事量の多さや給与、労働時間の長さなど待遇面に不満があるので辞めさせてください。
- 引き止めにあいやすい例2:退職に迷いを感じていることを伝える
- 実は、このままこちらで勤務を継続すべきか迷っています。皆さんに良くしていただいていますが、自分がお役に立てていないのではないかと感じ、退職を考え始めました。
会社への不満をそのまま上司に伝えると、それを解消する提案をされたり、上司との関係が悪くなったりと、スムーズな退職に結びつかない可能性があります。また、退職の意思に迷いが感じられると、引き止めの余地があると思われてしまうので注意しましょう。
退職の希望日
退職希望日は、退職を切り出したタイミングで一緒に交渉するとスマートです。退職希望日の決め方が分からないときは、以下のいずれかを目安にしてください。
- 就業規則に準じて決める
- 引き継ぎに必要な日数から逆算して決める
まずは、就業規則でいつまでに退職届を提出しなければならないかを確認しましょう。一般的には、退職期日の約1〜2ヶ月前までです。雇用期間に定めのない正社員の場合、法的には2週間前までに申し出ればよいとなっていますが、円満退職のためには会社のルールに従いましょう。
また、業務引き継ぎには、ある程度の時間を要します。そのため、退職を切り出してからではなく、内定が出そうだと感じたときに事前に準備を始めてください。ただし、転職先が決まっている場合は、入社予定日に合わせて退職日を決めるのが大前提です。スムーズな退職交渉のためにも、転職先への入社日や入社時期に関する条件を事前に確認しておきましょう。
退職意思の伝え方と退職前後に関して注意すべき6つのポイント

以下では、退職意思を伝える際や、退職の前後に注意すべき6つのポイントを解説します。
事前に交渉のアポイントメントを取る
退職に関する相談前には、上司にアポイントメントを取っておくのがマナーです。アポイントメントを取るのは、口頭のほか、電話やメール、チャット、書面などでも構いません。ただし、会社や上司の余裕がないときに切り出されると、後回しにされたり、強い引き止めにあったりする可能性があります。特に、繁忙期に申し出る際は、申し出るタイミングや時間、伝え方に気をつけましょう。
また、アポイントメントの段階では、用件を明確に告げる必要はありません。事前に伝えてしまうと、あれこれ理由をつけて先延ばしにされる場合もあります。
他者に話を聞かれない場所で申し出る
退職に関する話はセンシティブな内容です。普段仕事しているフロアや休憩室など、人に聞かれる恐れのある場所で伝えるのは避けることをおすすめします。
また、直属の上司に退職意思を伝えたあとの段取りが会社の規則やケースによって異なるため、併せて打ち合わせておくとよいでしょう。
自発的に行動する
退職に関する会社との打ち合わせは、自発的に動くよう心がけてください。なぜなら、会社が退職希望者のために積極的に動いてくれるケースはほとんどないからです。結果的に調整期間が長引きやすくなり、希望の退職日に間に合わなくなったり、引き継ぎに十分な時間が取れなくなったりしかねません。
打ち合わせの日時を自ら提案し、話がまとまったら、会社の指示を待つのではなく、すぐに退職届を提出しましょう。退職を切り出した後は、1週間程度を目安に交渉をまとめることを目標とすれば、スムーズかつ意思の強さがアピールできます。
退職準備は早めに取りかかる
退職の準備は、余裕を持って早めに取りかかりましょう。マニュアルの作成や資料の整理などの引き継ぎの準備にはある程度の時間がかかるため、着手が遅れるとその分退職までの日数も長引きます。
退職準備を始めるベストなタイミングは、内定が出そうだと感じたときです。退職の前にはたくさんの準備があるため、自分だけでできる作業をあらかじめ進めておきましょう。やることをリストアップしたり、チェックリストを作成したりしておくと、段取り良く進められるはずです。
ただし、退職準備で通常の業務が滞ると、トラブルになったり体調不良の元になったりすることがあるので、あくまでも差し障りのない範囲で取り組んでください。
残った有給休暇は計画的に消化する
未取得の有給休暇は、退職前に消化することが可能です。しかし、退職する方の都合だけで有給を取得すると、人間関係の悪化や業務の混乱を招き、円満退職とはいかなくなってしまいます。
退職を切り出す前に少しずつ消化しておく、有給休暇の日数を踏まえて転職先への入社日を決めるなど、計画的に消化できるよう工夫しましょう。
退職後の生活に関する手続きを確認しておく
退職時には、その後の生活に関する次のような諸手続きも同時に行う必要があります。
- 離職票の発行依頼
- 健康保険・年金の切り替え(資格喪失証明書の受取)
- 失業保険の申請 ※雇用保険の加入期間が6ヶ月以上ある場合
また退職時期によっては、住民税の納付を自分で行わなければなりません。障害年金の給付対象になる場合は、その手続きの準備も進めるとよいでしょう。
会社から強く引き止められて退職できないときは?

どれほど綿密に準備を進め、適切な対応を心がけても、強い引き止めにあい退職がなかなか認められないこともあります。直属の上司から話に取り合ってもらえないときは、さらに上位の役職者や、人事担当の部署に相談してみましょう。
それでも受け入れてもらえなかった場合は、労働基準監督署もしくは全国のハローワークをはじめとする国・自治体の就労支援・労働相談窓口に相談することをおすすめします。また、退職理由が体調不良や持病・障害の悪化などの際は、主治医や会社の産業医、保健所・保険センターなどへ相談するのも一つの方法です。各関係機関へ相談した旨を会社に伝えるだけでも、無理な引き止めの抑止力になります。
dodaチャレンジを利用している方が退職の引き止めにあった場合は、早めに担当のキャリアアドバイザーへ相談してください。障害者の就職・転職のプロとしての視点から、スムーズな退職が実現するようサポートします。
円満退職には工夫が必要!伝え方に気をつけてスムーズな転職を
円満退職のためには、退職意思を伝えるタイミングと伝え方が肝心です。十分な余裕を持った日程で、退職意思が強いことを伝えれば、スムーズな退職が実現しやすくなります。社会人としての節度やマナーを守った行動を心がけて退職することで、わだかまりなく次のステップへ進めるはずです。障害者専門の転職エージェントも活用し、スムーズかつ納得のいく転職活動を実現しましょう。
- 監修者:戸田 幸裕(とだ ゆきひろ)
- パーソルダイバース株式会社 人材ソリューション本部 事業戦略部 ゼネラルマネジャー
- 上智大学総合人間科学部社会学科卒業後、損害保険会社にて法人営業、官公庁向け営業に従事。2012年、インテリジェンス(現パーソルキャリア)へ入社し、障害者専門のキャリアアドバイザーとして求職者の転職・就職支援に携わったのち、パーソルチャレンジ(現パーソルダイバース)へ。2017年より法人営業部門のマネジャーとして約500社の採用支援に従事。その後インサイドセールス、障害のある新卒学生向けの就職支援の責任者を経て、2024年より現職。
【保有資格】- ■国家資格キャリアコンサルタント
- ■障害者職業生活相談員