発達障害の二次障害とは?ADHDやASDによる二次障害の症状や対処法を解説

ADHDやASDといった発達障害がある方は、うつ病や不安障害などの精神疾患を発症しやすいといわれています。こうした現象を「二次障害」と呼び、日常生活や社会生活での困難や「生きづらさ」がより深刻になってしまいます。
そのため、発達障害の二次障害には適切な対処が欠かせませんが、二次障害の内容は個人差が大きいため、障害特性や状況に合った対処が必要です。そこで本記事では、発達障害の二次障害の症状や対処法について詳しく解説します。
目次
発達障害の「二次障害」とは
発達障害の二次障害について、まずは次のポイントから見ていきましょう。
- 障害特性が原因で生じる精神疾患の総称
- 二次障害を発症してしまう主な理由・原因
障害特性が原因で生じる精神疾患の総称
「二次障害」とは、ADHDやASDなどの発達障害が原因となり、精神疾患を発症してしまう状態です。発達障害がある人はその障害特性が原因となり、周囲の人々とのコミュニケーションが取りづらく、環境にうまく適応できない傾向があります。
だからこそ周囲の理解や障害特性に合うサポートが必要なのですが、それが得られず強いストレスを感じる機会が多いと、精神疾患を併発してしまうことがあります。ただし、二次障害は医学的な診断名ではなく、発達障害のさまざまな特性が原因で起こる諸問題の総称です。
二次障害を発症してしまう主な理由・原因
発達障害には主に次のような種類があり、障害特性もそれぞれ異なります。
| 発達障害の種類 | 主な障害特性 |
|---|---|
| ADHD(注意欠如・多動症) | 注意や行動をコントロールしづらく、次々と周囲のものに関心を持つ |
| ASD(自閉スペクトラム症) | 興味や関心が特定のことに偏っており、対人関係やコミュニケーションが苦手 |
| LD/SLD(学習障害/限局性学習症) | 読む・書く・計算する・推論するなど、特定の分野を苦手とする |
発達障害は目に見えない障害であり、人それぞれ障害特性も異なるため、周囲の人から理解されにくいです。例えば、その場の空気や相手の意図を察するのが苦手という場合、あたかも本人の注意力や人格の問題であるかのように扱われることがあります。その結果「なぜ自分にはできないのか」と自分を責め、ストレスや自己嫌悪などで精神疾患を発症してしまうのです。
発達障害の二次障害の種類・症状
発達障害の二次障害には次の2種類のものがあり、それぞれ代表的な症状が異なります。
- 内在化障害
- 外在化障害
内在化障害
「内在化障害」は、自分自身に影響を及ぼす精神症状を指し、次のようなものが該当します。
| 精神疾患・症状 | 具体的な状態 |
|---|---|
| うつ病 | 気分が落ち込んだ状態が続き、生きていることがつらく感じてしまう |
| 適応障害 | 自身の置かれている環境に適応できず、不眠や抑うつ状態などの症状が出る |
| 不安障害 | 不安に襲われるとパニック発作が出て、人混みや電車を避けるなど社会生活に支障が出る |
| 強迫性障害 | 強い不安や恐怖を打ち消すために、例えば何度も手を洗うなど強迫的な行動が生じる |
| 対人恐怖症 | 他人との交流や評価を過度に恐れて、精神的・身体的なさまざまな症状が出る |
| 心身症 | 精神的・社会的な要因から生じる身体的な症状で、例えばストレスによる胃潰瘍など |
| 依存症 | アルコール依存症や薬物依存症など、特定の行動を自身で制御できない状態 |
| 引きこもり | さまざまな要因から学校や仕事を避けて、自宅に閉じこもる状態が続くこと |
発達障害の二次障害のなかでも、特に多いのが「うつ病」だといわれています。例えばASDの人が職場でのコミュニケーションに悩み、うつ病を発症するケースがあります。
外在化障害
「外在化障害」は、他者に影響を及ぼす精神症状を指し、次のようなものが該当します。
- 暴言や暴力
- 家出
- 非行
- 反社会的行動
- 行為障害
- 反抗挑戦性障害
- 感情不安定
- 自傷行為
学生時代など比較的幼いうちから、このような行動が見られることもあれば、大人になってから発現するケースもあります。
二次障害の発症・悪化につながる仕事上の悩み
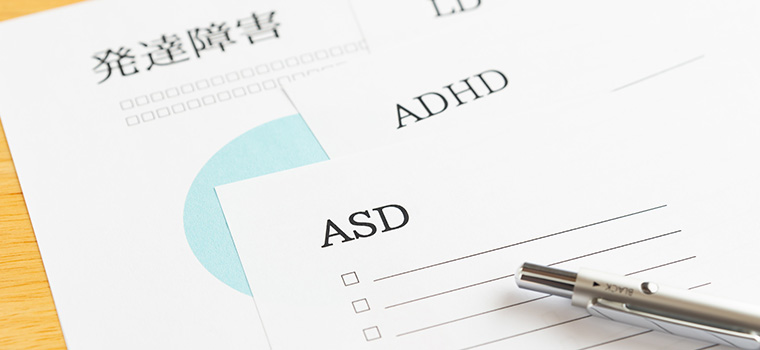
発達障害の二次障害を発症してしまう理由はさまざまですが、仕事においては次のような悩みや困りごとが、二次障害の発症や悪化の原因になると考えられています。
- 自分の仕事に自信が持てない
- 対人関係に恐怖心を感じる
- 周囲と衝突することが多い
- 周囲の理解や配慮が得づらい
自分の仕事に自信が持てない
発達障害がある人は、障害がない人と比べて「できないこと」があるという状況に直面しやすいです。例えばASDがある人の場合は、他人と足並みをそろえたり場の空気を読んだりすることが苦手で、悪目立ちや避けられることが増えやすい傾向があります。
その結果、仕事でトラブルが起きたり思うように成果が出なかったりしたときに、「自分はダメだ」と気分が落ち込んで二次障害の要因になってしまうのです。
対人関係に恐怖心を感じる
発達障害の人は、コミュニケーションに困難を抱えやすい傾向があり、特にASDのある人は対人関係に対する恐怖を抱えやすいといわれています。例えば、仕事ではお互いの立場の違いによって言葉遣いを変えるのが一般的ですが、ASDの人は不自然になってしまいがちです。
こうした障害特性は自覚しづらいうえに、自身で対処できる範囲も限られています。そのため、仕事でコミュニケーションが原因のトラブルが起きたときにどうすべきか分からず、対人関係を恐れて対人恐怖症や不安障害などの二次障害の要因となります。
周囲と衝突することが多い
発達障害の特性は人それぞれですが、特定の分野に対する「こだわり」が強い場合は、社内で衝突が起きやすくなります。自身の才能や得意分野が活かせない場合は、それがより強いストレスになることもあるでしょう。社内の同僚や上司とうまく付き合えないことで、自己嫌悪や疎外感を感じて二次障害につながることも珍しくありません。
周囲の理解や配慮が得づらい
発達障害は「目に見えない障害」であるため、職場で周囲の理解や配慮が得づらいです。例えば、ADHDのある人が集中力や正確さなどで困難を抱えていたとしても、性格や努力の問題として扱われてしまいがちです。理解や配慮が得られない結果として、他人との関わりを避けるようになり、誰にも悩みを相談できず二次障害を発症・悪化させてしまいます。
発達障害の二次障害への対処法
発達障害の方が二次障害の発症を防ぐ、もしくは悪化を防ぐためには、次のような対処法が効果的です。
- 医師や専門家に相談する
- こまめに休憩を取る
- 自身の障害特性を理解する
- 職場で理解と配慮を得る
- 対処が難しい場合は転職を検討する
医師や専門家に相談する
発達障害のある方が職場で何らかの困難を感じ、二次障害の発症や悪化の可能性がある場合は、まず医師や専門家に相談することが大切です。
前述したように、発達障害の場合は身近な人からの理解が得づらいため、信頼できる医師やカウンセラーに悩みを打ち明けることで、問題解決が進みやすくなります。そのうえで、次のような対処法を検討してみましょう。
こまめに休憩を取る
発達障害のある人は、基本的にストレスを感じやすい傾向があるといわれています。さらに、ADHDやASDがある人の場合は、疲労している状態でも長時間作業を続ける「過集中」の状態になりやすいのです。そのため、業務の合間には意識的にこまめな休憩を取り、適度に心身を休ませるようにすると無理なくはたらき続けやすくなります。
自身の障害特性を理解する
体調や症状とうまく付き合えていない場合は、まずは自分の障害特性についてしっかり把握することが大切です。どのようなときに困難やストレスを感じるかを理解することで、自分にとっての「二次障害が生じにくい環境」について分かります。
例えば、他人とコミュニケーションを取るときに強い不安を感じる場合は、顧客対応のような対人コミュニケーションが少なく、一人で課題に取り組めるような職種が向いています。
職場で理解と配慮を得る
自身の障害特性について理解できたら、職場で理解や配慮を求めることが重要です。前述したように、二次障害の主な理由は精神的なストレスなので、理解ある職場の中で周囲のサポートを得ることができれば障害特性と付き合いやすくなります。例えば、コミュニケーションに困難を感じているのであれば、対人業務が少ない部署への異動を希望するなどです。
対処が難しい場合は転職を検討する
職場で合理的配慮を得づらい場合や、さまざまな対策を取っても二次障害が改善しない場合は、転職を検討してみましょう。障害特性や自身の得意分野に合わせた仕事や環境を選ぶことで、二次障害のリスクを抑えて健康的にはたらきやすくなります。特に、発達障害に対する合理的配慮が得やすい職場が理想的です。
発達障害の二次障害のある方が活用できる就職・転職サービス

発達障害の二次障害がある方は、次のような就職・転職サービスを活用することで、自分に適した「はたらきやすい環境」が見つかるでしょう。
- 発達障害者支援センター
- 就労移行支援事業所
- 障害者向けの転職エージェント
発達障害者支援センター
「発達障害者支援センター」は、発達障害のある方を対象として、日常生活や仕事のサポートを提供する機関です。2025年時点で全国に90カ所前後あり、地方自治体・社会福祉法人・NPO法人などが運営しています。ハローワークとの連携もあるため、就職・転職について気軽に相談できるでしょう。
就労移行支援事業所
就労移行支援事業所は、はたらくための知識やスキルの習得、就職・転職活動のサポートを提供している機関です。転職後も定着支援としてスタッフと定期的に連絡ができるため、困ったことや悩みがある場合の精神的なサポートも得やすいことが魅力です。
ただし、就労移行支援事業所では求人の紹介は行っていないため、転職活動は別途ハローワークなどで行う必要があります。
障害者向けの転職エージェント
障害者向けの転職エージェントは、障害者の就労に特化したサービスで、自身の希望や適性に合う求人の紹介が受けられます。キャリアアドバイザーに無料で相談し、自身の障害特性に合わせた適切な転職先について知ることが可能です。また、就職・転職活動で欠かせない履歴書や面接などの対策サポートも受けられるので、安心して就職活動ができるでしょう。
二次障害に悩む方の就職・転職には「dodaチャレンジ」がおすすめ!
「対人関係に恐怖を感じる」「周囲の理解や配慮が得づらい」などの不安やストレスは、発達障害の二次障害のリスクを高めます。そのため、職場で合理的配慮が得づらい場合は、自分に合った環境ではたらける職場への転職を検討してみましょう。
発達障害がある方が転職を目指すときは、パーソルダイバースの転職支援サービス「dodaチャレンジ」がおすすめです。dodaチャレンジの転職支援サービスでは、発達障害および二次障害について専門知識を持ったキャリアアドバイザーが一人ひとりの就職・転職を支援します。あなたに合った求人情報を探してご紹介するほか、面接・ 応募書類作成のサポートや面接対策、個別のご相談なども行いますので、安心して転職活動に臨めるでしょう。
お仕事をしていて
こんなお悩み
ありませんか?

-

コミュニケーションが
うまくいかない -
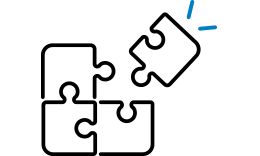
職場の人間関係が
よくない -

業務量が多すぎる
-

心身が不調
-
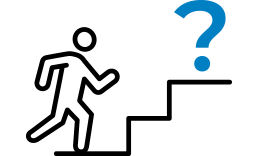
キャリアアップが
イメージできない -

自分に合う仕事が
わからない
転職について不安なことも
障害者雇用の知りたいことも
キャリアドバイザーが親身にお話をうかがいます
公開日:2025/2/28
- 監修者:木田 正輝(きだ まさき)
- パーソルダイバース株式会社 人材ソリューション本部 キャリア開発支援事業部 担当総責任者
- 旧インテリジェンス(現パーソルキャリア)に入社後、特例子会社・旧インテリジェンス・ベネフィクス(現パーソルダイバース)に出向。採用・定着支援・労務・職域開拓などに従事しながら、心理カウンセラーとしても社員の就労を支援。その後、dodaチャレンジに異動し、キャリアアドバイザー・臨床心理カウンセラーとして個人のお客様の就職・転職支援に従事。キャリアアドバイザー個人としても、200名以上の精神障害者の就職転職支援の実績を有し、精神障害者の採用や雇用をテーマにした講演・研修・大学講義など多数。
- ■国家資格キャリアコンサルタント
- ■日本臨床心理カウンセリング協会認定臨床心理カウンセラー/臨床心理療法士

 記事をシェアする
記事をシェアする
