抑うつ状態とは?症状が続くときの対処法と診断された後の働き方

「ゆううつな気分になることが増えた」「やる気が出ない」などの自覚症状があるときは「抑うつ状態」になっているかもしれません。抑うつは心のSOSであり、精神疾患の初期サインの可能性があるので、早期の対処が肝心です。
今回は、抑うつとはどのような状態なのか、うつ病との違いも踏まえてまとめました。仕事への影響や休職の要否、うまく付き合っていくための方法についても解説します。
目次
抑うつ状態とは
まず「抑うつ」とはどのような状態なのかみていきましょう。
抑うつ状態の定義
「抑うつ状態(うつ状態)」とは、心身に過度なストレスがかかることによって生じる一時的または慢性的な不調の総称です。人間関係の不和や環境の変化、身近な人との別れなどの精神的なストレスがあると、心に大きな負担がかかります。疲弊した心は身体や精神にさまざまな悪影響を及ぼしますが、その状態にあることを医学的には「抑うつ」と呼びます。
抑うつ状態の症状
抑うつ状態になると、身体的・精神的にさまざまな不調が生じます。次のような症状が、抑うつ状態の代表例です。
- 気分が晴れない
- やる気が出ない
- 身だしなみが気にならなくなる
- 身の回りが片付けられなくなる
- 集中して考えるのが難しくなる
- ささいなミスが増える
- 人と会う・話すのが億劫に感じる
- 自信がなくなる
- 夜眠れない、または眠り過ぎる
- 身体に原因不明の不調や痛みが現れる
- 食欲がない、または食べ過ぎる
- 短期間で体重が大きく増減する
- 月経不順が起こる
こうした抑うつ状態は、すべて心に起因することなので、身体的な治療だけでは改善が難しいといえます。
抑うつ状態は病気じゃない?
正確には、抑うつ状態という病名は存在しません。抑うつは、あくまでも心身の状態や、それに伴う諸症状を指す用語です。しかし、うつ病や双極性障害、適応障害などの精神疾患の初期症状として現れることも多いため、決して軽視してはいけません。
抑うつ状態とうつ病の違い

抑うつ状態は病名ではなく、何らかの原因で生じた症状名を指します。一方、うつ病は病名であり、その代表的な症状が抑うつ状態です。一時的な抑うつであれば時間の経過とともに改善することもありますが、その状態が慢性化し、一定の基準を満たすときはうつ病と診断されます。
抑うつ状態と診断されたからといって、必ずしもうつ病とは限りません。とはいえ、広義に「抑うつ状態」というと、うつ病やその他の精神障害・疾患を指すことも多いです。
抑うつ状態を主症状とする精神障害・疾患
ここでは、抑うつ状態を呈する代表的な6つの精神障害・疾患について説明します。
気分障害
「気分障害」とは、日常生活に支障をきたすほどの気分の変調と抑うつ状態を主症状とする精神疾患の総称です。うつ病や双極性障害、非定型うつ病などが該当します。一時的な抑うつ状態より症状が重篤かつ長期的で、強い自責や希死念慮が生じることもあります。
適応障害
「適応障害」とは、特定のストレスに適応できないことで生じる慢性的な抑うつ状態です。ストレッサーと距離を置くことで、改善する可能性があります。逆にいうと、ストレスが解消できない限り症状が長期化・慢性化するほか、別の重篤な精神疾患を発症する恐れもあります。
燃え尽き症候群
「燃え尽き症候群(バーンアウト)」とは、特定の物事に頑張り過ぎ、精神的に消耗した結果生じる無気力症状を指します。正確には疾患ではなく、蓄積されたストレスが一気に押し寄せることで、特定の物事へのモチベーションや意欲を失ってしまった状態です。
無気力症候群
「無気力症候群(アパシーシンドローム)」とは、疲労や過度なストレスから、突然あらゆることへの気力や、感情の起伏を無くしてしまう状態です。脳の疲労や神経伝達物質のバランスが崩れることで発症するといわれており、自身の努力や心がけだけでは改善が難しいといわれています。
統合失調症
「統合失調症」とは、気持ちや考えがまとまらなくなる精神疾患です。脳機能が低下し、神経伝達物質の分泌異常が生じることで発症するといわれています。統合失調症の主症状は、抑うつ状態もしくはそれに近いものが多いです。発症後すぐのほか、治療を開始してしばらく経ってから抑うつ感が生じることもあります。
認知症
「認知症」になると、これまでできていたことができなくなり、症状の進行に伴い気持ちが落ち込んで抑うつ状態になることがあります。また認知症の中には、うつ病に似た様相を呈し、強い抑うつ状態に陥りやすい類型があることも報告されています。
抑うつ状態かもしれないと思ったら?
抑うつ状態かもしれないと思ったときは、次の3つの方法で対処しましょう。
- 精神科や心療内科を受診する
- 休養をとる
- 自身の状態を正しく把握する
精神科や心療内科を受診する
抑うつ状態の疑いがあるときは、すみやかに精神科もしくは心療内科を受診してください。心の不調は自分では気づきにくいこともあるため、自覚症状がなくても、周囲に異変を指摘されたときは医療機関を受診しましょう。
休養をとる
抑うつ状態を治すには、精神科や心療内科で治療を受けつつ、しっかりと休養をとることが大切です。ストレッサーと距離を置き、過度な心の負荷を解消する必要があります。睡眠時間や余暇を確保するほか、食事の栄養バランスや適度な運動などにも配慮することで、健やかな心を取り戻しやすくなるはずです。
自身の状態を正しく把握する
抑うつと診断されたときに大事なのは、自身が、今どのような状態にあるのかを正しく把握することです。症状は人それぞれ異なり、日や時間によって波があることも多いため、特性への理解を深めることで適切な対処法がみえてきます。
抑うつ状態と診断された後の働き方
ここでは、抑うつ状態と診断された後の働き方について、3つのケースに分けて解説します。
仕事と治療の両立が可能な場合:特性に応じた環境調整を行う
抑うつ状態になっても、特性に応じた環境調整と配慮を受けることで、治療と両立できる可能性が高まります。例えば、朝に抑うつ感が生じやすい場合は、それに合わせて勤務時間や業務量を調整することが有効です。また、抑うつが強く出たときに備え、職場で人目を気にせず休める場所を確保するとよいでしょう。
環境調整は自身の心がけでできる内容もありますが、職場の協力・配慮が不可欠なものもあるため、現在の状態を開示するのも一つの方法です。周囲の理解が得られれば、治療と仕事の両立がぐっとスムーズになります。
症状がひどく就業が難しい場合:休職して治療・休養を優先する
抑うつ感が強く、就業や通勤がままならないときは、休職を検討するのも一つの選択肢です。無理してはたらき続けると、症状が悪化し、さらに重篤な障害や疾患に発展しかねません。休職すれば、会社に籍を置いたまま治療と休養に専念できます。
ただし、休職制度の有無や、抑うつ状態が対象になるかどうかは、勤め先の就業規則によって異なります。休職制度がある場合、医師の診断書があると適用となる可能性が高まるので、医療機関に相談してみてください。
一時的に休むだけでは改善が難しい場合:退職・転職を検討する
症状が重篤にもかかわらず環境調整が難しいときや、仕事・職場が原因で抑うつ状態になった場合は、退職も視野に入れる必要があるかもしれません。治療・休養で一時的に回復しても、状況が変わらないと、再発や悪化の恐れがあるからです。医師や身近な人とも相談しつつ、自身の状態と治療に適した選択肢を考えてみるとよいでしょう。
退職し、症状が改善したら、復職を目指して少しずつ就活を進めていくこととなります。症状がひどく、一般就労が難しい場合には、障害者手帳の取得を検討することで、合理的配慮を得てはたらけます。障害者手帳が取得できない・しない場合でも利用できる障害福祉・就労サービスがあるので、活用すればより良くはたらける仕事が見つかりやすくなるはずです。
障害者雇用枠での転職を希望するなら「dodaチャレンジ」へ!

抑うつ状態は、過度なストレスから心身がヘトヘトになっている状態です。病気ではないからと無理して頑張りすぎると、より重篤な精神疾患に発展する恐れがあるため、軽視してはいけません。しかし見方を変えると、自分自身を見つめ直し、今後の働き方を見直すターニングポイントにもなり得ます。精神科や心療内科を受診して医師のアドバイスを仰ぐとともに、より良い仕事や働き方を探してみましょう。
抑うつ状態が悪化した方や、根源に別の精神障害・疾患がある場合は、障害者手帳を取得して障害者雇用枠ではたらくのも一つの道です。「dodaチャレンジ」では「一人ひとりが自分らしくはたらき続ける」ことをテーマとし、個々の特性・希望に応じた求人および就労サポートを提供しています。専任のキャリアアドバイザーがあなたと障害者雇用に積極的な企業をつなぐ架け橋となり、一般非公開を含む求人の紹介と就活に関する個別の相談に対応します。就職・転職にまつわるあらゆることを無料でサポートしますので、ぜひご利用ください。
お仕事をしていて
こんなお悩み
ありませんか?

-

コミュニケーションが
うまくいかない -
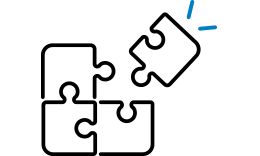
職場の人間関係が
よくない -

業務量が多すぎる
-

心身が不調
-
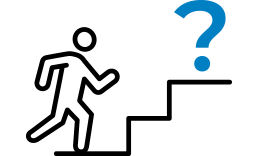
キャリアアップが
イメージできない -

自分に合う仕事が
わからない
転職について不安なことも
障害者雇用の知りたいことも
キャリアドバイザーが親身にお話をうかがいます
公開日:2025/9/1
- 監修者:戸田 幸裕(とだ ゆきひろ)
- パーソルダイバース株式会社 人材ソリューション本部 事業戦略部 ゼネラルマネジャー
- 上智大学総合人間科学部社会学科卒業後、損害保険会社にて法人営業、官公庁向け営業に従事。2012年、インテリジェンス(現パーソルキャリア)へ入社し、障害者専門のキャリアアドバイザーとして求職者の転職・就職支援に携わったのち、パーソルチャレンジ(現パーソルダイバース)へ。2017年より法人営業部門のマネジャーとして約500社の採用支援に従事。その後インサイドセールス、障害のある新卒学生向けの就職支援の責任者を経て、2024年より現職。
【保有資格】- ■国家資格キャリアコンサルタント
- ■障害者職業生活相談員


 記事をシェアする
記事をシェアする
