発達障害のグレーゾーンとは?仕事ができないと悩む大人のチェックポイント

発達障害という言葉が広く知られるようになり、特性への理解も進みつつあります。しかし、障害の度合いは人それぞれです。その中で、発達障害の傾向があっても確定診断がされないままの「グレーゾーン」が存在することをご存じですか。
この記事では、発達障害における「グレーゾーン」についてまとめました。よくある特性やその対処法、グレーゾーンにある方でも受けられる支援サービスも紹介します。
目次
発達障害の「グレーゾーン」とは
まず、発達障害のグレーゾーンとはどのような状態なのかを確認していきましょう。
発達障害のグレーゾーンの定義
発達障害の「グレーゾーン」とは、特性の傾向は認められるものの、正式に診断するに足る医学的根拠がない状態を指します。黒でも白でもない、曖昧な状態であることからその病名がつけられました。つまり、グレーゾーンと診断された場合、正確には発達障害とはいえず、障害者手帳の取得もできません。
発達障害の症状には幅があるため、医師の見解や受診時の体調などから、診断基準を満たさないと判断されていることもあると考えられるでしょう。本記事では「グレーゾーン」を正式な診断名・疾患名ではなく、状態をあらわす概念として記載しています。
そもそも「大人の発達障害」とは?
発達障害とは、脳の機能障害により、発達に凹凸が生じる精神障害です。幼少期では診断が難しく、特性を見逃したまま成長し、それが大人になって表面化する「大人の発達障害」も問題視されています。
なお、発達障害の主な区分は「ASD」「ADHD」「LD」の3種類です。個人差はありますが、それぞれに共通する特徴的な傾向がみられます。ここでは、各障害の特性をみていきましょう。
ASD(自閉スペクトラム症)
自閉スペクトラム症(ASD)とは、対人コミュニケーションの困難や強いこだわりと偏った興味・関心、感覚過敏を特性とする発達障害です。状況の急な変化や苦手なことにうまく対応できず、パニックや癇癪を起こしやすいという特徴があります。
大人のASD(自閉スペクトラム障害)とは?特徴や特性を活かした働き方や支援サービスをご紹介
ADHD(注意欠陥・多動症)
注意欠陥・多動症(ADHD)とは、不注意・多動性・衝動性の3つを特性とする発達障害です。集中力や注意力が乏しく、感情・欲求のコントロールがうまくできません。優位な特性には個人差がありますが、生活やコミュニケーションでさまざまな困難が生じます。
ADHDのある方に向いている仕事とは?「できない」を「できる」に変えるヒント集
LD(学習障害)
学習障害(LD)とは、知的な発達の凹凸はないものの、文字の読み書きや計算など特定の学習が困難になる発達障害です。脳の情報処理・伝達上で生じた異常が原因だといわれており、苦手な分野は練習しても習得が難しいといわれています
大人の発達障害とは?症状の特徴や対処法、二次障害への影響について
「グレーゾーン=症状が軽い」ではない
グレーゾーンだからといって、それを軽視してよいわけではありません。あくまで医学的な診断基準を満たしていないだけで、自分の意思ではどうにもならない症状や困り事に悩んでいる方もたくさんいるでしょう。なかには、発達障害のある方と同程度の支援を要するケースもあります。
発達障害のグレーゾーンにある方が仕事上で辛いと感じる5つのこと
発達障害のグレーゾーンにある方は、仕事をする上で、よく次のような悩みを抱えています。
- 仕事の段取りがうまくできない
- あいまいな指示が理解できない
- ミスや遅刻を繰り返してしまう
- 人間関係で悩みやすい
- 合理的配慮が得られない
仕事の段取りがうまくできない
発達障害のグレーゾーンにあると、状況を読んで優先順位をつけることが難しいという方が多いです。つい好きなことや興味がある作業を優先してしまい、後の業務に支障をきたしてしまうことがあります。また、工程の全体像をイメージしたり、マルチタスクをこなしたりすることが苦手です。イレギュラーな出来事への臨機応変な対応も難しく、急な予定変更があるとパニックになってしまいやすくなります。
あいまいな指示が理解できない
発達障害のグレーゾーンにあると、あいまいな内容から、やるべきことを判断するのが難しい傾向にあります。「適当に」「良い感じに」などの漠然とした指示では、何をどうすればよいのか分かりません。「普通は通じるだろう」という固定観念から、本人の努力だけではどうにもならず悩んでいる方も多いでしょう。
ミスや遅刻を繰り返してしまう
発達障害の傾向のある方は、気をつけているつもりでも、ケアレスミスを繰り返してしまいがちです。集中力が続かなかったり、細部まで注意が行き届かなかったりするほか、一つのことにこだわり過ぎて初動が遅れ、ミスや遅刻につながることもあります。また、時間という抽象的な概念がうまく理解できないので、予定から逆算して見通しを立てるのも不得意です。
人間関係で悩みやすい
発達障害のグレーゾーンにある方は、コミュニケーションにその特性が強く表れやすい傾向にあります。会話のキャッチボールが苦手で、雑談にうまく入れません。また、適切な距離感をつかんだり、言葉の裏を読んだりするのが難しく、悪気なくとった行動が意図せず相手を傷つけてしまうこともあるでしょう。上手にコミュニケーションがとれないことで、人間関係の悪化を招くことも少なくありません。
合理的配慮が得られない
グレーゾーンは医学的な病名ではないため、発達障害の傾向があっても、社会的には健常者とみなされます。本来であれば、発達障害の傾向がある方には適切なサポートが必要となるところ、医学的な根拠なしには公的な支援や合理的配慮が行き届きません。また、グレーゾーンの特性について、周囲に理解を求めることも容易ではないでしょう。
発達障害のグレーゾーンにある方は二次障害に注意を
発達障害のグレーゾーンにある方は、仕事や人間関係が思うようにいかないことで精神的に追い詰められ、うつ病やパニック障害などの二次障害につながることがあります。幼少期の失敗や挫折、叱られ続けた経験の積み重ねで自信をなくし、二次障害を発症するケースも少なくありません。特にグレーゾーンにあると、通常の発達障害に輪をかけて周囲からの理解が得られにくい傾向にあるため、それがネガティブにはたらく恐れがあります。
普段にない心身の不調や異変を感じたときは、速やかに医療機関を受診してください。早期の対処で、二次障害の発症および悪化を防げる可能性が高まります。
発達障害のグレーゾーンにある方が仕事上の困り事を減らすためにできること

発達障害のグレーゾーンにあっても、次のような心がけや対策で、仕事上の困り事が減らせるでしょう。
- 自らの障害特性の傾向を正しく把握する
- 再検査を受ける
- 障害者手帳がなくても利用できる支援サービスを活用する
自らの障害特性の傾向を正しく把握する
発達障害のグレーゾーンにある方は、自身の特性を正しく理解し、適切な対処法を考えることが大切です。特性の傾向に応じた対策を立てることで、得意を仕事に活かし、不得意をカバーできます。
また、発達障害の傾向は、見方を変えると強みになるかもしれません。例えば、強いこだわりは探究心や粘り強さ、衝動性は好奇心の強さや思い切りの良さと言い換えられます。特性を強みとして活かせる仕事に就くことで、自分らしい働き方が実現するでしょう。
ヘルプマークを活用する
発達障害のグレーゾーンにあることで、日常生活に関する不安を抱えている場合は「ヘルプマーク」活用をおすすめします。ヘルプマークとは、病気や障害に対する配慮を必要とすることを周囲に知らせるための制度です。
例えば、通勤や仕事での外出などで特性による発作やトラブルが起きたとき、ヘルプマークがあれば周囲に適切な対応が促せます。ヘルプマークの利用を検討している方は、自治体や公共交通機関の窓口などに問い合わせてみてください。
再検査を受ける
発達障害の傾向が顕著で、生活や仕事に支障をきたしている場合は、再検査を受けてみることをおすすめします。特性の現れ方には波があり、受診時の体調によって診断基準を満たさないと判断されている可能性があるからです。また、前回の診断時には問題がなくても、二次障害を発症していることもあります。
くわえて、診断は医師の判断に委ねられるため、結果に不安や思うところがある場合は、発達障害の専門医にセカンドオピニオンを求めてみるのも一つの方法です。多角的な視点からアドバイスを受けることで、より良い対処法や治療法が見つかるかもしれません。
障害者手帳がなくても利用できる支援サービスを活用する
基本的に、発達障害の支援制度は確定診断を受けていることを前提としており、グレーゾーンにある方は対象外です。しかし、障害福祉サービスの中には、障害者手帳がなくても利用できるものも存在します。現在、障害者手帳を未取得でも利用できる主な就労支援サービスには、以下のようなものがあります。
| 支援サービスの種類 | 概要 |
|---|---|
| ハローワーク | グレーゾーンの特性を考慮した就労アドバイスが受けられる |
| 発達障害者支援センター | 障害のある方およびその関係者へ生活や仕事をはじめとする包括的な相談・支援や情報を提供する |
| 障害者就業・生活支援センター | 障害のある方の生活改善・自己管理の方法などの職業準備性を高めるサポートが得られる |
| 就労移行支援事業所 | 一般就労を目指してビジネススキルやマナーが学べる |
就労移行支援事業所といったサービスの利用の際は「障害福祉サービス受給者証」が必要となる場合があります。障害福祉サービス受給者証の申請の際は、お住まいの自治体の障害福祉窓口に相談してみてください。
なお、大人の発達障害のグレーゾーンにあり、自身の得意分野を就労に活かしたいと考えているなら「Neuro Dive(ニューロダイブ)」で学んでみませんか。Neuro Diveは、AIやデータサイエンスなどの4領域の先端ITスキルから、特性や興味に合う分野を選んで身につけられる就労移行支援事業所です。独自の「ダブルマップ・メソッド」と就活支援「キャリアアシスト」により、自分らしくはたらくためのスキル習得と仕事探しをお手伝いします。各カリキュラムとの適正がWebでセルフチェックできるので、ぜひ確認してみてください。
発達障害のグレーゾーンにあっても工夫次第でより良くはたらける!

発達障害のグレーゾーンゆえの困りごとも多いでしょう。しかし、特性があるからこその強みもあるはずです。特技や興味が活かせる仕事を見つけることで、就業上の困り事が減らせるかもしれません。障害者手帳がなくても利用できる障害福祉サービスを活用して、周囲への理解を促し、自分らしくはたらける方法を探してみてください。
公開日:2022/12/27
更新日:2025/6/25
- 監修者:戸田 幸裕(とだ ゆきひろ)
- パーソルダイバース株式会社 人材ソリューション本部 事業戦略部 ゼネラルマネジャー
- 上智大学総合人間科学部社会学科卒業後、損害保険会社にて法人営業、官公庁向け営業に従事。2012年、インテリジェンス(現パーソルキャリア)へ入社し、障害者専門のキャリアアドバイザーとして求職者の転職・就職支援に携わったのち、パーソルチャレンジ(現パーソルダイバース)へ。2017年より法人営業部門のマネジャーとして約500社の採用支援に従事。その後インサイドセールス、障害のある新卒学生向けの就職支援の責任者を経て、2024年より現職。
【保有資格】- ■国家資格キャリアコンサルタント
- ■障害者職業生活相談員
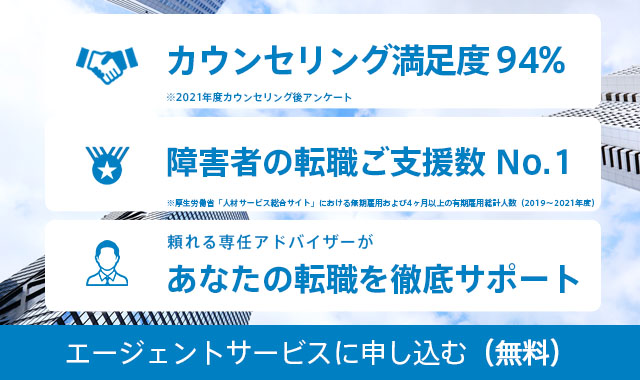

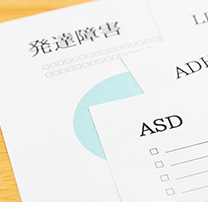

 記事をシェアする
記事をシェアする
