障害者雇用とは?障害者雇用を利用するメリット・デメリットや制度をわかりやすく解説

「障害者雇用」は、障害のある人がそれぞれの障害特性に合わせてはたらけるように、企業が一般の雇用枠とは別枠で雇用することを指します。しかし「障害者雇用と一般雇用の違い」や「障害者雇用ではたらく方法」など、分からないこともあるのではないでしょうか。
そこで本記事では、障害者雇用の特徴やメリット、利用できる支援機関・サービスなど、制度について詳しく解説します。
目次
障害者雇用とは
障害者雇用について、まずは次のポイントから概要を見ていきましょう。
- 障害者雇用の意味
- 障害者雇用の対象者
- 障害者雇用ではたらく目的
障害者雇用の意味
「障害者雇用」とは、身体障害・精神障害・知的障害がある人を、一般雇用とは別枠で雇用することを指します。障害がある人が健常者と同じ条件ではたらくことは、障害特性や体調などの影響で難しいケースが少なくありません。
そこで後述する「障害者雇用促進法」によって、障害者の職業の安定を図るために、障害者雇用を促進するための取り組みが行われています。これにより、障害のある人が一人ひとりの特性に合わせてはたらける機会が得やすくなるのです。
障害者雇用の対象者
障害者雇用の対象となるのは、原則として障害者手帳を取得している人のみです。障害者手帳には障害の内容により、「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があります。
障害者手帳は条件を満たすことで交付されますが、その名称は自治体によって異なる場合があります。また、障害者手帳を所有している場合でも、一般雇用枠の求人に応募することは可能です。
障害者雇用ではたらく目的
障害者雇用では、企業が「障害があること」を前提に採用しているため、障害のある方が自身の障害を開示することで、一般雇用枠よりも「合理的配慮」を受けやすくなります。
合理的配慮とは、障害者から何らかのサポートを求める意思表示があったとき、過度な負担にならない範囲で合理的な対応をすることです。この合理的配慮の提供は、2016年の障害者雇用促進法の改正により雇用主に対して義務化されています。これにより、障害特性・症状や苦手なことについて周囲の理解を得て、仕事内容や体調などの面で配慮を受けて、安定してはたらきやすくなるのです。
障害者雇用は「障害者雇用促進法」の取り組みのひとつ
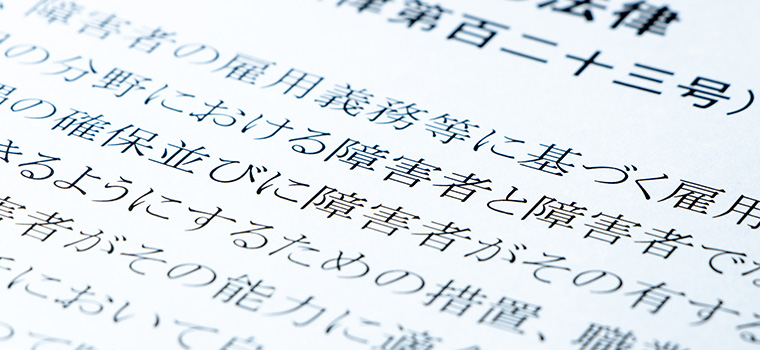
障害者雇用は「障害者雇用促進法」で指定されている取り組みのひとつです。障害者雇用促進法の正式名称は「障害者の雇用の促進等に関する法律」であり、障害のある人の職業の安定を実現するために、次のような取り組みが行われています。
- 雇用義務制度
- 職業リハビリテーション
- 合理的配慮の提供
雇用義務制度
雇用義務制度として、「障害者雇用率制度」と「障害者雇用納付金制度」の2つが実施されています。
障害者雇用率制度は、障害のある人を一定以上の割合で雇用することを義務付けるものです。その割合は一般的に「法定雇用率」と呼ばれており、従業員を40人以上雇用している事業主が対象です。この法定雇用率は令和7年時点で2.5%となっており、令和8年7月には2.7%になるなど段階的な引き上げが続いています。
障害者雇用納付金制度は、法定雇用率を達成できない企業から納付金を徴収し、それを財源として法定雇用率を超えて雇用している事業主に助成金を支給する制度です。障害者の雇用促進を図ることが主な目的で、常用労働者数が100人を超える企業が対象となります。
職業リハビリテーション
「職業リハビリテーション」は、障害者の職業生活における自立を支援するためのもので、「ハローワーク」「地域障害者職業センター」「障害者就業・生活支援センター」で実施されています。各施設では、次のようなサポートを受けることができます。
| ハローワーク | 職業相談や定着支援 |
| 地域障害者職業センター | 職業を選ぶためのアドバイス |
| 障害者就業・生活支援センター | 就業や生活に関する相談への対応 |
合理的配慮の提供
前述したように、合理的配慮の提供は雇用主に義務付けられています。これは障害のある人が必要とするサポートを企業が提供できるようにすることで、障害の有無に関わらず労働機会が得られるようにするためのものです。合理的配慮の例としては、車椅子の利用者が通勤ラッシュを避けるために時差出勤を認めたり、通院のために勤務時間・休暇を調整したりすることなどが挙げられます。
一般雇用と障害者雇用の違い
一般雇用と障害者雇用には、次のような違いがあります。
- 求人の数や種類
- 障害への配慮
- 就職後の定着率
求人の数や種類
一般雇用は職種や求人数が豊富で、障害者手帳の有無に関わらず応募できます。障害があって障害者手帳を所有している場合でも、障害について企業に開示せずはたらくことも可能です。一方で、障害者雇用は障害者手帳がある人のための雇用枠ですが、職種や求人数は一般雇用と比較すると少ない傾向があります。
障害への配慮
一般雇用ではたらく場合は、障害について開示せずにはたらく場合と、開示してはたらく場合があります。開示せずに就労しているは、企業側が障害特性について把握していないため、障害への配慮を受けることはできません。
障害をオープンにして就労する場合でも、障害があることを前提とした求人ではないため、障害に対する理解や配慮が得づらい可能性があります。障害者雇用を利用していれば、障害特性や症状に合わせた合理的配慮がよりいっそう受けやすいため、安心してはたらくことができるでしょう。
就職後の定着率
一般雇用と障害者雇用では、就職後の定着率が大きく異なることも重要です。厚生労働省の「障害者雇用の現状等」によると、障害者雇用枠の1年後の定着率は70%前後となっています。しかし、一般雇用枠における障害者の定着率は、障害を開示していた場合でも約50%、開示していない場合は約30%と、障害者雇用枠に比べて低い傾向があります。
障害者雇用ではたらくメリット

障害者雇用ではたらくメリットとして、次のようなものが挙げられます。
- 安心してはたらきやすくなる
- 一般雇用より就職しやすい
安心してはたらきやすくなる
前述したように、障害者雇用では合理的配慮の提供により、業務内容や働き方などの柔軟な対応が受けられるため、一般雇用と比べて障害特性と付き合いながらはたらきやすくなります。万が一、障害の症状や体調が悪化した場合にほかの人のサポートが受けられるなど、安心して就労できる環境が手に入ることが大きなメリットです。
また、障害がある人は「障害特性が理解されない」「ほかの人に迷惑をかけてしまう」ことなどを恐れ、精神的なストレスを抱えやすい傾向があります。障害者雇用の場合は、障害特性に関する周知が行われるため、精神的な負担も軽減できるでしょう。
一般雇用より就職しやすい
一般雇用とは異なり、障害者雇用では障害のある人を採用することが前提であるため、業務内容が取り組みやすいものになっている傾向があります。障害者雇用は求人数が少ないため、「狭き門」のようなイメージがあるかもしれませんが、前述したように法定雇用率の引き上げなどの背景によりむしろ「受かりやすい」可能性があります。
なお、障害者雇用枠の受かりやすさや採用されるためのコツについては、次の記事で詳しく解説しているのでぜひご参照ください。
障害者雇用ではたらくデメリット・注意点
障害者雇用ではたらくことを検討する際は、次のようなデメリットに注意しましょう。
- 職種や業務内容の選択肢が少ない
- 「正社員雇用」の求人が少ない
職種や業務内容の選択肢が少ない
障害者雇用では合理的配慮などの観点から、業務内容が調整されることが多いです。一方で、これは職種の選択肢が少ないことでもあり、自身の経験やスキルを最大限に活かしたり、キャリアアップを目指したりする場合は、むしろ満足できない可能性があります。
ただし、例えば「発達障害がある人はIT系職種が向いている」といわれるなど、障害特性をうまく活かして魅力的な職種が選べるケースもあります。ご自身の障害特性や適した職種・職場などが分からない場合は、後述する「障害者向けの転職エージェント」のキャリアアドバイザーに相談してみるといいでしょう。
「正社員雇用」の求人が少ない
障害者雇用は正社員雇用の求人が少なく、一般的には非正規雇用が多い傾向があります。例えば、障害特性や症状の影響で安定就労やフルタイム勤務が難しいなどの理由が背景にあります。必ずしも正社員ではたらくことが適しているとは限らないので、まずは非正規雇用で仕事に慣れてから正社員登用を目指すなどの選択肢も有効です。
なお、障害のある人が正社員ではたらくことが難しいといわれる理由や、正社員としてはたらく方法については、次の記事も併せてご参照ください。
障害者雇用ではたらく方法・利用できる支援機関とサービス

障害者雇用ではたらくためには、次のような支援機関やサービスを利用するのがおすすめです。
- ハローワークの障害者関連窓口
- 就労移行支援事業所
- 障害者向けの転職エージェント
ハローワークの障害者関連窓口
全国のハローワークには、障害がある人のための「障害者関連窓口」が設けられており、障害のある方が就労に関するさまざまな相談ができます。専門知識がある担当者の対応が受けられるため、ご自身の障害特性や症状に合う求人が見つかりやすいことが魅力です。履歴書作成や面接対策など、転職活動に必要なサポートも受けられます。
就労移行支援事業所
就労移行支援事業所は、はたらくための知識やスキルの習得に加えて、就職・転職活動のサポートを求職者に提供している機関です。就職・転職後も「定着支援」として困りごとや悩みの相談ができるので、障害との付き合い方にお悩みの方も安心して利用できます。
パーソルダイバースが運営するの「ミラトレ」は、障害のある方の適切な就労をかなえるための就労移行支援事業所です。適職に就いて安定したはたらき方を実現するために、さまざまな支援を行っておりますので、まずはお気軽に見学・ご相談ください。
障害者向けの転職エージェント
障害のある方が自分に合う仕事・職場を見つけるためには、「障害者向けの転職エージェント」の活用がおすすめです。障害に関する専門知識と豊富なサポート実績があるキャリアアドバイザーに相談することで、どのような仕事・職場ではたらくのが向いているかなどの相談や、さまざまなサポートが受けられます。もちろん、障害者雇用の求人紹介も受けられます。
障害のある方が就職・転職を目指すときは、障害に対する理解が適切に得られるような職場が見つかるかどうか不安があるでしょう。障害者向けの転職エージェントでは、ご自身の障害特性や症状への理解を深めることができるため、合理的配慮に関する事項を明確化して「はたらきやすい環境」での就労をかなえることができるでしょう。
障害者雇用ではたらく人の事例
障害者向けの転職エージェント「dodaチャレンジ」を活用し、理想の就労・転職をかなえた方の事例をご紹介します。
- 聴覚障害|障害者雇用での転職で年収100万円アップ
- 双極性障害|時短勤務・完全在宅など無理のないはたらき方を実現
- うつ病|再発を繰り返さないために特例子会社で安定就労へ
聴覚障害|障害者雇用での転職で年収100万円アップ
Aさんは社会人になってから聴力が低下し、合理的配慮が受けやすい職場に転職するために、dodaチャレンジの転職支援サービスを利用しました。現職ではたらきながら転職活動を行いましたが、キャリアアドバイザーによる提案や、書類作成や面接対策などのサポートにより3ヶ月で年収100万円アップの転職に成功しました。
納得のいく転職を実現するためにAさんが意識したのは、配慮事項を明確化することです。「電話対応はできない」「会議はオンラインツールが必須」など、できないことや必要なものを明確化することで、はたらくために必要な合理的配慮を企業が提供しやすくなります。そのために欠かせないのが、経験豊富なキャリアアドバイザーによるきめ細やかなサポートなのです。本事例の詳細については次の記事をご参照ください。
双極性障害|時短勤務・完全在宅など無理のないはたらき方を実現
Bさんは社会人になってから双極性障害を発症して休職し、症状が安定して主治医の許可が出たあとで転職活動に取り組みました。Bさんは「時短勤務」と「通勤時間の短さ」を意識していましたが、dodaチャレンジのキャリアアドバイザーがさらに重視したのは「これまでの経験を活かせるキャリア選択」です。
マスコミ業界での事務アシスタントとして、満足のいく転職を実現できましたが、新型コロナウイルスの蔓延により心身が不安定になってしまいました。それから2回目の転職としてdodaチャレンジを通じて出会ったのが、インターネット広告会社の求人です。契約社員としてまずは時短勤務から徐々に慣らし、フルタイム勤務への移行に成功しました。Bさんの現在の目標は正社員へのチャレンジです。本事例の詳細については次の記事をご参照ください。
うつ病|再発を繰り返さないために特例子会社で安定就労へ
Cさんは50代になってから、過労や寝不足によるストレスからうつ病を発症しました。休職して療養に努め、半年後に焦りから転職しましたが、うつ病が完治しておらず再発してしまいました。それから障害者手帳を取得し、自立支援のデイケアサービスや就労移行支援事業所に通所し、うつ病の治療と症状の安定化に専念しました。
転職のために登録したdodaチャレンジでは、「特例子会社」への求人に応募しました。その際に役立ったのが、キャリアアドバイザーによるきめ細やかな転職支援です。Cさんの経歴・スキルや障害特性・適正などを理解したマッチングにより、はたらきやすい理想の環境を手に入れることができたのです。本事例の詳細については次の記事をご参照ください。
障害者雇用に関するよくある質問

障害者雇用に関するよくある質問についてまとめました。障害者雇用ではたらくことを検討する際にご活用ください。
- 障害者雇用は「単純作業」ばかり?
- 障害者雇用の収入は具体的にどれくらい?
- 障害者雇用では障害者だけのチームではたらくのか?
- 障害者雇用では障害に関するすべてが社内で知られてしまう?
障害者雇用は「単純作業」ばかり?
障害者雇用の仕事内容というと、工場での仕分け・検品・梱包などのような「軽作業」という印象があるかもしれません。かつては障害に関する理解が乏しい企業が多く、「単純な作業しか任せられない」という誤解がありましたが、近年では個々の特性・能力に合わせたポジションを提供できるケースが増えています。
仕事内容について心配な場合は、先ほど紹介した障害者向けの転職エージェントを活用することで、専門知識のあるキャリアアドバイザーが適切な職種・キャリアを提案してくれるでしょう。
障害者雇用の収入は具体的にどれくらい?
一般雇用と比べると、確かに障害者雇用の収入は低い傾向にあります。厚生労働省の「令和5年度障害者雇用実態調査」によると、平均月収は障害の種類別に次のとおりです。
| 障害の種類 | 平均賃金 | 前年比(前回の数値) |
|---|---|---|
| 身体障害 | 23万5千円 | +2万円(21万5千円) |
| 知的障害 | 13万7千円 | +2万円(11万7千円) |
| 精神障害 | 14万9千円 | +2万4千円(12万5千円) |
| 発達障害 | 13万円 | +3千円(12万7千円) |
前年比で上昇しているとはいえ、一般雇用と比べると全体的に低く、身体障害とそれ以外では10万円近い差があることが特徴です。なお、障害者雇用における給与水準の詳細については、次の記事も併せてご参照ください。
障害者雇用では障害者だけのチームではたらくのか?
企業や部署により、どのような編成で働くことになるかは異なります。例えば「特例子会社」の場合は、そもそも障害者雇用の推進のために設立されたものなので、チームメンバーの大半が障害者ということが珍しくありません。
一般企業の障害者雇用でも、障害者雇用チームのようなものがある場合も中にはありますが、既存部門に配置されて障害者は自分ひとりというケースもあります。配置や編成について気になる場合は、就職活動・転職活動の際に企業の担当者などに質問してみるとよいでしょう。
障害者雇用では障害に関するすべてが社内で知られてしまう?
個人の障害特性については、業務における合理的配慮が必要な範囲のみ、社内で共有されます。開示する範囲は自身で決めることができるので、開示したくない部分は開示する必要はなく、自身が同意しなければ開示内容を社内で勝手に共有されることは基本的にはありません。
必要以上に配慮や特別扱いをされたくないなどの場合は、そのことを人事部などにあらかじめ伝えておきましょう。ただし、障害特性や症状についてはある程度は社内で知っておいてもらわなければ、いざというときに適切なサポートが受けづらくなるので注意が必要です。
障害者雇用ではたらくなら「dodaチャレンジ」をご利用ください

障害者雇用で就労することで、合理的配慮を得ながら安心してはたらけるようになります。一方で、一般雇用と比べて職種・業務内容の選択肢が少ない傾向がありますが、支援機関やサービスを活用することで、ご自身の障害特性や適正に合わせた仕事が探しやすくなるでしょう。
障害のある方が就労・転職を目指すときは、パーソルダイバースの転職支援サービス「dodaチャレンジ」がおすすめです。さまざまな障害に対する専門知識があるキャリアアドバイザーが、あなたの「障害特性や症状への理解が得られるか」「それに適した就労環境が見つかるか」という不安と向き合い、理想の就労・転職をかなえるサポートをいたします。
dodaチャレンジのご利用者の約8割が「転職は期待どおり・期待以上」と答え、約85%が「今後もその職場ではたらき続けたい」と思うなど、満足度・定着率の高い転職を実現しています。dodaチャレンジの利用は無料なので、転職をお考えの方はこの機会にぜひご相談ください。
まずは、キャリアアドバイザーに転職相談を

電話orオンライン
でお気軽にご相談ください
転職について不安なことも
障害者雇用の知りたいことも
キャリアドバイザーが親身にお話をうかがいます
公開日:2025/7/31
- 監修者:戸田 幸裕(とだ ゆきひろ)
- パーソルダイバース株式会社 人材ソリューション本部 事業戦略部 ゼネラルマネジャー
- 上智大学総合人間科学部社会学科卒業後、損害保険会社にて法人営業、官公庁向け営業に従事。2012年、インテリジェンス(現パーソルキャリア)へ入社し、障害者専門のキャリアアドバイザーとして求職者の転職・就職支援に携わったのち、パーソルチャレンジ(現パーソルダイバース)へ。2017年より法人営業部門のマネジャーとして約500社の採用支援に従事。その後インサイドセールス、障害のある新卒学生向けの就職支援の責任者を経て、2024年より現職。
【保有資格】- ■国家資格キャリアコンサルタント
- ■障害者職業生活相談員
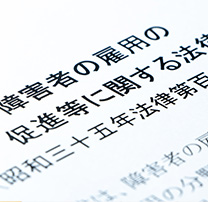



 記事をシェアする
記事をシェアする
