さまざまな分野で活躍するITエンジニアを紹介する
ギークアカデミー(GEEK ACADEMY)!
インタビューを通して、皆さんが参考にできる
"エンジニアとして成長するためのポイント"を探っていきます。
![]()
 |
“本当はすごいエンタープライズIT”について話そう(前編)
|
![]()
 |
社会人でプログラミングを始めレッドコーダーに、フラッシュメモリのファームウェア開発に能力を発揮(前編)
|
 |
HDDからSSDへの時代の変わり目に、タイミング良く大容量・コンパクトなSSD新製品を投入したい(後編)
|
![]()
 |
他者から観測可能な自分の価値を高める(前編)
|
![]()
 |
中学時代からゲームで稼ぎ、「君たち会社作ってよ」で起業(前編)
|
![]()
 |
「どうしてもシリコンバレーで働きたい!」(前編)
|
![]()
 |
「CG/VFX業界ではPythonが標準言語に」(前編)
|
![]()
 |
まつもとゆきひろインタビュー
|
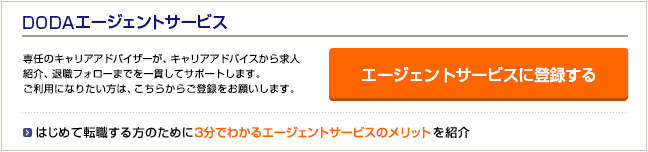
|
エンジニア特有の転職成功ノウハウや市場動向をご紹介 |
||
|
インフラ領域特有の転職成功ノウハウや市場動向をご紹介 |
||
|
クリエイター転職特有のノウハウ・事例などご紹介! |
||
|
先端を走る技術を、ギークに学ぶ |

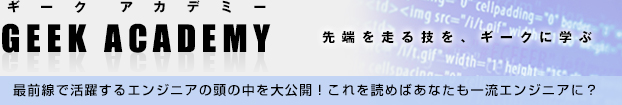
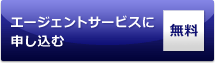
![あなたの“本当の年収”や今後の“年収推移”も分かる!年収査定サービス[無料]](/cmn_web/img/bnr/nensa_bnrb.jpg)