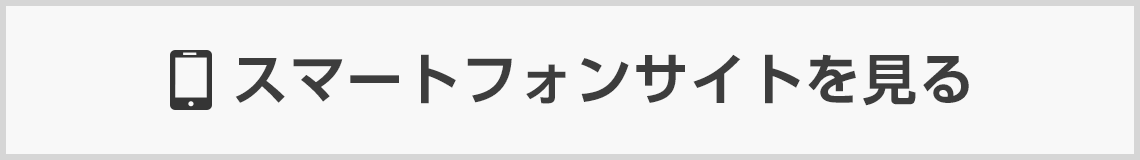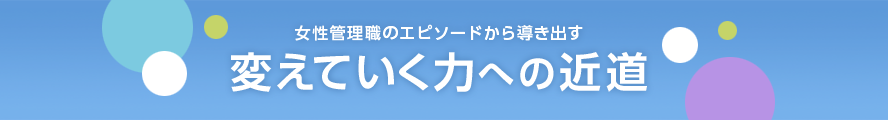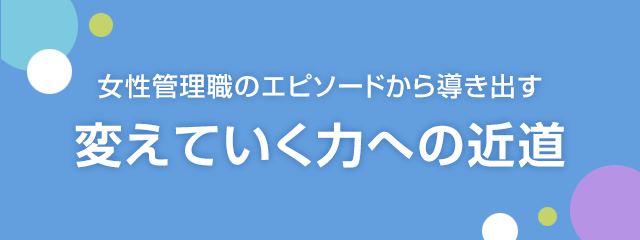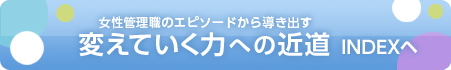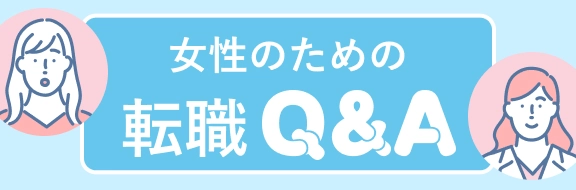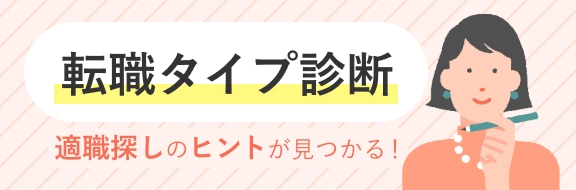めまぐるしく変化する経営環境のもと、企業をはじめ職場や人もまた、絶え間なく変わっていくことが求められています。そんな中、管理職として、身近な人や職場、ビジネスを変え続けている女性たちがいます。彼女たちが変えてきたもの、そして、彼女たちに影響を与えてきたものとは何なのか。今回は、「対顧客」「組織・職場運営」「人材マネジメント」「自分の価値観」の4つの観点で、それぞれのエピソードをひも解き、「変えていく力」を発揮するためのヒントを見出します。
※この記事は2015年3月に発行した株式会社パーソル総合研究所の機関紙・別冊『HITO』でまとめた記事をWoman Careerが再編集しました。
※所属や肩書きは取材当時のものです。
掲載日:2015年12月17日
川嶋 由美子(36歳)
パーソルキャリア株式会社
dodaキャリアアドバイザー ゼネラルマネジャー
※所属や肩書きは取材当時のものです
「対顧客」「組織・職場運営」「人材マネジメント」「自分の価値観」という4つの観点から女性管理職のエピソードを伺ってきた本連載。最終回に登場するのは、dodaのキャリアアドバイザーとしてキャリアを積んだ後、現在は時短勤務のマネジャーを務める、パーソルキャリア株式会社 dodaキャリアアドバイザー ゼネラルマネジャーの川嶋由美子です。20代から30代で変化してきた仕事へのモチベーションと、多様性を重視した部下のマネジメント方法を聞きました。
パーソルキャリア株式会社
求人情報サービス「an」「salida」、転職サービス「doda」など求人メディアの運営、人材紹介、人材派遣、求人情報を提供する総合人材サービス会社。「はたらくを楽しむ社会」の実現に向けてインフラとしての人材サービスを提供する。
育児休暇を経て、仕事のモチベーションが「社会貢献」に
 入社から3年弱は、エンジニアの人材派遣をサポートする法人営業を担当していました。その後、もともと希望していたキャリアアドバイザーになることができ、営業職、事務職、販売・サービス業の方々の転職を支援する部署に配属されました。そこでキャリアアドバイザーとマネジャーを経験し、2度の産休・育休を取得。現在は時短勤務のゼネラルマネジャーとして、ITエンジニアの転職支援を手がけるコンサルタント35名(取材当時)を束ねています。
入社から3年弱は、エンジニアの人材派遣をサポートする法人営業を担当していました。その後、もともと希望していたキャリアアドバイザーになることができ、営業職、事務職、販売・サービス業の方々の転職を支援する部署に配属されました。そこでキャリアアドバイザーとマネジャーを経験し、2度の産休・育休を取得。現在は時短勤務のゼネラルマネジャーとして、ITエンジニアの転職支援を手がけるコンサルタント35名(取材当時)を束ねています。
初めてマネジャーを任されたのは入社5年目です。当時は出産前だったので、もちろんフルタイムで働いていました。その頃は、とにかく現場に強いマネジャーでありたいという思いが強く、一人のコンサルタントとして、部下に背中を見せていくマネジメントスタイルを取っていました。業務も時間をかけて行うというやり方でしたね。20代だったこともあり、どうしても周りと比較して自分を評価することでモチベーションを保つ傾向がありました。
しかし、30代に入って、目線が周りとの比較から社会貢献に変わりました。きっかけは、育児休暇中に「自分は社会とつながっていないのではないか」「社会に貢献できていないのではないか」という不安を抱いたことです。そこで自分の仕事を振り返った時に、転職を希望する方にキャリアカウンセリングを通して喜んでもらえることや、新たな社員の入社をお手伝いすることで企業の活性化を生み出せていることは、社会貢献の1つであると気付きました。もちろん、自分のマネジメントによって部下が活き活き働けるようになったりすることにも、社会に貢献している面があります。そこで生まれた社会的使命感は、今の自分にとって大切なモチベーションとなっていますね。
徹底した事前準備で時間の無駄をなくす
部下とのコミュニケーション方法も工夫するように
 育休後は時短勤務で働くこととなり、業務では事前準備を徹底するようになりました。時間の無駄をなくすことで、限られた勤務時間内であっても最大限の働きができるようにするためです。出社した瞬間からほぼ隙間なく予定が入っているので、ミーティング前に資料を見直して考えをまとめる時間はありません。次の日のミーティングのアジェンダは事前に用意し、細かい確認事項や問題提起などはメモを作っておくことで、確認漏れがないようにしておきます。相手にも準備が必要なミーティングであれば事前に問題を共有し、お互いにミーティングが始まった瞬間にはスイッチが入る状態にしていますね。
育休後は時短勤務で働くこととなり、業務では事前準備を徹底するようになりました。時間の無駄をなくすことで、限られた勤務時間内であっても最大限の働きができるようにするためです。出社した瞬間からほぼ隙間なく予定が入っているので、ミーティング前に資料を見直して考えをまとめる時間はありません。次の日のミーティングのアジェンダは事前に用意し、細かい確認事項や問題提起などはメモを作っておくことで、確認漏れがないようにしておきます。相手にも準備が必要なミーティングであれば事前に問題を共有し、お互いにミーティングが始まった瞬間にはスイッチが入る状態にしていますね。
部下とのコミュニケーションについても、限られた時間で計画的に話をするようになりました。例えば、部下のキャリアカウンセリングに同席する時には、転職を希望する方とのキャリアカウンセリングに1時間半、それを受けて部下に対してフィードバックを行うのに30分と、計2時間が必要です。時短勤務での2時間はとても大きいので、1回の同席を通して部下にたくさんの指導ができるよう、山のようにメモを取りますね。ただし、フィードバックではすべてを一度に伝えるのではなく、計画的に伝えることで部下が受け止めやすくなるようにしています。
また、週に一度の「ウィークリーレポート」も実践しています。業務の報告をレポート形式で提出してもらい、私が全員にフィードバックするというものです。目的は、レポートとフィードバックの往復を通して、部下の内省を促すこと。マネジメント上、コミュニケーション量を確保するという意味でも、部下がレポートを書き、それを私がフィードバックするというのは重要ですし、上司に直接思いを伝える機会があると、部下の自己表現欲求も満たされると思います。お互いに何を重視し、どんな理念を持って業務に取り組んでいるのかというレベルでの目線合わせにもなっていますね。
「人と比較しない」「部下と向き合う」ことで個人の強みを認め、多様性を活かすマネジメントへ
 部下のマネジメントという点では、多様性を活かすことを重視しています。私は社内で初の時短勤務のマネジャーだったため、最初は"異端"である自分を感じていました。しかし、他のマネジャーとは違うことを「申し訳ない」と思うのではなく、"異端"である自分を活かそうと決めたことをきっかけに、部下に対しても多様性を活かすマネジメントをするようになったのです。マネジメントにおいては、統一性のある管理をすることが効率的ですが、管理上必要な部分は仕方ないとしても、付加的な部分については、個人の強みを認め、それを活かすことを心がけています。
部下のマネジメントという点では、多様性を活かすことを重視しています。私は社内で初の時短勤務のマネジャーだったため、最初は"異端"である自分を感じていました。しかし、他のマネジャーとは違うことを「申し訳ない」と思うのではなく、"異端"である自分を活かそうと決めたことをきっかけに、部下に対しても多様性を活かすマネジメントをするようになったのです。マネジメントにおいては、統一性のある管理をすることが効率的ですが、管理上必要な部分は仕方ないとしても、付加的な部分については、個人の強みを認め、それを活かすことを心がけています。
その1つとして、「人と人とを比較しない」ということには気を付けていますね。かつては、部下同士を比較して、何かが苦手な部下に対しては「これは○○さんの方が優れているから聞いてきなさい」と言い、自分で聞いて理解してもらう、というマネジメントをしていたこともありました。確かに伝わりやすい側面はあったのですが、安易なやり方だったのではないかと思ったのです。自ら説明することは一人ひとりの部下と向き合う機会なのに、それを省いてしまっていたのではないかと。今は部下ともっと向き合うことを意識し、求めるレベルを率直に伝えています。
マネジメントをしていて実感するのは、女性は鋭い感覚を持っていることが多いということです。数字を見なくても課題の存在を察知して、仮説を立てる。それから数字を見てみると、本当に課題があり、仮説が裏付けられる。その察知する感覚は研ぎ澄まされていると思います。一方で、数字を第一に説明しないという弱点もあるので、理論を立ててロジックで説明する力は必要です。上司に対して、率直に意見を言える傾向も、女性に強く見られます。私自身、子育てをしながら管理職を務めていますが、女性には強みがあってそれを活かしていくことができるということを、周りの人が感じてくれていたらうれしいですね。
記事一覧
- #10「時短勤務の管理職だからこそ見いだした部下と向き合い、多様性を重視するマネジメント」
パーソルキャリア株式会社 川嶋由美子 - #09 「一人ひとりに合わせたマネジメントで安心してチャレンジできる組織へ」
株式会社みずほフィナンシャルグループ 五十嵐伊津子 - #08「誰のために、何のために」を考えることが仕事の始まり 時代の変化に合わせて、これからの商社をつくる人材を育てたい
丸紅株式会社 許斐 理恵 - #07「外資系企業での体験を活かした一人ひとりの主体性を根付かせる取り組み」
野村證券株式会社 東由紀 - #06「いきいきと仕事をするために必要なのは、「自己効力感」」
株式会社アバント 藤井久仁子 - #05「新しい仕事のやり方を切り開く、「格好いい」リーダーでありたい」
GEヘルスケア・ジャパン株式会社 田村咲耶 - #04「前向きに挑戦し続けるために必要なインプット ワーキングマザーとして、完璧は無理でも一歩でも前に進みたい」
株式会社リコー 児玉涼子 - #03「キャリアを広げていく中で見つけた「俯瞰的視点」」
株式会社クレディセゾン 堀内裕子 - #02「「メンバーを尊重して育てる」"母親"のようなマネジメント」
株式会社虎屋 福田昌子