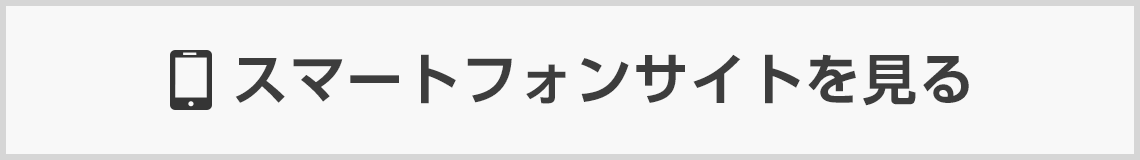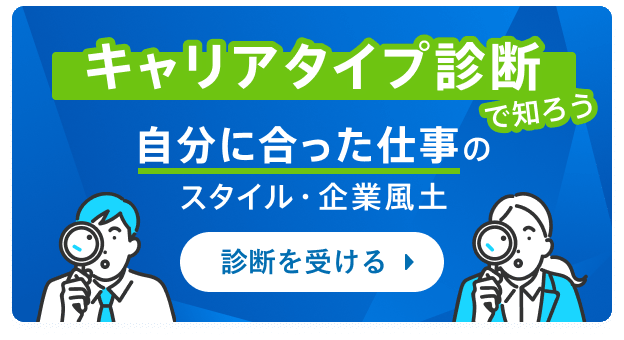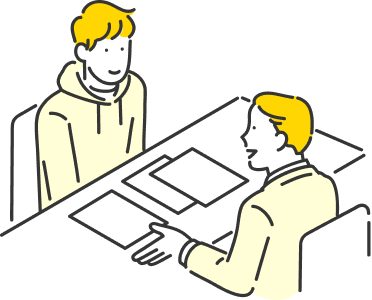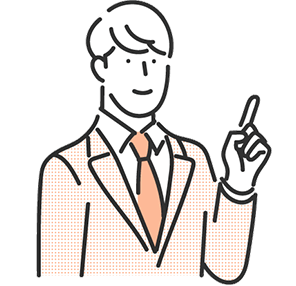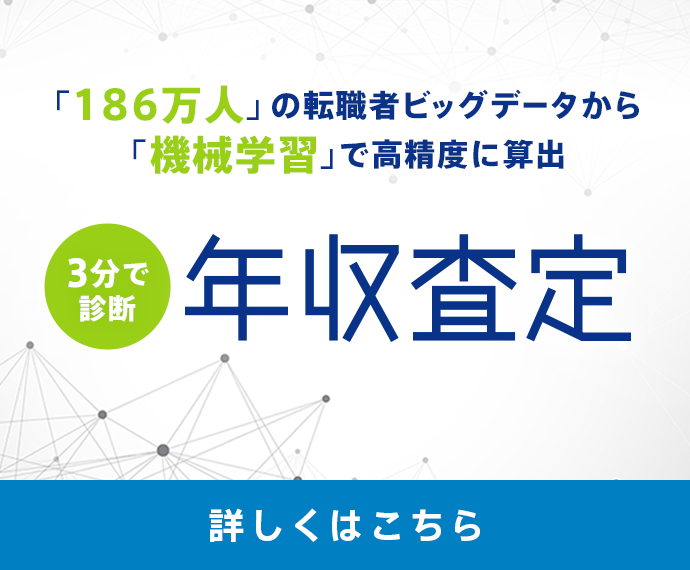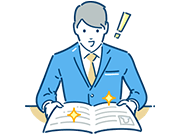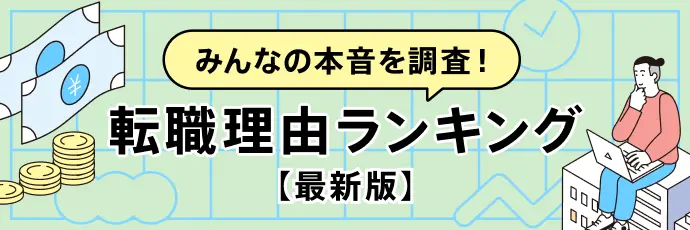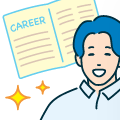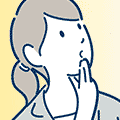公務員を辞めたい…
主な理由や退職の判断をする前に
やることを解説!
監修者:戸村 直樹(とむら・なおき) dodaキャリアアドバイザー
公務員は一般的には安定しているイメージを持たれる職業ですが、中には公務員の仕事が合わず、辞めたいと悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、公務員として働いている人が仕事を辞めたいと感じる主な理由や、辞めようか悩んだときの判断のポイントについて詳しくお伝えします。公務員を辞めたいと思ったときは一度立ち止まって、本記事をご一読ください。
公務員が「仕事を辞めたい」と感じる主な理由は?
公務員が仕事を辞めたいと感じる理由にはどのようなものがあるのでしょうか。
実際に多くの公務員の転職をサポートしているキャリアアドバイザーへの取材内容をもとに、よくある理由を解説します。
一つの業務の専門性を高めることが難しい
公務員は組織内での不正の防止や職員の能力開発、職場の活性化などの観点から、定期的にジョブローテーションが行われます。
一部の職種を除き、基本的にはゼネラリストとしてのキャリアを歩むことになるので、一つの業務の専門性を高めていきたい志向の方は転職の検討につながりやすいでしょう。
前例踏襲の風土があり、変化が少ない環境
公務員は自国や地方自治体を守ることが業務上のミッションです。基本的には前例踏襲の風土が根強く、どうしても保守的にならざるを得ない傾向にあります。
そのため、クリエイティブな仕事や常に新しい挑戦を求める方はやりがいが感じられず、辞めたいという考えに至りやすいでしょう。
特に地方公務員で、役所の窓口などルーティンワークが多い業務を担当している方は、成長実感が得られにくいと悩むケースが多いようです。
年功序列であり成果に応じた評価・給与ではない
公務員の給与は階級によって細かく定められています。また、基本的には年功序列で勤続年数や年齢を加味した昇給が多いため、自分の成果や実力に応じた評価を受け、それに見合った給与を得たいと考える方は転職を意識する傾向にあるでしょう。
労働環境を改善したい
公務員は部署によっては残業が多く、ワーク・ライフ・バランスを重視して辞めたいと思う方もいるでしょう。
例えば、国家公務員は通常の業務に加えて「国会対応」を行うことになります。質問に応じて大臣の答弁の内容を急いで用意する必要があるため、通常業務の進捗にかかわらず、残業せざるを得ないこともあるでしょう。
また、全体的にリモートワークができる部署が少ないため、近年では柔軟な働き方を求めて退職するケースも多いようです。
公務員を辞めるか判断する前にやっておきたいこと
公務員を辞めるべきか悩んでいる場合は、まず一度立ち止まって考えてみることをおすすめします。
今は公務員を辞めたい理由のほうが目についているかもしれませんが、自分の中で気持ちが固まっていないまま退職・転職してしまうと、後悔につながりかねません。
ここでは、公務員を辞めるか判断する前に具体的に考えておきたい・やっておきたいことをご紹介します。
公務員を辞めたい理由の言語化・整理
まずはなぜ公務員を辞めたいのか、その理由を整理することが大切です。
やり方としては、最初に辞めたいと思い至った原因や出来事を洗い出していきます。
次に、その理由はこのまま公務員として働き続けた場合に解決するのか、それとも公務員として働き続ける限り避けられないことなのかを自分なりに整理してみましょう。
辞めたい理由を言語化しておくことで、公務員を辞めるべきかどうかの一つの判断軸になるはずです。
なお、辞めたい理由をより明確化したいときはdodaの「セルフチェックツール」をご活用ください。「仕事・業務内容」「給与・報酬・評価」など6項目の不満度が算出できるので、自分が何に不満を抱えているのか言語化する際のヒントになるでしょう。
「不満を可視化するセルフチェックツール」を使ってみる(無料)
今後のキャリアプランを考える
辞めたい理由が整理できたら、次に今後のキャリアプランを考えてみましょう。
公務員を辞めるにしても今の仕事を続けるにしても、自分のキャリアプランを明確にしておくことは大切です。
自分の理想のキャリアと現在地とのギャップを理解することで「今後どんなスキルを身につけていきたいか」や「どんな環境に身を置きたいか」など、自分が次に取るべき行動がより明確になるでしょう。
このキャリアプランは仕事に限定する必要はありません。趣味やパートナー・家族との時間など、仕事以外で大切にしたいことも踏まえて考えてみてください。
自分に合った仕事や企業風土を知りたいときは、dodaの「キャリアタイプ診断」がおすすめです。キャリアプランの参考に、ぜひ活用してみてください。
キャリアに漠然と悩んでいる方へ
あなたの強みや今持っているスキルが分かる
まずは転職活動をしてみる
意外に思うかもしれませんが、公務員を辞めるかどうか判断するために転職活動を行うのも一つの手段です。「転職」と「転職活動」は別ものです。転職活動をしたからといって、必ず転職しなくてはいけないわけではありません。
実際の求人を見たり面接を受けてみたりすることで、より転職した後のイメージがわきやすくなるでしょう。場合によっては、今の職場のよいところが見えてきて、転職をしない選択肢も生まれるかもしれません。
特に民間企業への転職を視野に入れている場合は、公務員との違いを認識しておくためにも、転職活動を通じて情報収集しておくのがおすすめです。
公務員を辞めたいと思ったら、
dodaに登録して情報収集から始めよう
キャリアアドバイザーに相談する
辞めたい理由やキャリアプランを自分一人で考えるのが難しい場合は、キャリアアドバイザーに相談するのも一つの手段です。
転職すべきか迷っている段階でも問題ありませんので、キャリアアドバイザーに相談して悩みを整理し、キャリアの方向性を考えてみましょう。
「公務員を辞めたい…」と感じたときの選択肢
次に公務員を辞めたいと感じたときの行動として、考えられる選択肢を確認しておきましょう。ここでは5つの選択肢を解説します。
異なる領域の公務員へ転職する
公務員の役割や待遇には満足しているけれど今の仕事内容を変えたい方は、異なる領域の公務員に転職する方法があります。
例えば、教育分野から環境分野、または行政から警察など、異なる領域に移ることで新しい視点やスキルを得られるでしょう。
ただし異なる領域の公務員に転職する際は、公務員試験を再度受け直す必要があります。また、試験日程はあらかじめ決まっているため、実際に転職するまでには時間がかかる点も考慮しましょう。
学校法人や社団法人などの非営利法人へ転職する
民間企業ではなく、非営利法人への転職も選択肢の一つです。
非営利法人には、例えば学校法人(大学職員など)や一般社団法人、公益社団法人などが含まれます。これらは公務員ではありませんが、社会の利益を第一に考えて業務を行う点で、公務員と考え方が似ているといえるでしょう。
ただし類似する点が多い分、公務員を辞めたい理由が本当に改善するかどうかはよく考える必要があります。
民間企業へ転職する
公務員の働き方そのものを変えたい場合は、民間企業に転職するのも一つの選択肢です。民間企業では公務員以上に成果やスピード感を求められることが多く、公務員とは異なる働き方になりますが、その分やりがいも大きく、実績・成果に伴う評価を得やすいでしょう。
また企業によっては副業やリモートワークなど、より柔軟な働き方ができる場合もあります。
一口に民間企業といってもさまざまな業界・職種・文化の企業があります。転職を考える際は「自分のやりたい業務内容や伸ばしたいスキルは何なのか」「自分のこれまでの経験をどう活かすか」をしっかりと自己分析することが重要です。
現職に残る
退職理由を整理した上で、退職しなくても解決できそうな問題であれば、現職に残る選択肢も考えられます。まずは退職理由に挙げている事柄が一時的なもので今後改善される見込みがあるのか、それとも公務員として働く限りずっと続くものなのか考えてみましょう。
例えば、現在の部署の職場環境が合わない場合や、同じ省庁や役所内でほかにチャレンジしたい業務がある場合は、異動希望を出してみるのも一つの方法です。まずは上司や人事担当者に相談し、異動の可能性について確認してみましょう。
退職・休職をする
通常は次の職場が決まっていない状態で退職することはおすすめしていませんが、これ以上続けていくのがどうしてもつらい場合や、残業が多く転職活動に時間を割けない場合は、転職先が決まる前に退職するのも一つの選択肢です。また、体調や精神面での不調がある場合は、無理をせず一度休職してもよいでしょう。
また公務員を退職後、独立して起業することを選択する人もいます。自分のビジネスを立ち上げることで、自由な働き方や自己実現を追求することができるでしょう。ただ独立にはリスクも伴うため、入念な事前準備が重要です。
公務員を辞めて後悔しないために!知っておきたい転職活動のコツ
公務員を辞めて非営利法人や民間企業への転職を目指す場合に、納得のいく転職先を見つけるためのコツを解説します。
転職の目的(転職軸)を明確にする
転職活動を始める際は、「なぜ公務員を辞めたいか(退職理由)」だけでなく「転職することで何を解決したいか(転職軸)」を自分の中で定めておくことが大切です。転職軸があいまいなままでは、選考が通りづらい上、仮に内定を獲得できたとしても入社後に「こんなはずじゃなかった」とギャップを感じるかもしれません。
例えば、公務員を辞めたい理由が「残業時間」や「年収」だったとしても、それが改善できればどの企業でもよいことはないはずです。転職後どのようなキャリアを積みたいかも一緒に考えることで、将来的にもより満足度の高い転職につながるでしょう。
転職先の選択肢は幅広く検討する
非営利法人や民間企業への転職を考える場合、知名度や会社・法人の規模などに意識が向きやすいかもしれませんが、パブリックイメージが良い企業・団体が必ずしも自分にとって良い職場とは限りません。
入社後のミスマッチを防ぐためにも、社名やイメージだけに左右されず、幅広い選択肢の中から転職先を検討したほうが、最終的に満足度が高い転職ができるはずです。求人を探す際は「退職理由が改善するか」「転職の目的がかなうか」の観点で情報収集しましょう。
もし一人で判断するのが難しければ、キャリアアドバイザーに相談してみましょう。自分では思ってもみなかった選択肢を提示してもらえるかもしれません。
\転職するか迷っていてもOK!/
公務員転職に詳しいキャリアアドバイザーが親身にサポートします!
転職先で何が活かせるか明確にしておく
特に公務員から民間企業への転職を検討する際、これまでの経験やスキルはリセットされると考える方も多いかもしれません。しかし、実は公務員で培った経験やスキルは民間企業で活かすことができ、選考の段階でも十分なアピール材料になります。例えば、公務員として培った調整力や業務管理力、遂行力などは公務員以外でも評価されるスキルです。
自分のこれまでの経験を棚卸しし、何が自分の強みか把握しておくことで、強みを活かした企業選びができるでしょう。また企業側も、転職後にどう貢献してもらえるかイメージしやすくなるので、選考の通過率にも影響があるはずです。
より詳しい棚卸し方法を知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
公務員を円満に辞めるために押さえておきたいコツ
転職先が決まったら、公務員を辞めるための手続きに進みましょう。ここでは円満に退職するためのコツを解説します。
退職の意思ははっきりと伝える
辞表を出す前に、まずは上司に口頭で退職の意思を伝えます。退職理由は明確に話すに越したことはありませんが、現職の不満を明け透けに語るのは好ましくありません。
これまでの感謝を伝えつつ、「公務員では実現できないことをかなえるために転職したい」や「家庭の都合でやむを得ず転職したい」など、上司に受け入れてもらいやすい理由を伝えましょう。
また、上司に退職の意思を伝える際は、メールなどではなく直接伝えるほうがより誠意を感じられます。明確な意思表明とていねいなコミュニケーションを心がけましょう。
円満退職に向けた退職の伝え方・切り出し方 | 例文でポイントを解説
引き継ぎ期間には余裕を持って退職日を設定する
転職先への入社日の決定にも関わってきますが、退職日は業務の引き継ぎ期間を十分に取れるスケジュールで設定しましょう。
退職に当たってこれまで行っていた業務を誰かに引き継ぐことになるはずなので、相手が問題なく業務に取りかかれるよう、マニュアルの作成や口頭での連携を行う必要があります。
退職後の質問対応などを避けるためにも、余裕のあるスケジュールできちんと業務を引き継いでから退職できるよう、退職日・入社日を設定しましょう。
キャリアに漠然と悩んでいる方へ
あなたの強みや今持っているスキルが分かる
公務員を辞める前に知っておきたい退職の注意点
ここでは公務員ならではの退職の注意点をご紹介します。事前に把握した上で、必要な対応を行いましょう。
公務員は失業保険が支給されない
公務員は基本的に失業保険を受給できないので、退職から転職までの間に離職期間がある場合は、生活費や転職活動に必要な費用を事前に見積もっておくことが大切です。
また自己都合による退職の場合は、退職金の金額が通常より下がることも知っておく必要があります。事前に経済的な準備をしておき、転職活動を安心して進めましょう。
国家公務員は転職先の届け出が必要
国家公務員には再就職先の透明性を確保するため、国家公務員法により再就職先の届け出が義務付けられています。
国家公務員を辞める前に転職活動を行う場合、再就職の約束をした日から1週間以内に、所定の書類を任命権者に届け出る必要があります。ここでいう「再就職の約束」とは、内定が出た場合を指します。対応が漏れてしまうと懲戒処分の対象になることもあるので、早めに対応しましょう。
このほか、国家公務員の在職中に一定の役職に就いていた方は、再就職先によっては離職後2年間、届け出が必要になります。
再就職先の届出に関する規則の詳細はこちらを参考にしてください。
国家公務員には再就職等規制がある
国家公務員のうち「本省課長補佐級以上」の役職に就いている方には「再就職等規制」が適用され、以下の3つが制限されます。
- 他の職員・元職員の情報提供や再就職依頼の規制
- 在職中の利害関係企業等への求職活動の規制
- 元職員による口利きの規制
このうち、転職活動で特に気をつけたいのは「在職中の利害関係企業等への求職活動の規制」です。
国家公務員で「本省課長補佐級以上」の役職者は自身の業務と利害関係がある企業への転職活動が原則禁止されています。条件にあてはまる方は、規則を確認した上で転職活動を行いましょう。
国家公務員の再就職等規制についてはこちらを参考にご覧ください。
公務員を辞めたいと思ったら、まずその理由を整理しよう
公務員はその仕事柄、前例踏襲や年功序列の文化が強かったり、残業が多かったりと、人によっては辞めたいと思うこともあるでしょう。
「公務員を辞めたい」と感じたら、まずはその理由を整理・言語化しましょう。その結果によって、民間企業に転職すべきか、民間企業の中でもどのような条件の企業を探すべきかなどが見えてきます。
民間企業の就職活動の経験がなく不安な場合は、転職エージェントの利用もおすすめです。dodaエージェントサービスでは、公務員からの転職に精通したキャリアアドバイザーが在籍しています。公務員ならではの転職のコツや注意点を理解しながら転職活動を進められるので、ぜひお気軽にご相談ください。
- 会員登録しておけば、おすすめ求人がメールで届きます!
- 無料で会員登録する
- あなたに向いている働き方や企業風土を知ることから始めよう!
- キャリアタイプ診断を受ける(無料)
この記事を監修したキャリアアドバイザー
【経歴】
2016年株式会社インテリジェンス(現・パーソルキャリア株式会社)に中途入社。約3年、法人営業として採用向けコンサルタントとして従事。その後、キャリアアドバイザーとして販売職・営業職・専門職の方を担当。2023年4月に公務員の方々を専門に担当する組織が発足し、メンバーとして参画。
【メッセージ】
これまで5,000人を超える販売職、営業職、その他専門職、公務員の方々とお会いして転職をサポートしてきました。一人ひとりにそれぞれの思いやかなえたい未来がある中で、これから転職活動に臨むことになると思います。転職活動の良い点、厳しい点も率直にお伝えしますので、後悔のない転職活動を一緒に進めていきましょう。
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1

-
2

-
3

-
4

-
5