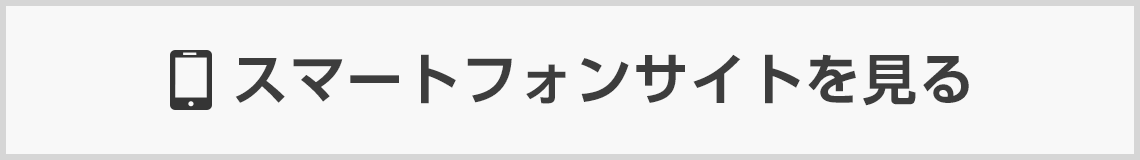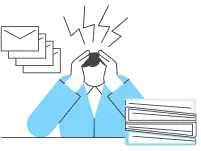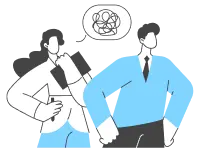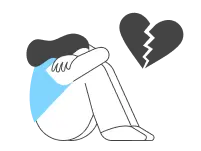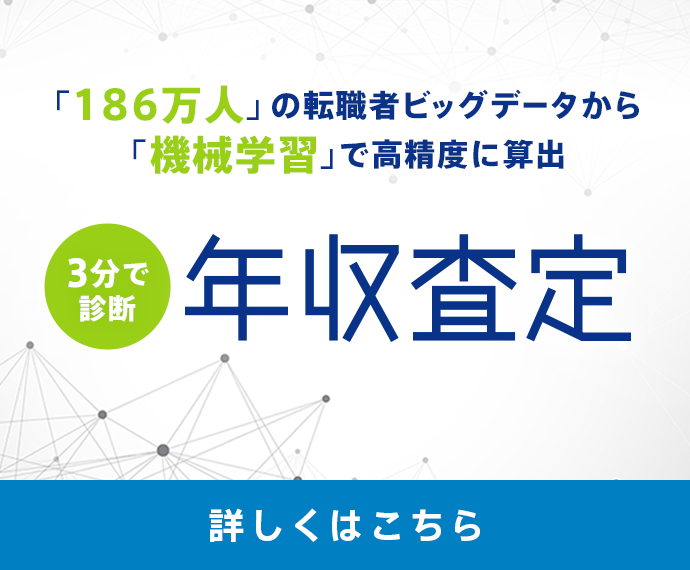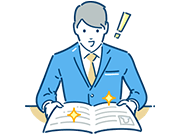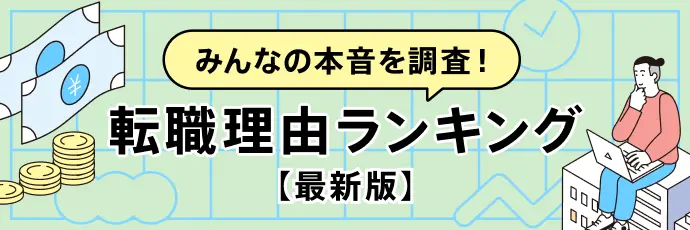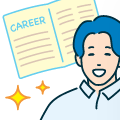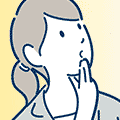仕事がつらい…は甘えじゃない!
原因別に心が軽くなる対処法を
精神科医が解説
本記事では、精神科医・産業医の堤多可弘先生のお話をもとに、「仕事がつらい」ときの要因や、メンタル不調に陥らないためにできること、心が軽くなる対処法を、メンタルヘルスの観点でご紹介します。また、自分一人で抱え込みすぎず、少しずつ前を向くための考え方も解説します。
この記事で分かること
- SNS普及など社会構造の変化の影響もあり、「仕事がつらい」と感じやすい世の中になってきている
- 「仕事がつらい」と感じる主な原因は仕事、人間関係や環境、プライベートの3つ
- つらさに気づいたときは、一人で抱え込まない・自分を責めすぎないことが重要
もくじ
「仕事がつらい」と感じやすい世の中になってきている…?
「仕事がつらい」と感じる方が、年々増えてきているといわれています。実際、精神科医・産業医として多くの社会人の相談に乗っている堤先生によると、最近は「仕事がつらい」という相談が増えている傾向があるということです。
堤先生いわくこうした背景には、働く環境や社会構造の変化が関係しているといいます。
- ・仕事で求められるレベルが高くなっており、プレッシャーを感じやすい
- ・SNSの普及で理想像だけ切り取った内容を目にする機会が増え、自分と比較して自己肯定感が下がりやすい
まず1つ目の背景を詳しく見ていきましょう。相談の多い内容から、仕事は以前と比べてより細分化・高度化・高密度化しているように感じます。
それにより、専門性の高い業務が求められ、しかもその変化スピードも非常に早くなっているのかもしれません。
結果、変化に適応する負荷が高まり、常に学び続けなければならない状態が続くことで、心身の余裕を失いやすくなっているといえます。
また、2つ目に記載している「SNSの普及」も人々の仕事に対する考え方に影響を及ぼしています。
SNS上でキラキラした成功体験を多く目にできる一方で、その裏にある失敗や葛藤、過程は見えづらく、最初からうまくいっている人ばかりのように感じてしまう方も多いのではないでしょうか。
その結果、自分と他人のギャップを感じやすく、自分の頑張りを評価する基準が分からなくなり、迷いや劣等感につながってしまうケースも多く見られます。
こうした背景から、「仕事がつらい」と感じる方が増えているかもしれません。
あなたに向いている仕事スタイルや
性格や気質、スキルが分かる
「仕事がつらい」と感じやすい人の特徴
仕事がつらいと感じやすい人には、いくつかの性格や考え方のパターンがあります。
代表的なのが「完璧主義」や「~すべき」という思考の強い人。このような人は、自分にも周りの人にも求めるレベルが高くなりやすい傾向があり、周りの人に頼らず仕事を抱え込みやすく、他者にも厳しくなりがちです。結果的にオーバーワークや人間関係の疲れにつながってしまいやすいでしょう。
また、「周りの人との比較」や「周りの人からの評価」を重視するタイプも要注意です。周りの人を意識するあまり、自分にとって本当に必要な行動が取れなくなったり、相談や質問ができずに一人で抱え込んだりしてしまう傾向があります。特に現代はSNSなど、手軽に他者と自分を比較できる機会が増え、時にはキラキラした姿ばかりが目に入るため、余計に焦りを感じやすい環境といえるでしょう。
「仕事がつらい」とき…メンタル不調に陥らないためには
仕事がつらいとき、自分では気づかないうちに精神的な負荷がかかり、そのまま放置しておくとメンタル不調に陥る可能性も考えられます。そうならないためにも、心の負荷がどの程度かかっているかを把握し、必要以上精神的な負荷を増やさないことが大切です。
メンタル不調の初期サインとは
まずはこれから紹介するメンタル不調の初期サインが現れていないか確認してみましょう。
<メンタル不調の4つのサイン>
| 食べる |
|
|---|---|
| 寝る |
|
| 遊ぶ |
|
| 考える |
|
メンタル不調の初期サインは「食べる・寝る・遊ぶ・考える」のどこかに異常として多く現れます。例えば食欲や睡眠の変化、趣味を楽しめない、思考のまとまりにくさなどは、見逃せない心と体のサインです。
「食べる・寝る・遊ぶ・考える」それぞれのサインとしてよくある例は上記のとおりです。当てはまる不調が出ている方は自分の状態をよく観察してみましょう。
特に注意したいのが、「遊んでいるつもり」でスマホに没頭している状態です。
これは気晴らしに見えて、流れ作業のように動いてしまっている行動なので、より疲れる原因になってしまったり、人によってはスマホ依存に陥ってしまったりするケースもあります。
また、「食べる・寝る・遊ぶ・考える」以外にも、自分だけの「不調のサイン」に気づくことも大切です。
例えば過去を振り返ってみて「口内炎ができる」「カフェインの摂取量が増える」「辛い物や甘い物を食べる量が増える」など、体調の悪化や精神的な不調が起こる直前に共通する行動や事象はなかったでしょうか。
自分なりの不調のサインを知っておくことで、早めのセルフケアにつながり、不調の深刻化を防ぐことができるでしょう。
本格的なメンタル不調に陥ってしまうと回復には時間がかかります。「食べる・寝る・遊ぶ・考える」のサインは本格的な不調に一歩近づいているサインです。次の節では、不調を未然に防ぐために押さえておきたいポイントをご紹介します。
不調を未然に防ぐには?日常で意識してほしいポイント
本格的な不調に陥る前に、自分のコンディションを日常的に「青信号」「黄信号」の段階で把握しておくことが重要です。
おすすめは、睡眠時間や気分をモニタリングする習慣を持つことです。例えば手帳の隅に1日10点満点で体調を記録するだけでも、変化に気づきやすくなります。
また、気分転換を習慣化するのも効果的です。リフレッシュになるけれど手間がかかること(例:週1回のジム、ヨガ、カフェ巡りなど)を続けられている間は「青信号」というように、心の余裕を測る指標になります。
逆に、スマホで時間をつぶすことや飲酒など依存につながる行動は、調子が悪いときほど増えやすいので注意が必要です。また、仕事ではメールボックスのたまり具合や事務作業を面倒に感じるかどうかなども、日々の小さな「黄信号」サインとして活用できるでしょう。

![]() 堤先生の一言アドバイス
堤先生の一言アドバイス
不調のサインを感じたときは、気分転換を習慣化することで、青信号に戻すこともできます。実際に私が習慣化している気分転換は、ジムに週1回行くことと、毎日10分でも新聞に目を通すことです。
「仕事がつらい」と感じる原因
「仕事がつらい」と感じる背景には、主に以下の3つのストレス要因があります。
実際にはそれぞれが複雑に絡み合い、あなたが今「仕事がつらい」と感じている原因になっていると考えられます。順に詳しく見ていきましょう。
仕事による原因
仕事そのものがつらいと感じる背景には、主に「業務量の多さ」と「業務内容の質(得意、不得意など)」、「業務での裁量権」があります。
例えば、長時間労働や終わらないタスクに追われている場合や、やりがいを感じにくい仕事を続けている場合、また、業務内容は嫌いではないが裁量権が少ない場合などが該当します。
また、「業務量の多さ」や「業務内容の質(得意、不得意など)」に目が行きがちですが、ここで重要なのが「裁量権」の存在です。同じ業務量・内容でも、自分で決められる範囲が広ければその分ストレス軽減につながりますが、裁量権がない中で業務の量が増えていくと、疲弊感や無力感が強まり、つらさに拍車がかかります。
よくあるケース
- 担当業務が多すぎて処理しきれない
- プロジェクトが複数並行し、優先順位が不明確
- テレワークで仕事とプライベートの境目があいまいになり、常に仕事をしてしまう
- 業務の成果が見えづらく達成感がない
- 業務内容が自身のスキルや成長につながっていないと感じる
- 業務に裁量権がなく、指示待ちばかりでやりがいを感じられない
あなたに向いている仕事スタイルや
性格や気質、スキルが分かる
人間関係や就業環境による原因
職場の人間関係や就業環境の変化も、仕事がつらいと感じる大きな要因です。
職場内でのコミュニケーションの希薄さ、上司や同僚との関係性にもやもやすることが多いなどが該当します。
また、残業が急に増えた、突然のテレワーク廃止で働き方が変わったなど、就業環境の変化もストレスにつながります。生活のリズムが崩れたり、オンオフの切り替えが難しくなったりすることで、メンタルへの負荷が知らず知らずのうちに蓄積されてしまうのです。
よくあるケース
- 人間関係が良くない
- 職場に相談できる相手がおらず孤立している
- 仕事に対する評価が不透明で納得感が持てない
- テレワークの比率が変化した
- 合併や経営層の変化により会社の人事制度や文化が変わった

あなたに向いている企業風土や
性格や気質、スキルが分かる
プライベート(家庭・恋愛など)による原因
仕事とは直接関係がないように見えて、実は大きな影響を与えるのがプライベートの変化です。家庭内の問題、恋愛関係の悩み、育児・介護の負担など、私生活の不安定さは仕事への集中力や意欲にも影響します。
例えば、家庭が穏やかでプライベートが安定していれば、多少仕事がハードでもプライベートのために乗り越えられることがあります。しかし、介護や育児で強いストレスを感じていたり、パートナーとの関係悪化などがあったりすると、心に余裕がなくなり、通常なら対応できる出来事も過剰にストレスを感じてしまう恐れがあります。
よくあるケース
- パートナーとけんかが続いており、悩んでいる
- 親の介護と仕事の両立がうまくできていない
- 子供の寝かしつけで睡眠時間が取れていない
- 不妊治療中など周囲に話しづらい状況を抱えている
【原因別】仕事がつらい方へ、心が軽くなる対処法
仕事がつらいと感じたときの対処法は、原因によって異なります。この章では、前述した3つの原因に対し、それぞれの対処法をご紹介します。
 仕事による原因への対処法
仕事による原因への対処法
業務量の多さや、自分に合わない仕事の内容など、日々の「仕事そのもの」がストレス源になっている場合は、「すべてに関して完璧を目指す思考を緩める」ことから始めましょう。
まずは完璧を目指す・成長しなければならないという前提を見直し、「完璧でない・成長がない中でも、熱中できているか」「小さな変化に気づけているか」といった視点に目を向けたり、求められている仕事や成果の水準を会社と再度すり合わせてみることも有効です。
また、業務の合間に短時間でもよいのでストレッチや深呼吸など、自分のための時間を意識的に取ってみるのもおすすめです。さらに、週に一度でもよいので気分転換を習慣化できると、心のバランスを保ちやすくなるでしょう。
仕事に意味ややりがいを感じづらいときは、ジョブ・クラフティングを試してみるのも効果的です。ジョブ・クラフティングとは、仕事内容や人との関わり方、仕事の意義に対して自分なりに意味付けを行ったりやり方を変えたりすることで、仕事を前向きに捉え直すアプローチのことです。
例えばカフェのスタッフが、「家でくつろぐような時間をお客さまに提供したい」と意義を持って働くと、マグカップでのドリンク提供の提案や「ゆっくりしていってください」と声掛けを行うなど、一つひとつの対応に自分なりの工夫を加えることができます。
このように仕事の意義や目的を自分なりに捉え直してやりがいが出るように工夫することがジョブ・クラフティングです。
仕事内容や人との関わり方に自分の思いを少しだけ加えることで、「やらされている」から「自分で選択している」という感覚になり、モチベーションを取り戻すきっかけになります。
 人間関係や就業環境よる原因への対処法
人間関係や就業環境よる原因への対処法
職場の人間関係や急激な働き方の変化がストレスになっている場合は、無理にすべてを改善しようとせず、「距離を取る」「割り切る」といった視点を持つことも大切です。
相手の価値観や考え方を変えることはできないため、こうした視点を持つことで、気持ちが楽になるケースも多いでしょう。「自分が相手に過度な期待をしていないか」と振り返ってみるのも効果的です。
ただし、パワハラやいじめなど深刻なケースでは、社内の相談窓口や厚生労働省の総合労働相談コーナーなど外部の機関に相談することが重要です。
また、給与や評価制度、働き方など、一見、自分ではどうしようもない外的な要因に不満を抱えている場合は、それが「本当に変えられないものなのか」考え直してみましょう。
要因を細分化し、小さいところから手を打っていくことで、意外と着手できる改善点が見つかることもあります。例えば、「残業が毎日1時間以上あることと、リモートワークできないことが不満」な場合、残業に関しては「業務効率化など自分で変えられることがありそう」、リモートワークに関しては「会社の制度の問題なので個人で変えられなそう」など、自分で変えられる・変えられないことをまずは整理してみましょう。

あなたに向いている企業風土や
性格や気質、スキルが分かる
 プライベート(家庭・恋愛など)による原因への対処法
プライベート(家庭・恋愛など)による原因への対処法
家庭や恋愛、健康などプライベートの状況は、仕事への集中力や心の余裕に影響を及ぼします。
介護や育児、パートナーとの関係性など、目に見えにくい負担を抱えると、プライベートに問題がなく穏やかだった時期に比べて、気持ちに余裕がなくなることが多くなります。結果的に、仕事や会社との向き合い方、捉え方も悪い方向に向かってしまう可能性があります。
こうしたときに有効なのが、自分のキャパシティーを基準に行動を見直すことです。「すべてをやりきる」のではなく、「プライベートで自分にとって本当に大切なこと」から優先順位を付けて取り組むようにします。
その際、やらなければならないこと(To Do)、できればやりたいこと(To Wish)、思い切ってやらないと決めること(Not To Do)という3つの区分に分けて考えてみると、自分の中の整理がしやすくなります。
例えば、「週に1日はお弁当を買って自炊しない」など、あえて「やらないこと」を決めることが心の余白をつくり、自分のリズムを整える手助けになることもあります。
 すべての原因に通ずる対処法
すべての原因に通ずる対処法
どの原因にも共通することとして、「一人で抱え込まない、無理に我慢せず自分の心を守る視点」を忘れないことが大切です。
まずは信頼できる人に悩みを話してみることで、感情が整理されたり、思わぬヒントが得られたりすることもあります。「自分だけがこんなに悩んでいる」と感じやすいときこそ、人に話してみることは力になるでしょう。
また、「白黒つける思考」や「完璧主義」に陥っていないか、定期的に立ち止まって確認してみましょう。我慢や気合で乗り越えようとするのではなく、「できること」と「できないこと」を分けて考える柔軟さを持てると自分の心を守ることにつながります。
以下の表は、自分にとって「大事なこと」「できること」かをもとに優先度を付ける方法を整理したものです。こちらの表を参考に、「大事ではないこと&できること」は放置し、「大事なこと」「できること」に集中しましょう。
<大事なこと×できることに集中する>
|
できないこと |
できること |
|
|---|---|---|
| 大事なこと |
できることに 分解する |
ここに集中 |
|
大事では ないこと |
放置 |

![]() 堤先生の一言アドバイス
堤先生の一言アドバイス
人間はつらいのに頑張れる唯一の動物です。一方で、すべての動物の中で、唯一我慢をしすぎてしまう生き物といえます。
働くチカラは大事ですが、働き続けるチカラはもっと大切。我慢をして常につらいまま走っていては力を十分に発揮できず、働き続けられないリスクも。この判断ができるのも人間ならではなので、自分からのサインに注目しながら、それぞれのペースを見つけていきましょう。
各原因を自分の中でどう受け止めているか?も大切
仕事がつらいと感じる原因は、先ほどお伝えした3つの要素(仕事・人間関係や就業環境・プライベート)に分類されます。
しかし、それぞれのストレス要因に直面していても、それをあなたがどう受け止めるかによって、感じるストレスの強さやストレスから回復する早さは大きく異なります。
つまり、「何が起こったか」と同じくらい、「それをどう捉えたか」が心の負荷を左右するのです。例えば、「自分がもっと頑張るべき」「完璧にやるべき」といった「ベキ思考」が強いと、同じ出来事でも自分をより強く追い込んでしまうことがあります。
このような内面的な受け止め方や回復力に関わる力を「レジリエンス」と呼びます。レジリエンスとは、困難やストレスに直面したときに、心のダメージから立ち直る力、つまり精神的な回復力のことです。レジリエンスが高いと、多少のストレスでもしなやかに対応でき、必要以上に引きずらずに済むといわれています。
ストレスの原因を整理することはもちろん重要ですが、それと同時に「自分はどんな考え方のクセを持っているか」「ストレスをどのように受け止めているか」に目を向けることも、心を守る上で欠かせない視点です。
仕事がつらいと感じているときのNG行動とその対処法
仕事がつらいと感じているとき、人は心の余裕を失い、視野が狭くなってしまいがちです。ここでは、ストレスが強まったときに陥りがちなNG行動と、その背景にある心理状態、そして少しでも心を軽くするための具体的な対処法を解説します。
 一人で抱え込んでしまう
一人で抱え込んでしまう
仕事がつらいと感じているときは、「人に頼る」という選択肢すら思い浮かばなくなることがあります。心が疲弊し、視野が狭くなってしまうことで、「迷惑をかけたくない」「相談できる人なんていない」と思い込み、すべてを自分一人で処理しようとしてしまうのです。
しかし、こうした孤独な状態が続くと、エネルギーは徐々にすり減り、心身の不調を招きやすくなります。実際に不調を経験した人の多くが、「もっと早く誰かに頼ればよかった」と振り返っていると、堤先生は言っています。
対策としては、あらかじめ「相談できる人」と「相談できる内容」を書き出してリストにしておくのがおすすめです。意外にも、話せる相手は身近にたくさんいるものです。例えば、友達、家族、SNSのグループチャットや職場の同期、かつての同僚など、つながりを活かせる場所はきっとあります。
 自分を責めすぎる
自分を責めすぎる
メンタルが落ち込んでいるとき、人はつい矢印を自分に向けがちです。「自分の努力が足りないのでは」「自分なんて役に立っていない」といった思いが頭を占め、冷静な状況の判断ができなくなります。これは自責というよりも、自己否定的な思考に近く、自己肯定感をさらに低下させてしまいます。
こうした状態になると、回復するエネルギーも奪われてしまいます。「反省」ではなく「否定」に近い状態のままでは、回復どころか、より深く落ち込んでしまう可能性があるでしょう。大切なのは、「自責」ではなく「自分にできることを振り返る」という視点を持つことです。
もし今の自分が自己否定的になっていると感じたら、それはエネルギーが不足しているサイン。まずは心身の負荷を減らすことを優先しましょう。
 衝動的に現職を辞めてしまう
衝動的に現職を辞めてしまう
「もう全部投げ出したい」「今すぐここから逃げ出したい」といった気持ちが強まっているときに転職や退職を決断するのは、あまりおすすめできません。そのような状態では、冷静な判断ができなくなっていることが多く、転職や退職が「出口」ではなく「逃げ場」になってしまうリスクがあるからです。
転職を行うことで、仕事内容や人間関係、就業環境など置かれている状況すべてがリセットされる可能性もあります。戦略的に行えば良い方向に進むこともありますが、衝動的な決断ではうまくいかないこともあります。まずは、小さくても現職で改善できることがないかを模索してみるのも一つの手です。
冷静に今置かれている状況を分析した結果として「全体を変えたほうがいい」と判断できているなら、それは前向きな転職といえます。今の気持ちが「投げ出したい」なのか「前向きな戦略」なのか、一度立ち止まって見極めてみることが大切です。
 すべて他責にしてしまう
すべて他責にしてしまう
つらい状況に置かれると、人は本能的に自分を守るため、責任の所在を外に向けてしまうこともあります。「上司のせいだ」「会社の制度が悪い」など、環境要因に怒りを向けてしまうこともあるかもしれませんが、それが長く続くと、かえって自分自身を苦しめてしまうこともあるでしょう。
他人を変えることは簡単ではありません。それにもかかわらず「相手に変わってほしい」という願いにエネルギーを使い続けてしまうと、解決から遠ざかり、さらにストレスが増してしまいます。
他責的な思考に気づいたら、「今、自分にできることは何だろう?」という視点に切り替えることが大切です。困っていることを書き出し、自分で変えられる部分を整理してみましょう。その上で、「自分にできて、かつ大切なこと」だけに集中することが、負のループから抜け出すための第一歩になります。

![]() 堤先生の一言アドバイス
堤先生の一言アドバイス
一見キラキラと楽しく働いている人でも苦しい時期はあります。「仕事がつらい」という感情は誰もが感じるものですし、成長痛みたいなものと考えましょう。
つらいと感じたときは今回ご紹介した方法を試してほしいのですが、それさえもつらい時はまず相談してみるのがよいと思います。相談することで悩みが言語化されてフォーカスされますし、いろいろな解決策が出てきますよ。
まとめ
仕事がつらいと感じる背景には、業務量や人間関係、環境変化、プライベートなど多様な要因があります。重要なのは、それらをどう受け止め、どう対処するか。レジリエンス(心の回復力)を高める視点を持ちながら、少しずつ自分の心と向き合うことが大切です。
原因別の対処法や考え方の整理を通じて、無理なく前に進むヒントを見つけましょう。
自分のつらさの原因を分析した上で、つらさの「出口」として転職が視野に入ってきた場合は、エージェントサービスへの相談がおすすめ。キャリアアドバイザーに相談することで、一人では狭くなってしまいがちな視野を広げ、あなたの考え方を一緒に整理しながら今後のキャリアの進み方に関してのアドバイスも行っています。お気軽にご相談ください。
この記事の監修

精神科医/産業医 弘前大学医学部卒業後、東京女子医科大学精神科で助教、非常勤講師、メンタルクリニックの副院長を歴任。首都圏を中心に企業や行政機関の産業医やアドバイザーを10カ所以上担当。ブログや著作、研修などを通じて、メンタルヘルスや健康経営、産業保健の情報発信も行っている。共著に『企業は、メンタルヘルスとどう向き合うか―経営戦略としての産業医」(祥伝社新書)がある。
「仕事つらい」に関する記事
-

- 仕事に行きたくない、仕事がつらい…原因を把握して無理せずに乗り切る方法
- 仕事に行きたくないという悩みを一人で解決するのは大変です。原因や対処法を紹介します。
-

- 職場の人間関係がストレス…気にしない方法や転職も視野に入れた解消方法とは
- 上司や同僚との関係で悩んで転職する人は多いもの。転職活動を成功させるには?
-

- 仕事にやりがいがない…原因と自分にとってのやりがいを見いだす方法
- 仕事にやりがいを求めている人は多いです。やりがいのある仕事に就くためのコツを紹介します。
-

- 仕事を辞めたい…!言い出せない・行動できない理由、転職活動のポイント
- 働いていれば「仕事を辞めたい」と1度は思うでしょう。悩みを解決し次につなげる方法を解説します。