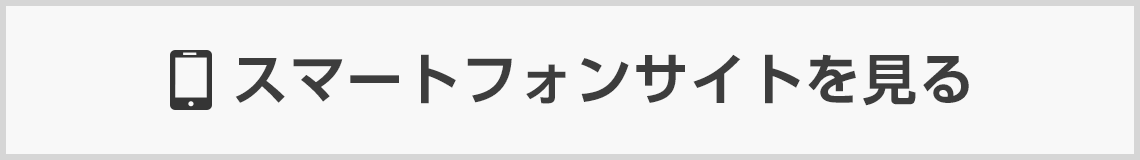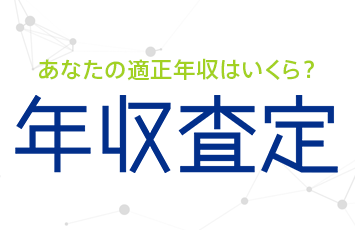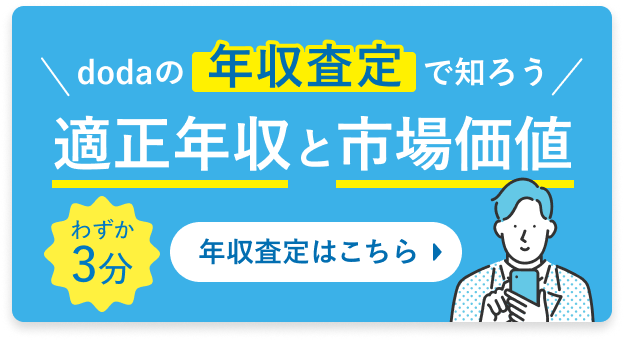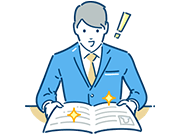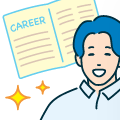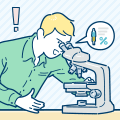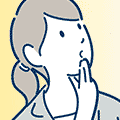失業手当(失業保険)とは?もらえる条件や期間、手続き方法を解説【社労士監修】
監修者:社会保険労務士 北 光太郎(きた・こうたろう)氏(きた社労士事務所 代表)
退職後に次の仕事が見つかるまでの間、失業手当(失業保険)を受給したいという人は多いのではないでしょうか? 失業手当(失業保険)は、退職後の生活を守るために重要な手当です。
ただし、給付を受けるには一定の条件を満たした上で、手続きを行う必要があるため注意が必要です。以下で受給条件・受給期間・受給金額などについて、社労士監修のもと詳しく解説するので、チェックしておきましょう。なお、本記事は2025年4月1日以降の雇用保険制度の改正に対応しています。
- 押さえておきたい失業手当(失業保険)のポイント
-
-
受給条件:失業手当(失業保険)の受給には、次の3つの条件をすべて満たしている必要があります。
- 条件 1|失業状態であること
- 条件 2|ハローワークで求職の申し込みを行い転職活動していること
- 条件 3|雇用保険の被保険者期間が一定期間以上あること
-
受給期間:失業手当(失業保険)を受け取れる期間は、多くの場合3〜4カ月程度です。また初回の支給日は、離職理由が会社都合の場合で申請から約1カ月、自己都合の場合で申請から2カ月程度かかります。
-
受給金額:失業手当(失業保険)の金額はおおよそ離職前の給与の50〜80%で、離職前の給与水準が低かった方ほど給付率が高く設定されています。
-
1. 失業手当(失業保険)とは
失業手当(失業保険)とは、離職者が失業中の生活を心配することなく、新しい仕事を探し、1日でも早く再就職できるように支援するために支給される手当です。
失業手当(失業保険)を受給するためには一定の条件を満たす必要があります。また、給付は「任意」となるため、受給を希望する場合は離職者が自ら申請する必要があります。
なお「失業手当」の正式名称は「雇用保険の失業等給付の基本手当」ですが、本記事では、「失業手当(失業保険)」と表記します。
2. 失業手当(失業保険)がもらえる条件
失業手当(失業保険)を受給するには、下記3つの条件をすべて満たす必要があります。以下で詳しく解説するので、ひとつずつ見ていきましょう。
- 条件 1|失業状態であること
- 条件 2|ハローワークで求職の申し込みを行い転職活動していること
- 条件 3|雇用保険の被保険者期間が一定期間以上あること
条件 1|失業状態であること
「失業状態」とは、就職しようとする意思やいつでも就職できる能力があり、求職の申し込みを行っているにもかかわらず、本人の努力やハローワークの支援があっても職業に就けない状態を指します。
したがって雇用保険の被保険者であっても、以下のようなケースは失業状態とは認められず、失業手当(失業保険)は受け取れません。
- 家業に専念することになった/家業や家事の手伝いをしている場合
- 学業に専念することになった場合
- すでに次の就職先が決まっており、転職活動をする予定がない場合
- 自営業を始めた(準備も含む)場合
- 会社や団体などの役員に就任した(予定や名義だけの場合も含む)場合※
※活動や報酬がない場合は、現住所がある市区町村を管轄するハローワークに要確認
ただし以下の場合は、ハローワークに失業手当(失業保険)の受給期間延長手続きを行えば、働ける環境が整ったあとで給付を受け取れます。
- 定年退職して、しばらく働かない場合
- 病気・けが・妊娠・出産・育児などで、すぐに働けない場合※
- 介護などですぐに働けない場合
※ドクターストップがかかっていなければ、転職活動をしながら失業手当(失業保険)を受け取ることも可能です
条件 2|ハローワークで求職の申し込みを行い転職活動していること
失業手当(失業保険)の受給を希望する場合、ハローワークで渡される「求職申込書」に氏名・住所・職歴などの必要事項を記入して、求職の申し込みを行う必要があります。求職の申し込みは最初に行うべき手続きでもあるため、受給を決めたらハローワークに求職申込書を受け取りに行きましょう。
求職の申し込みを完了させると、ハローワークから「ハローワーク受付票」が交付されます。その後、ハローワークで職業相談や求職活動を行う場合は、職員が求職情報を確認するため「ハローワーク受付票」を持参しましょう。
ハローワークに行く前にオンラインで仮登録すると手続きがスムーズに!
ハローワークに行く前に自宅のパソコンやスマートフォンからオンラインで求職申込書の情報を入力し、仮登録(「求職者マイページ」の開設)をすることができます。仮登録することでハローワークに行ってから情報を記入しなくて済むため、手続きをスムーズに進められるでしょう。
さらにオンラインで仮登録した人はマイページから「ハローワーク受付票」を表示させることも可能です。失業手当(失業保険)の受給手続きを行う際はハローワークに行く前にオンラインで仮登録を行うことも検討してみましょう。
自分の年収って適正?と思ったら...
あなたの適正年収を診断してみませんか?
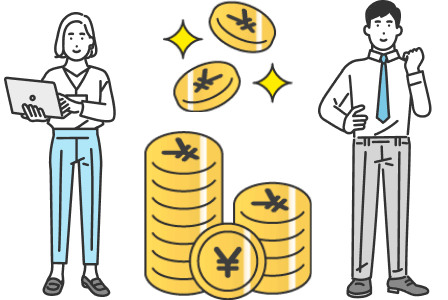
条件 3|雇用保険の被保険者期間が一定期間以上あること
自己都合により失業手当(失業保険)を受給する場合は、雇用保険の被保険者期間が過去2年間で通算12カ月以上ある必要があります。被保険者期間とは雇用保険に加入していた期間のことです。
ただし、必要な被保険者期間は離職理由によって変わるため、以下の表から自身に当てはまるものをご確認ください。
| 離職理由 | 受給資格 | 離職例 | 必要な被保険者期間 |
|---|---|---|---|
| 自己都合 | 一般受給資格者 | キャリアアップ、職場への不満解消など自己都合での退職、 懲戒解雇(違反行為など自己理由に帰するもの)、 定年退職などで離職した人。 |
退職日以前の2年間に 12カ月以上 |
| 特定理由離職者 | 契約更新を希望したのに更新されずに期間満了となった人や、 病気やけが・出産・配偶者の転勤などの やむを得ない理由で失業した人。 |
退職日以前の1年間に 6カ月以上 |
|
| 会社都合 | 特定受給資格者 | 会社の倒産や解雇などの理由により、 再就職の準備をする時間的な余裕がなく、 離職を余儀なくされた人。 |
解雇されたのに自己都合退職にしてほしいと言われた場合や、自己都合を会社都合にできる場合については、よくある質問で解説しているので、チェックしてみましょう。
特定受給資格者と特定理由離職者の違いは以下の記事も参考にしてください。
3. 失業手当(失業保険)をもらえる期間は?
失業手当(失業保険)は申請してすぐに受け取れるわけではありません。会社都合で離職した場合は約1カ月、自己都合での離職の場合は、2カ月程度かかります。また、失業手当(失業保険)を受け取れる期間は多くの場合3〜4カ月程度のため、転職活動は計画的に行う必要があります。
受給期間や受給開始の時期は、離職理由によって異なります。各ケースを見ていきましょう。
自己都合(一般受給資格者)・やむを得ない理由での自己都合(特定理由離職者)の場合
雇用保険の被保険者期間に応じて、支給される期間は90日~150日までと変わります。
| 雇用保険の被保険者期間 | 所定給付日数 |
|---|---|
| 1年未満 | 90日 |
| 1年以上5年未満 | |
| 5年以上10年未満 | |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
また、自己都合(一般受給資格者)の場合、失業手当(失業保険)の受給までに、待期期間と給付制限期間が設けられています。これにより、初めての受給は手続きしてから2カ月後になることは留意しておきましょう。
待期期間は受給資格問わず、離職票の提出と求職の申し込みを行った日から通算して7日間と決まっています。
給付制限期間は、自己都合(一般受給資格者)のみに設けられている期間です。通常は1カ月ですが、過去5年間で2回以上自己都合による離職をしている場合は、3回目の離職では給付制限期間が3カ月になります 。
なお、やむを得ない理由で自己都合(特定理由離職者)の場合は給付制限期間が設けられず、待期期間のみとなります。
会社都合(特定受給資格者)・契約更新を希望したが更新されずに期間満了(特定理由離職者)の場合
受給期間は「雇用保険の被保険者期間」と「離職時の年齢」によって変化します。
ただし、雇用保険の被保険者期間が1年未満であれば、受給期間は90日間で一定です。被保険者期間が1年以上になると、年齢が上がるにつれて受給できる期間も長くなります。ハローワークで求職の申し込みを行ったあと、7日間の待期期間満了後から給付が始まり、初回の支給日は約1カ月後となります。
なお、特定受給資格者と特定理由離職者の違いは以下の記事も参考にしてください
特定受給資格者とは?特定理由離職者との違いや給付日数を解説【社労士監修】
| 雇用保険の被保険者期間 | 離職時の年齢 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ~29歳 | 30歳~34歳 | 35歳~44歳 | 45歳~59歳 | 60歳~64歳 | |
| 1年未満 | 90日 | ||||
| 1年以上5年未満 | 90日 | 120日 | 150日 | 180日 | 150日 |
| 5年以上10年未満 | 120日 | 180日 | 180日 | 240日 | 180日 |
| 10年以上20年未満 | 180日 | 210日 | 240日 | 270日 | 210日 |
| 20年以上 | ― | 240日 | 270日 | 330日 | 240日 |
- 退職しようかな…と思ったらまずは会員登録して情報を集めよう!
- 会員登録する(無料)
4. 失業手当(失業保険)はいくらもらえる?
失業手当(失業保険)として受け取れる金額は、年齢や退職前の賃金によって変わります。以下で、実際の算出方法について詳しく解説します。
失業手当(失業保険)の金額計算方法
※厚生労働省やハローワークなどの資料とも照合しやすいように、この記事では正式名称である「基本手当」の表記で記載しています。
失業手当(失業保険)で受け取れる額は、「給付日数×基本手当日額」で決まります。受給額は離職前の賃金の、5~8割程度になることが一般的です。以下のステップで計算していくと失業手当(失業保険)の算出ができます。
- Step1|
賃金日額の計算方法:退職前6カ月の賃金合計÷180 - Step2|
基本手当日額の計算方法:賃金日額×給付率 - Step3|
基本手当総額の計算方法:基本手当日額×給付日数
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。原則、退職前6カ月間の賃金(ボーナスを除く)の総額を180で割った「賃金日額」に、およそ50~80%の給付率を掛けた金額です。給付率は離職時の年齢と退職前の賃金によって異なり、金額が低い方ほど給付率は高くなります。
給付率は、離職時の年齢と退職前の賃金によって変わります。2024年8月更新時点の給付率は以下の表のとおりです。
| 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
|---|---|---|
| 離職時の年齢が29歳以下 | ||
| 2,869 円以上 5,200 円未満 | 80% | 2,295 円~4,159 円 |
| 5,200 円以上 12,790 円以下 | 80%~50% | 4,160 円~6,395 円 |
| 12,790 円超 14,130 円以下 | 50% | 6,395 円~7,065 円 |
| 14,130 円(上限額)超 | ― | 7,065 円(上限額) |
| 離職時の年齢が30~44歳 | ||
| 2,869 円以上 5,200 円未満 | 80% | 2,295 円~4,159 円 |
| 5,200 円以上 12,790 円以下 | 80%~50% | 4,160 円~6,395 円 |
| 12,790 円超 15,690 円以下 | 50% | 6,395 円~7,845 円 |
| 15,690 円(上限額)超 | ― | 7,845 円(上限額) |
| 離職時の年齢が45~59歳 | ||
| 2,869 円以上 5,200 円未満 | 80% | 2,295 円~4,159 円 |
| 5,200 円以上 12,790 円以下 | 80%~50% | 4,160 円~6,395 円 |
| 12,790 円超 17,270 円以下 | 50% | 6,395 円~8,635 円 |
| 17,270 円(上限額)超 | ― | 8,635 円(上限額) |
| 離職時の年齢が60~64歳 | ||
| 2,869 円以上 5,200 円未満 | 80% | 2,295 円~4,159 円 |
| 5,200 円以上 11,490 円以下 | 80%~45% | 4,160 円~5,170 円 |
| 11,490 円超 16,490 円以下 | 45% | 5,170 円~7,420 円 |
| 16,490 円(上限額)超 | ― | 7,420 円(上限額) |
※出典:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和6年8月1日から~」
なお、 離職時の年齢が65歳以上の場合は、失業手当(失業保険)ではなく「高年齢求職者給付金」を受給します。
基本手当日額の最高額と最低額は毎年8月に改定されるため、厚生労働省HPで最新情報をチェックしましょう。
失業手当(失業保険)のシミュレーション例
実際に下記の条件で計算してみましょう。
※なお、以下の金額計算例は2024年10月時点のものです。
基本手当日額は毎年変更になるため、最新情報は厚生労働省HPをご確認ください。
- <シミュレーション条件>
-
- 自己都合による離職
- 離職当時の年齢は25歳
- 雇用保険の被保険者期間は3年間
- 退職前6カ月間の賃金総額は2,304,000円
- Step1|
賃金日額の計算方法:
2,304,000円(退職前6カ月の賃金合計)÷180=12,800円 - Step2|
基本手当日額の計算方法:
12,800円(賃金日額)×50%(給付率) = 6,400円 - Step3|
基本手当総額の計算方法:
6,400円 (基本手当日額)× 90日(給付日数) = 576,000円
上記のシミュレーション条件の場合、離職時の年齢が29歳以下で、賃金日額が「12,790円超14,130円以下」となるため、給付率は50%となります。賃金日額の12,800円を当てはめると、基本手当日額は6,400円となり、基本手当総額は576,000円となります。
1カ月に振り込まれる失業手当(失業保険)の額を求める場合は、以下を追加するとよいでしょう。
- Step4|
1カ月の給付額の計算方法:
6,400円(基本手当日額)×28日分=179,200円
失業手当(失業保険)の算出時の注意点
基本手当日額には上限、下限が設定されています。そのため、前述の計算式を用いて算出した基本手当日額が上限額を上回った場合は、上限額が適用されるため注意が必要です。
基本手当日額の上限・下限は下記のとおりです。
- 基本手当日額の上限・下限(2024年8月更新時点)
-
29歳以下 2,295~7,065円 30歳以上45歳未満 2,295~7,845円 45歳以上60歳未満 2,295~8,635円 60歳以上65歳未満 2,295~7,420円
- ※基本手当日額の上限・下限は毎年8月ごろに変更されます。
- ※厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和6年8月1日から~」
上限、下限は変更される場合があるため、詳しくは厚生労働省HPで最新情報を確認しましょう。
5. 失業手当(失業保険)をもらうために必要な手続き

基本的な流れは上の図のとおりです。詳しくは以下で解説するので確認しましょう。
書類を準備する
ハローワークで求職の申し込みをする前に、まずは必要な書類を準備しましょう。必要書類は以下のとおりですので、チェックして忘れずに持参しましょう。
- 雇用保険被保険者離職票-1・2
- 雇用保険被保険者証
- 証明写真×2 ※たて3cm×よこ2.4cmの正面上半身のもの
- 本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
- 住所・氏名・年齢を確認できる本人確認書類
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) - 個人番号確認書類
(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか1種類)
「雇用保険被保険者離職票」の取得方法が分からない人は以下のコラムもチェックしてみてください。
ハローワークで給付の申し込みをする
上記の書類が準備できたら、管轄のハローワークへ行き、以下の手続きを行いましょう。失業手当(失業保険)の給付を受けるには、再就職の意思を示すために求職申し込みが必須となります。
- ① 求職申込書に記入する(事前にオンラインで仮登録した場合は原則不要)
- ② 必要書類の提出、職業相談を行う
- ③ 雇用保険説明会の日時決定
必要書類を提出した日が「受給資格決定日」となり、この日から7日間の待期期間が始まります。
雇用保険説明会への参加は、失業手当(失業保険)を受給するには必須事項なので、日時などをしっかりメモしておきましょう。
雇用保険説明会へ参加する
前述したとおり、失業手当(失業保険)を受給するにあたって雇用保険説明会への参加は必須事項となっています。
ハローワークで指示された日時の、雇用保険説明会に参加しましょう。説明会で渡される失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を持って、次のステップで失業認定を受けます。
ハローワークに失業認定申告書を提出する
雇用保険説明会後にハローワークへ行き、失業認定申告書を提出します。失業認定を受ける日付は、ハローワークから指定されるため、忘れないよう気をつけましょう。
初回は1回以上の求職活動で失業認定を受けることができますが、2回目以降、失業認定を受けるには2回以上の求職活動が必要になります。
受給の継続を希望するなら4週間ごとにハローワークへ通う
その後も受給の継続を希望する場合、4週間ごとにハローワークへ行き、失業認定を受ける必要があります。離職理由による対応の違いは、受給開始期間のみとなるため、会社都合の離職であっても4週間ごとに失業認定を受ける必要があります。
なお求人情報の検索・閲覧や求職の申し込みはオンライン(ハローワークインターネットサービス)でも行えるので、確認してみてください。
6. 失業手当(失業保険)に関するよくある質問
失業手当(失業保険)についてのよくある質問をまとめました。ぜひ参考にしてください。
Q.解雇されたのに離職票の退職理由が自己都合になっていた場合の対処法は?
A.離職の理由を不当に自己都合とされていた場合、ハローワークに異議を申し立てましょう。
また、離職票には自身が記載できる欄が設けられているため、会社から「自己都合」と記載されていても、正当な理由を伝えることができます。もし、会社と離職者の主張が異なる場合は、ハローワークが両者の状況を調査します。もし会社側の記載に誤りがあると判断されれば、会社都合に変更されることがあります。
Q.自己都合の退職を会社都合にしてもらうことはできる?
自己都合退職となっている場合でも、会社都合退職に変更できる可能性があります。例えば、給与の未払いがあった、勤務地や職種が採用条件と大きく異なっていた、など労働条件が当初の説明と異なる場合には変更が認められます。
このような場合には、給与口座の履歴や労働条件通知書など、証拠となる資料をハローワークに提出して判断してもらいましょう。
一方で、転職や結婚、引越しなどにより自らの意思で退職する場合は、会社都合と認められないため、留意しておきましょう。
Q.失業手当(失業保険)受給中に健康保険や年金の支払いは必要?
A.健康保険は状況に応じて対応が変わります。年金は免除制度の利用が可能です。
失業手当(失業保険)を受給して離職期間が発生する場合、健康保険に関しては下記のいずれかの状態のはずです。
- 任意継続被保険者制度を利用している
- 国民健康保険に加入している
- 家族の扶養に入っている
任意継続被保険者制度を利用する場合は、収入が減っても保険料の支払い額は変わりません。国民健康保険の場合は、会社都合による離職で雇用保険の特定受給資格者に認定されれば保険料の支払いが減免されるでしょう。
また離職中、失業手当(失業保険)受給金額が日額3,612円未満(年収130万円未満)であれば家族の扶養に入れる場合があります。ただし、健康保険組合によって定めが違う場合があるので確認しておきましょう。扶養に入る場合に支払うのは、被保険者分の保険料のみで、失業中の被扶養者から保険料が徴収されることはありません。扶養に入ったために被保険者分の保険料の金額が高くなることもありません。また、家族の扶養に入っていても、失業手当(失業保険)を受給できます。
Q.失業手当(失業保険)受給中にアルバイト・パートとして働いてもいい?
A.アルバイトやパートとして働くことは可能ですが、場合によっては給付が受けられなくなります。
待期期間として定められた7日間に働いたり、1週間の所定労働時間が20時間以上もしくは31日以上の雇用が見込まれるほど働いたり、1日で失業手当日額の80%を超える収入を得た場合、給付が受けられなくなります。また1日4時間以上働くと支給の開始が先送りになります。
Q.失業手当(失業保険)の所定給付日数を残して就職したらどうなる?
A.再就職手当をもらえます。
再就職手当とは、失業手当(失業保険)の受給資格がある人が所定給付日数を残して安定した職業に就いた場合に支給される手当です。
早期の再就職を支援するための制度で、早く再就職をすると、より給付率が高くなります。受給には以下の条件をすべて満たす必要があります。
- ■再就職手当を受給する条件
-
- 失業手当(失業保険)の待期期間経過後に就職した
- 失業手当(失業保険)の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある
- 離職前の事業主、また関連会社など密接な関係にある事業主に再び雇用されたものでない
- ハローワークの紹介または、厚生労働大臣の許可を受けた職業紹介事業者による職業に就いた(※)
- 1年を超えて安定的に雇用されることが確実な職業に就いた
- 再就職先で雇用保険の被保険者資格を取得している
- 過去3年以内の就職について、再就職手当・常用就職支度手当の支給を受けていない
- 受給資格決定前に内定を受けた事業主に雇用されたものでない
- 再就職手当の支給日が決定する前に離職していない
※dodaで取り扱っている求人には、「厚生労働大臣の許可を受けた職業紹介事業者による紹介」に該当する求人と、該当しない求人があります。dodaエージェントサービスを通じて求人に応募し、採用された場合は「厚生労働大臣の許可を受けた職業紹介事業者による紹介」に該当しますが、ご自身で企業へ応募する形の求人で採用が決定された場合はこれに該当しません。
7. 失業手当(失業保険)をはじめとした退職後の手続きを把握しよう
失業手当(失業保険)は、再就職を目指す人を支援するための給付金です。受給条件や受給期間を確認し、失業中の生活に役立てましょう。失業手当(失業保険)の受給は任意で、受給を希望する場合は書類の記入やハローワークでの手続きが必要になります。本記事を参考に、確認しながら進めていきましょう。
dodaでは失業手当(失業保険)以外にも、退職後の手続きに関する記事をご用意しています。安心して再就職に向けた活動をするためにも、各手続きの手順や必要なものを把握して不備なく進めましょう。
- 退職しようかな…と思ったらまずは会員登録して情報を集めよう!
- 会員登録する(無料)
- あなたの適正年収はいくら?転職市場の相場感を知っておきましょう
- 年収査定をする
- あなたは何を大切にするタイプ?診断で適職探しのヒントを見つけよう
- 転職タイプ診断を受ける
この記事を監修した社会保険労務士

北 光太郎(きた・こうたろう)氏
きた社労士事務所 代表 大学卒業後、エンジニアとして携帯アプリケーション開発に従事。その後、社会保険労務士資格を取得し、不動産業界や大手飲料メーカーなどで労務を担当。労務部門のリーダーとしてチームマネジメントやシステム導入、業務改善などさまざまな取り組みを行う。2021年に社会保険労務士として独立。労務コンサルのほか、Webメディアの記事執筆・監修を中心に人事労務に関する情報提供に注力。読者に分かりやすく信頼できる情報を伝えるとともに、Webメディアの専門性と信頼性向上を支援している。
ステップで分かる転職ノウハウ
転職に役立つ!テンプレート・ツール集
なるほど!転職ガイド
人気ランキング
-
1

-
2

-
3

-
4

-
5