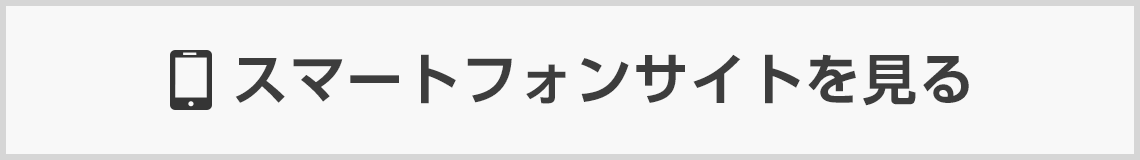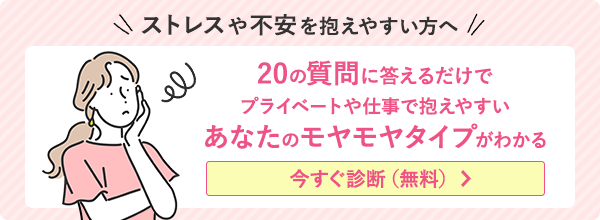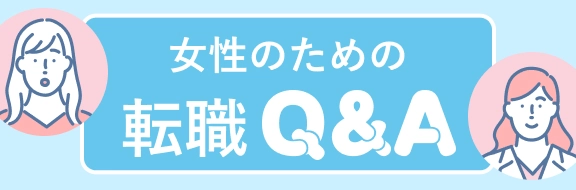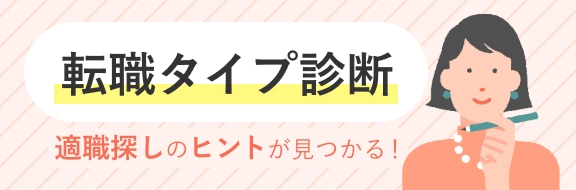働く女性が知っておきたい妊娠・出産・育児の制度


出産手当金が早く欲しいときは分割申請を活用!条件や計算方法も解説
更新日:2024年5月27日
産休・育休中の収入確保のため、少しでも早く出産手当金を支給してほしい人もいるでしょう。そこで今回は、出産手当金が早く欲しい場合に活用できる分割申請の流れや受給条件、支給金額の計算方法、転職直後に申請できるかなどについて紹介します。産休に入る前にしっかりと確認して、安心して出産に臨みましょう。
出産手当金とは?

労働基準法では、原則として産前6週間と産後8週間は就業が禁止されており、本人が希望すれば産前・産後休業を取得し会社を休めます(※1)。
しかし、その間の収入は保証されていないため、これを補填する目的で出産手当金が支給されます(※2)。
出産手当金は健康保険組合(または協会けんぽ、共済組合)から給付を受けられます。
ただし、一部の健康保険組合では給付制度がない場合があるので勤務先に確認してみましょう。
自営業やフリーランスの人が加入する国民健康保険にも、出産手当金がないため支給されません。
出産手当金と出産育児一時金の違い
妊娠・出産に関係する給付金は、出産手当金のほかに「出産育児一時金」があります。ともに健康保険から支給されるため混同されがちです。
どのような違いがあるか確認しておきましょう(※2,3)。
| 出産手当金 | 出産育児一時金 | |
|---|---|---|
| 受取条件 | 出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産翌日以降56日までの範囲に会社を休み、この間の収入がない被保険者(被扶養者は対象外) | 妊娠4カ月(85日)以上で出産した被保険者(被扶養者も対象) |
| 受取金額 | 標準報酬月額平均の3分の2(詳しい計算方法については「出産手当金としてもらえる金額」に記載) | 1児につき50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関の場合は48.8万円) |
| 対象期間 | 出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産翌日以後56日までで、給与の支払いがなかった期間 | 一時金なので期間はない |
| 手続方法 | 勤務実態や給与について事業主の証明が必要。産休前に書類を用意し、本人以外に医師と事業主にも記入してもらい、窓口に提出 | 医療機関が本人に代わって申請する「直接支払制度」が一般的。本人が出産費用を負担し、出産後に支給申請を行う方法も選択可能 |
| 申請期限 | 出産のため会社を休んだ日ごとに、その翌日から2年以内 | 出産日の翌日から2年以内 |
| 注意点 | ・退職後の出産の場合、在職中に1年以上の被保険者期間があり、出産手当金をすでに受給しているか受給条件を満たしている場合に支給される ・休暇期間中に有給休暇を使うと支給額が減額(社内規則上、ボーナス支給日に会社に在籍して給与をもらう必要がある、などのケース) |
・退職後の出産の場合、在職中に1年以上の被保険者期間があると、退職日の翌日から6カ月以内の出産であれば受給できる ・分娩に関連して障害を負った場合、別の制度が存在 ・妊娠4カ月(85日)以上の中絶や早産も支給対象 |
| 窓口 | 健康保険組合(または協会けんぽ、共済組合)・勤務先 | 健康保険組合(または協会けんぽ、共済組合)・医療機関 |
適用条件や金額については上記以外のケースも存在します。詳しくは申請時に窓口で確認してください。
なお、共済組合の場合、出産育児一時金ではなく「出産費(家族出産費)」と呼ばれます。
出産手当金としてもらえる金額
出産手当金は、出産前の標準報酬月額や出産予定日との差異によって金額が変動します(※2)。
対象期間
出産手当金の対象となる期間は、出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産日の翌日以後56日の合計98日間となります。
つまり産前・産後休業の間です。実際の出産日が予定日より遅れた場合は、出産予定日から出産日までの日数も対象期間に含まれます。
給与の約3分の2相当が支給される
1日当たりの支給額は、以下の計算式で求められます。
1日当たりの支給額=支給開始以前12カ月間の平均標準報酬月額÷30日×2/3
支給額の計算方法について、具体例を見てみましょう。
<例:支給開始以前12カ月間の平均標準報酬月額が21万円のときの1日当たりの支給額>
210,000円÷30日=7,000円(端数が出た場合には10円未満を四捨五入)
7,000円×2/3=4,667円(端数が出た場合には1円未満を四捨五入)
つまり、1日当たり4,667円が会社を休んだ日数分だけ支給されます。では次に、総支給額を計算してみましょう。
例えば、産前休業を最大日数(42日)取得し、予定日より4日遅れて出産し、産後休業を最大日数(56日)取得した場合の総支給額は以下のとおりです。
支給日数:42日+4日+56日=102日
総支給額:4,667円×102日=476,034円
よって支給総額は476,034円です。
ただし、対象期間中、出産手当金より少ない給与が支払われている場合は、差額分のみの支給となります。
出産手当金の受取条件と申請方法
次に、出産手当金を受け取るための条件や申請方法について詳しく見ていきましょう(※2)。
健康保険の被保険者であること
出産手当金を受け取るには、本人が会社の健康保険の被保険者であることが条件となります。このため、国民健康保険の加入者は出産手当金を受給できません。
会社の健康保険の被保険者であれば、契約社員やアルバイト、パートでも給付対象となります。
会社を辞めた場合、個人で加入できる任意継続被保険者だと原則として給付の対象外になるため、注意が必要です。
特定のケースでの支給条件
【転職直後の場合】
健康保険の被保険者であれば転職直後でも受給できますが、書類の提出が必要になります。
標準報酬月額を用いた金額の算出に注意が必要なため、各健康保険組合の規約を確認しましょう。
【退職後に出産した場合】
退職後に出産した場合でも、以下の条件を満たす場合は受給対象になります。
- ・退職前に1年以上被保険者である
- ・退職時に出産手当金を受給している、または受給条件を満たしている
- ・退職日に出勤していない
なお、退職日に引継ぎやあいさつ回りなどの目的で出勤してしまうと、3番目の「退職日に出勤していない」を満たせなくなるので注意しましょう。
【傷病手当金が同時に受けられる場合】
出産手当金と傷病手当金が同時に受けられる場合は出産手当金が優先され、この期間は傷病手当金の支給はされません。
傷病手当金の額が出産手当金を上回る場合には、差額分が支給されます(※4)。
申請方法
出産予定日が分かったら、産休に入る前に申請書を用意しましょう。
会社が用意してくれる場合もありますが、自分で申請書を取り寄せる場合には協会けんぽ、または加入先の健康保険組合のホームページからダウンロードすることができます(※5)。
申請書に以下の内容を記載し、必要に応じて証明書類を添付して勤め先に提出します。
- ・被保険者証の記号および番号、または個人番号(マイナンバー)
- ・振込先口座
- ・出産予定日(出産前の申請)または出産日と出産予定日(出産後の申請)
- ・出産のため労働に従事しなかった期間とその日数
- ・医師または助産師による、出産日・出生児数・医療機関名などの証明欄への記入
- ・事業主の証明書
なお、マイナンバーを記載した場合は、別途、身元確認ができる資料が必要になります。
駆け込み申請には注意
出産手当金の申請期限は出産のために会社を休んだ日の翌日から2年以内です。
ただし、出産手当金は1日単位で支給されるため、申請期限も1日ごとに設定されます(※5)。
出産育児一時金を自分で事後申請するときに、出産手当金もいっしょに申請する人もいると思いますが、そのときは注意してください。
出産育児一時金の申請期限は「出産日の翌日から2年以内」であるため、2年以内の申請であればいつでも満額を受け取れます(※6)。
しかし、出産手当金の申請期限は上述のとおりなので、タイミングによっては一部しか受け取れないことがあります。
【出産手当金が一部しか受け取れない例】
出産予定日と出産日、そして出産育児一時金と出産手当金の申請日が以下のとおりだったとします。
- ・出産予定日:2024年11月30日
- ・出産日:2024年11月30日
- ・申請日:2026年11月23日
申請日は出産日の翌日から2年以内であるため、出産育児一時金は満額もらえます。
一方、出産手当金の支給対象期間は42日前の2024年10月20日から2025年1月25日までになります。
しかし、2024年10月20日から2024年11月22日までの分が申請期限を過ぎているため、受け取れるのは2024年11月23日から2025年1月25日までの分だけです。
こういったことにならないよう、産休前にあらかじめ出産手当金の申請をしたい旨を勤務先に伝えておき、産休中に申請書を書き進めておくとよいでしょう。
入金が遅い場合の確認方法
出産手当金の入金が遅い場合、給与計算のタイミングの兼ね合いで、勤務先から健康保険組合などへの申請がまだ行われていない可能性があります。
申請書を勤務先に提出する際には、あらかじめ健康保険組合などへの申請時期を教えてもらっておくとよいでしょう。
また、記入ミスなど申請書類の不備により手続きが止まっているケースもあります。心配な場合は、勤務先や健康保険組合などに問い合わせてみてください。
出産手当金が早く欲しいときは分割申請の検討を

出産手当金が振り込まれるのは産休終了の1~2カ月後なので、産休中の生活費には充てられません。
そのため、産休中の生活費は貯金をしておくなど事前に用意する必要があります。
とはいえ、長期間収入がないとだんだん不安になってしまうでしょう。そこで、出産手当金が早く欲しいときには分割申請の検討をおすすめします(※2)。
産前と産後に分けて申請
分割申請は、出産手当金を少しでも早く欲しい場合に、産前分と産後分など複数回に分けて申請できるシステムです。
給与のように毎月申請することもできます。
ただし、勤怠状況や給与の支払い状況などの申請書の事業主が記入する欄は、申請のたびに毎回勤務先に記入してもらう必要があります。
一方で、医師や助産師が記入する欄は、2回目以降の申請では不要になるケースもあります。詳しくは健康保険組合に確認しましょう。
健康保険・厚生年金の支払いはどうなる?
出産手当金を分割申請しても、多くのケースでは入金まである程度時間がかかってしまうため、産休中は出費をできるだけ抑えたいところです。
幸い、産休の開始月から職場復帰予定月の前月までは健康保険と厚生年金保険の保険料が免除されます。
しかも、年金額を計算する際には保険料を納めた期間としてカウントされるため、将来受け取れる年金額が減ることはありません(※7)。
出産手当金は、出産のために給与を受けられない期間の収入を保障するためのお金です。出産費用の負担を軽減させ、安心して出産・育児ができるように、出産手当金を活用しましょう。
参考
※1 厚生労働省「働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について」
※2 全国健康保険協会「出産手当金について」
※3 全国健康保険協会「子どもが生まれたとき」
※4 全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
※5 全国健康保険協会「健康保険出産手当金支給申請書」
※6 全国健康保険協会「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書」
※7 日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が産前産後休業を取得したときの手続き」
監修者:社会保険労務士法人クラシコ/代表 柴垣 和也(しばがき・かずや)
昭和59年大阪生まれ。人材派遣会社で営業、所長(岡山・大阪)を歴任、新店舗の立ち上げも手がけるなど活躍。企業の抱える人事・労務面を土台から支援したいと社会保険労務士として開業登録。講演実績多数。
社会保険労務士法人クラシコ(https://classico-os.com/)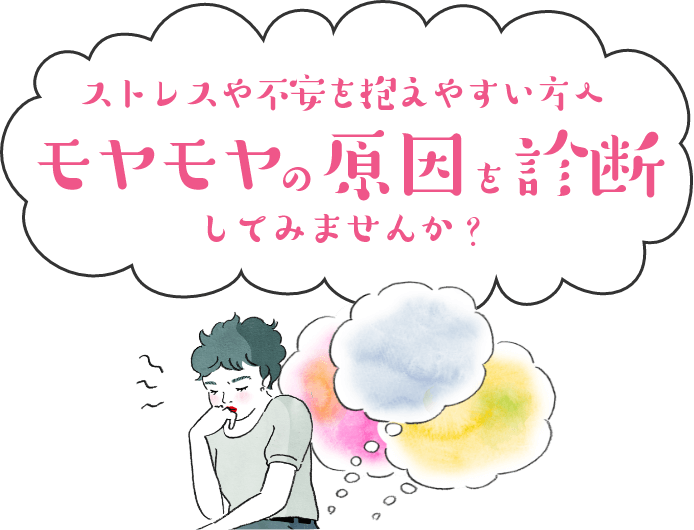
20の質問に回答するだけ
解消のヒントが見つかる
- あなたの基本性格
- 日常生活や職場での傾向・
クセを9つのタイプから診断!
- 生き方のヒント
- あなたの不安や悩みに
大きく影響している
モヤモヤの種類とアドバイス
- キャリアのヒント
- 今後のキャリアの不安や
不満を解消する
満足度UPのポイントを紹介
- 疑問・悩みが解決したら、気になるこだわり条件から求人を探そう!
- 求人情報を検索する
妊娠中
産前・産後
育児と仕事の両立
- 時短勤務で給料は変わる? 残業代や年金の算出方法も詳しく解説
- あなたは大丈夫?育児休暇や時短勤務が適用されないケースに要注意
- 働く女性を守る制度「育児時間」とは? さまざまな疑問をまとめて解決
- 育児休業の期間はどのくらい? 延長できるケースや給付金も徹底解説
- 夫婦二人で育児休暇を取るために「パパ・ママ育休プラス」を利用しよう
- 育児休業給付金の支給条件や計算方法を知って育休期間をより安心に!
- 3歳までの子育てには短時間勤務制度を使いこなそう!
- 子どもの病気やけがには看護休暇を! 半日や時間単位で取得できる?
- 妊娠や出産を原因とする会社とのトラブルは「紛争解決援助制度」で解決を
- 幼児教育・保育の無償化の適用条件は? よくある疑問も解説
- 働くママ必見! 仕事と家庭の両立に役立つ制度や方法を紹介
- 地域で子育てを支援するファミリーサポートセンター事業とは
- 共働きで子どもが病気にかかった場合は「病児保育」を活用しよう