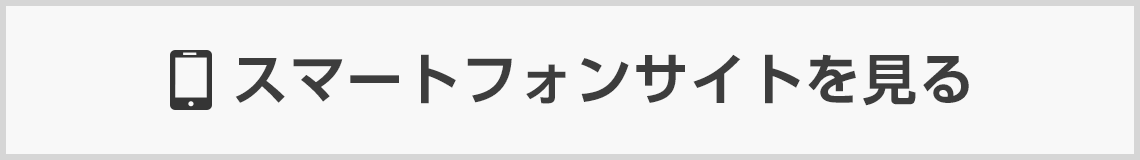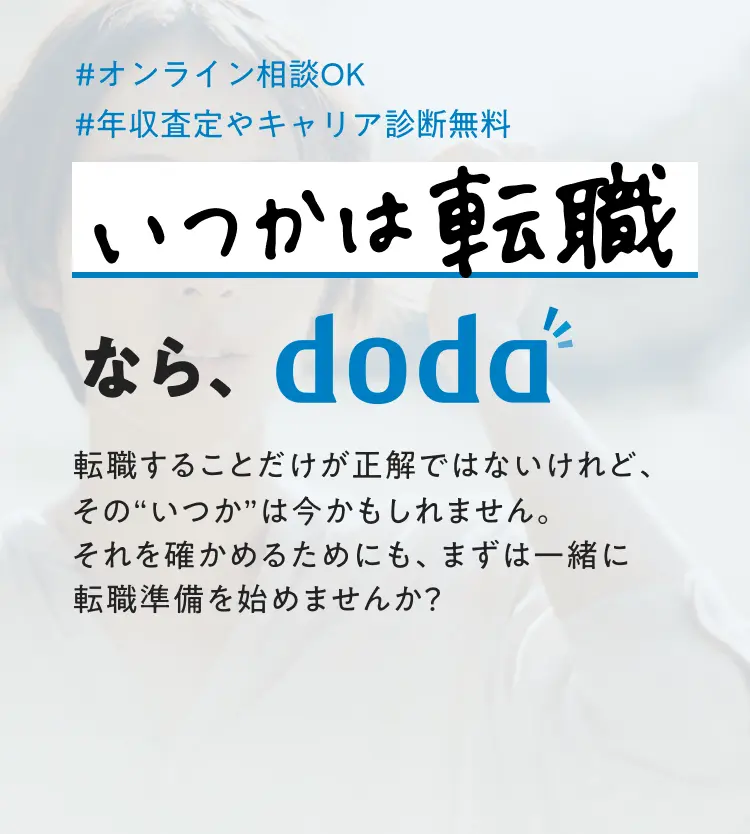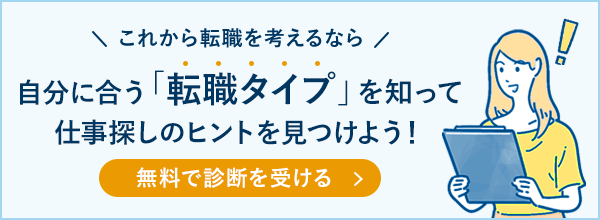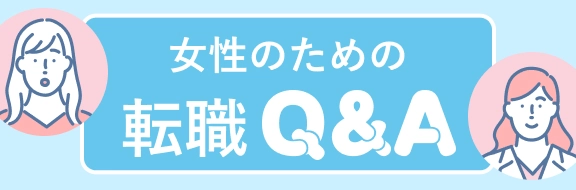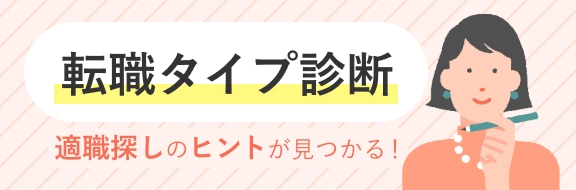働く女性が知っておきたい妊娠・出産・育児の制度


出産後の再就職はこれをチェック!働きやすい仕事探しのポイント
更新日:2024年5月27日
出産後に再就職を目指す女性は多いと思います。しかし、いざ仕事を探そうとすると、子どもの預け先の確保や保育園のお迎え時間に合わせて働く必要などが出てくるでしょう。そこで今回は、出産後の再就職はいつからがよいのか、働きやすい仕事探しで重視すべきポイント、さらには再雇用制度などについて解説します。
出産後の再就職のタイミング

妊娠や出産を理由に退職したものの、仕事をしたくなったり、もしくはやむを得ない事情で働く必要が出てきたりすることで、再就職を望む女性は多くいます。
とはいえ、産後は生活が子ども中心に変化します。子育てと仕事を両立させるには気力も体力も必要です。
その結果、出産前のような働き方ができなくなるかもしれません。
そこで、出産後の再就職について、産後の状態も踏まえてベストなタイミングを考えてみましょう。
生後6カ月程度まで
再就職先を探すにしても、赤ちゃんが生後6カ月になるくらいまでは慎重さが求められます。
原則として、産後8週間は法律で就労が禁止されています。この期間は、体力の回復や生まれたばかりの赤ちゃんと一緒に過ごすことに専念しましょう。
産後8週間を超えるか、もしくは産後6週間経過後に自ら働く意思を示し、かつ医師が認めた場合に限って就業が可能です(※1)。
しかし、しばらくは授乳など赤ちゃんのお世話に手がかかり、慣れない子育てで疲れがたまりがちなので無理は禁物です。
生後6カ月~3歳
生後6カ月を過ぎると利用可能な託児所や保育園が増えるので、子どもを預けて再就職のために活動し始める人が出てきます。
個人差がありますが、出産直後と比べて体力的・精神的な余裕が出てくる時期です。
早期に再就職を目指すのであれば、この時期に転職活動をするのも一つの手でしょう。
託児所や保育園は、地域によっては1歳児よりも0歳児のほうが定員が多く、入園倍率が低い場合があります。
募集状況を確認し、必要に応じて早めに動き出してもよいかもしれません。
ただし、生後6カ月~3歳ごろまでは急な発熱などで託児所や保育園からの呼び出しが多くなりがちです。
家族や頼れる人の協力を得ておいたり、地域の育児支援サービスについて調べておいたりして、いざというときに備えておくことが大切になります。
3歳以降
もう一つの再就職のタイミングは、子育てが少し落ち着く3歳ごろになってからです。
預け先も比較的見つけやすく、子どもの体調も安定してくるため、職場選びの選択肢も広がります。
再就職での働きやすい仕事探しのポイント
出産後は子どもを中心としたライフスタイルにシフトせざるを得ません。
そのため、再就職先の選択においては、これまでのキャリアを活かしつつも、子育てとの両立ができるかどうかを確認することが大切です。
それを踏まえて再就職先を選ぶ際のポイントや、効率よく求人情報を探す方法を押さえておきましょう。
育児中の社員や産休中の女性がいるか
出産後の再就職先として重視すべきポイントの一つは、育児中の社員や産休中の女性が在籍しているかどうかです。
同じ境遇の人が多くいる職場であれば、会社の理解もあり、受け入れ体制が整っていて働きやすい環境である可能性が高いでしょう。
柔軟な働き方が可能か
子どもが小さいうちは、急な病気や保育園の行事などで仕事を休まなければならないことが多くあります。
そのため、柔軟な働き方を推進している職場かどうかも重要なポイントです。
例えば、以下のような点を調べるとよいでしょう。
- ・有給休暇の取得率や、振替休日について就業規則に規定があるか
- ・半日休暇制度や時間単位の有給休暇制度があるか
- ・リモートワークやフレックスタイム勤務が可能か
さらに、保育園への送り迎えも考えると、通勤時間の長さや残業の有無も重視すべきポイントです。
認定を受けているか
企業のウェブサイトや求人情報だけでは実際に子育てと両立しやすいかどうか判断が難しい場合もあります。
そのようなときは、「くるみん」や「えるぼし」といった指標も参考になるでしょう。
これらは国が実施しており、仕事と子育ての両立支援に取り組んでいる、あるいは女性の活躍を推進しているなどと判断された企業が認定されます。
ただし、福利厚生などの条件を過度に重視すると、仕事内容にミスマッチが発生することもあります。
自分のやりがいと会社の方向性が合っているかの確認も怠らないようにしましょう。
出産後の再就職に役立つ制度や支援サービス
一度退職してブランクができてしまうと、再就職して新しい環境に飛び込むことや、一人での就職活動が不安に感じることもあるでしょう。
そこで、ここからは再就職に役立つ制度や支援サービスを紹介します。
再雇用制度を活用する
企業によっては、再雇用制度を設けているところがあります。再雇用制度とは一度退職した社員を再び雇い入れる制度のことです。
再雇用制度を設けている企業の多くは、「これまでの業務経験を活かして働いてもらえる」「会社への愛着がある人を雇用できる」といった点に期待しています。
再雇用される側からすると、慣れ親しんだ環境で働けるため職場に溶け込みやすく、即戦力として活躍しやすいというメリットがあります。
以前の勤務先が再雇用制度を導入している場合には、出産後の再就職先として検討してみてください。
その際、事前に企業側と面談する機会がある場合は、以下の点について話し合っておくと安心です。
- ・離職前との業務内容の違い
- ・雇用形態などの勤務条件
- ・希望する条件
なお、再雇用制度には退職前の勤続期間、退職理由、離職期間などの適用条件が定められている場合があります。
この条件は会社ごとに異なるので、制度の利用を検討するときは会社の担当部署に確認しましょう。
仕事と育児カムバック支援サイトを活用する
再就職に向けて一人での就職活動に不安がある場合には、「仕事と育児カムバック支援サイト」を活用するという方法もあります(※2)。
仕事と育児カムバック支援サイトは厚生労働省が管轄しているウェブサイトです。
育児休業からの復職や、育児などを機に退職した女性の再就職を支援するために情報提供をしています。具体的には以下のとおりです。
- ・再就職支援情報や保育園の状況などを地域別に検索
- ・休業中に受け取れる給付金などについての解説
- ・子育てをしながら再就職を目指す女性が意見交換できる交流掲示板
- ・悩みや疑問を相談できるコンテンツ
- ・再就職経験者の体験談
- ・不安解消のためのQ&A集 など
マザーズハローワーク・マザーズコーナーを利用する
厚生労働省が運営している「マザーズハローワーク・マザーズコーナー」は、子育てをしている人のための就職支援施設です(※3)。
キッズスペースや授乳室、オムツ替えのスペースなどが設置されているので、子ども連れでも利用しやすい環境になっています。
就職相談は専属スタッフが担当してくれ、子育てと両立しやすい仕事の紹介も可能です。
そのほか就職に役立つセミナーの実施や、保育園などの子育て支援の情報も提供してくれるため、きめ細かなサポートが期待できます。
無料で利用できるので、検討してみてはいかがでしょうか。
転職エージェントを利用する
一般的に、転職エージェントでは以下のようなサポートやサービスを受けられます。
- ・これまでのキャリアのヒアリング
- ・希望条件をもとにした求人の紹介
- ・履歴書の書き方や面接のアドバイス
- ・応募書類の提出や雇用条件の交渉などの代行
福利厚生や子育て支援制度の取得実績といった、直接企業に聞きづらい情報をキャリアアドバイザー経由で確認できるのも心強いポイントです。
一人での転職活動に不安がある人は利用してみるとよいでしょう。
出産を機に退職した女性にとって、子どもを育てながら再就職に向けて一歩を踏み出すのはとても勇気がいることです。
今回ご紹介した内容を参考に、ライフスタイルの変化に合わせて自分自身が満足できる再就職を目指しましょう。
参考
※1 厚生労働省「産前・産後休業を取るときは」
※2 厚生労働省「仕事と育児カムバック支援サイト」
※3 厚生労働省「マザーズハローワーク事業」
監修者:社会保険労務士法人クラシコ/代表 柴垣 和也(しばがき・かずや)
昭和59年大阪生まれ。人材派遣会社で営業、所長(岡山・大阪)を歴任、新店舗の立ち上げも手がけるなど活躍。企業の抱える人事・労務面を土台から支援したいと社会保険労務士として開業登録。講演実績多数。
社会保険労務士法人クラシコ(https://classico-os.com/)
復職を考えているけど、今の
仕事が向いているかわからない
キャリアや家庭など
何を重視して働けばいいか悩む
自分の志向性を知って
これから転職するか考えたい
このようなお悩みを持つ方には
転職タイプ診断がおススメ!
- 転職タイプ診断でわかること
- 仕事をするときに大切にしたい軸
- 仕事で満足・不満を感じるポイント
- 適職探しのアドバイス


今すぐ転職を考えていなくても、
自分の志向を知って今に活かそう!
- 仕事やプライベートで抱えやすいあなたのモヤモヤタイプが分かる
- モヤモヤ解消診断を受けてみる(無料)
- 疑問・悩みが解決したら、気になるこだわり条件から求人を探そう!
- 求人情報を検索する
妊娠中
産前・産後
育児と仕事の両立
- 時短勤務で給料は変わる? 残業代や年金の算出方法も詳しく解説
- あなたは大丈夫?育児休暇や時短勤務が適用されないケースに要注意
- 働く女性を守る制度「育児時間」とは? さまざまな疑問をまとめて解決
- 育児休業の期間はどのくらい? 延長できるケースや給付金も徹底解説
- 夫婦二人で育児休暇を取るために「パパ・ママ育休プラス」を利用しよう
- 育児休業給付金の支給条件や計算方法を知って育休期間をより安心に!
- 3歳までの子育てには短時間勤務制度を使いこなそう!
- 子どもの病気やけがには看護休暇を! 半日や時間単位で取得できる?
- 妊娠や出産を原因とする会社とのトラブルは「紛争解決援助制度」で解決を
- 幼児教育・保育の無償化の適用条件は? よくある疑問も解説
- 働くママ必見! 仕事と家庭の両立に役立つ制度や方法を紹介
- 地域で子育てを支援するファミリーサポートセンター事業とは
- 共働きで子どもが病気にかかった場合は「病児保育」を活用しよう