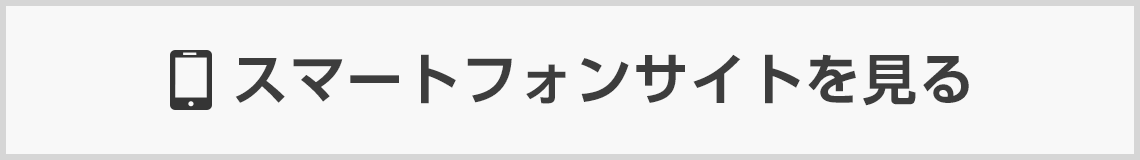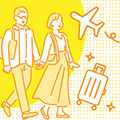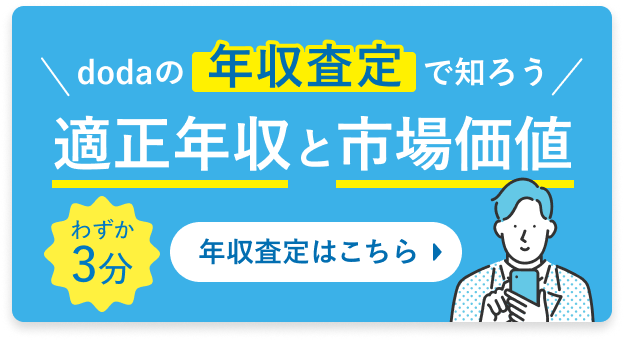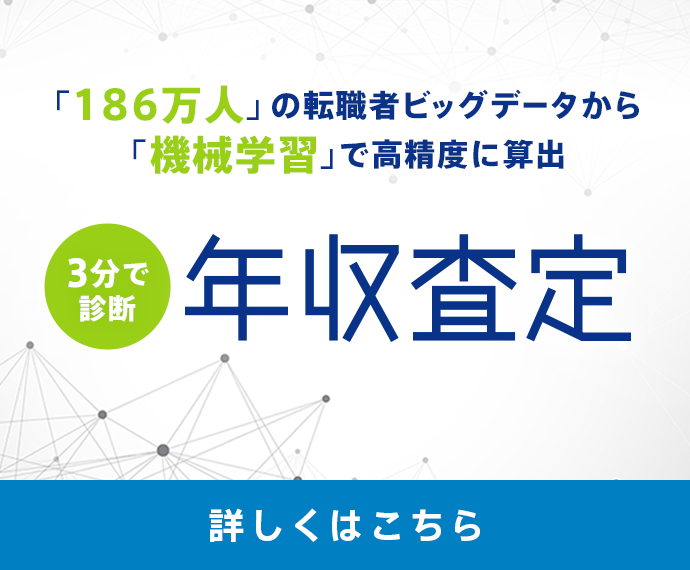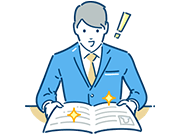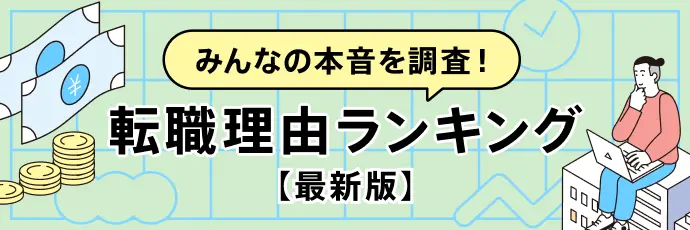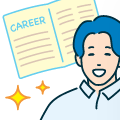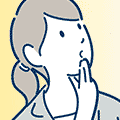転職Q&A(お金)#ボーナス
Q. ボーナスはいつ支給される?賞与との違いや計算方法を知りたい
「現在、転職活動中なのですが、求人を見ていると「ボーナス」と書いてある会社、「賞与」と書いてある会社ががあります。この二つは何が違うのでしょうか。また、ボーナスはいつ支給されることが一般的ですか? ボーナスの種類や支給される金額の計算方法など、基本的な情報を分かりやすく教えてほしいです。(26歳・男性)」
A.ボーナスがいつ支給されるかは会社によって異なりますが、多くは夏季と冬季の2回です。毎月の給与とは別に支払われる特別報酬」を指します。
ボーナスは、公務員の場合は支給日が定められていますが、民間企業の場合は会社によって異なり、一般的には夏と冬の2回支給のパターンになっています。また、ボーナスは法律上、支給が必須なものではないため、会社によってはボーナスがないこともあります。
そもそもボーナス(賞与)とは?
ボーナスとは、毎月支給される定期給与とは別に、企業の業績や労働者の評価などに応じて支給される給与のことです。同じ意味で「賞与」という言葉が使用されることもあるほか、「特別手当」「夏季手当」「年末手当」「期末手当」などとも呼ばれています。
ボーナス(賞与)の種類
ボーナスには「基本給連動型賞与」「業績連動型賞与」「決算賞与」の3種類があります。それぞれの特徴をご紹介します。
基本給連動型賞与
基本給連動型とは、その名のとおり基本給と連動して支給されるボーナスのことで、多くの会社で採用されています。就業規則などで「基本給◯カ月分」と記載されている場合はこのタイプに当たります。基本給は、毎月支払われる給与の総額から残業手当などの各種手当を引いたものを指すので、支給総額と同じ意味と勘違い誤認しないように注意しましょう。
基本給連動型賞与は基本給に支給される月数を乗じるだけで求められるので、計算が簡単で分かりやすい点がメリットです。しかし、基本給に連動するため、成果の大小にかかわらず、所属年数や役職に応じた金額が支給される傾向にあります。個人の業績が反映されにくいため、「業績連動型賞与」との併用を採用し「基本給×◯カ月分」と「個人の成果または企業の業績分の賞与」を合算して支給している会社もあります。
業績連動型賞与
業績連動型賞与とは、成果によって支給される賞与のことです。個人の成績や部門・会社の業績と連動して支給額が毎回変わるのが特徴です。業績によってボーナスの額が決まることから、社員のモチベーションアップにつながりやすくなります。
しかし、個人の成績や企業の業績に応じた金額が支給されるということは、個人の成績によってはボーナスを受け取れない可能性も出てきてしまいます。そこで「基本給連動型賞与」と併用し、業績分の賞与に加えて「基本給×◯カ月分」を支給している会社もあります。
決算賞与
決算賞与とは、決算月前後の会社の業績によって金額が決まる賞与です。夏季や冬季の賞与はほぼ毎年受け取れますが、決算賞与はそもそも支給されるかどうかが、会社の業績によって決定します。
そのため、夏季や冬季の賞与とは別に支給されるパターンもあれば、決算賞与のみというパターンもあります。決算賞与は通常の賞与以上に決算結果とダイレクトにつながっているので、業績連動型賞与と同様、社員のモチベーションアップにつながりやすいタイプの賞与です。
ボーナスの支給額が会社の業績に左右されるため、業績連動型賞与と同様にボーナスの支給額が増減しやすい特徴があります。
ボーナス(賞与)はいつ支給される?
ボーナスの支給時期は、民間企業と公務員とで異なります。具体的な支給時期を見ていきましょう。
民間企業の場合
民間企業のボーナスの支給日は、各会社の裁量に委ねられています。会社によって、年1回や年2回、四半期ごとなどと、年間の支給回数が異なります。ボーナスを年2回支給する場合は、1回目が5月下旬から7月下旬、2回目が12月中旬であることが一般的です。
民間企業のボーナスの支給日は決まりがないため、支給日が気になる方は、人事担当者に聞くか就業規則を通して確認しましょう。
【doda/最新調査】15,000人に聞いたボーナス支給日の実態はこちら
公務員の場合
公務員の場合は年2回のボーナスがあり、支給日が決まっています。自身で支給日を確認する必要はありません。国家公務員は1回目が6月30日、2回目が12月10日に支給されます。地方公務員の場合は各自治体の条例によって定められていますが、国家公務員の支給日と同じなのが一般的です。
また、公務員はボーナスの名称が「期末手当」や「勤勉手当」となっており、民間企業とは異なります。
ボーナス(賞与)の支給日を確認する方法
ボーナスの支給日を知りたいときに、まずチェックするべきは求人票です。求人票にはそもそもボーナスが支給されるか否かの記載があるので、応募前にしっかり確認しておきましょう。
次に確認できる書類は就業規則です。就業規則では一般的に、査定期間やいつごろ支給されるか、算定基準などが記載されています。また、会社によってはメールや社内の掲示板などで支給日を案内する場合もあるため、入社後に正確な支給日が分かるという場合もあります。
ボーナス(賞与)の計算方法
ボーナスの支給額は各会社の方針や業績状況によって変化します。
基本給連動型賞与の場合、一般的には「基本給×月数」で算出され、この金額がボーナスの支給総額になります。
実際に受け取れる金額は、ボーナスから社会保険料と所得税を差し引いた金額です。「(ボーナスの支給額)-(社会保険料 + 所得税)」と計算すると、手取り額を求められます。
ちなみに、社会保険料とは一般的に「健康保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」「介護保険料(40歳以上のみ)」のことです。所得税とは、1年間の収入に対してかかる税金のことをいいます。
ボーナス(賞与)から引かれる社会保険料の計算方法
ボーナスから引かれる社会保険料の金額は、ボーナスの支給額面にそれぞれの保険料率を掛けることで算出できます。詳しくは「ボーナス(賞与)から社会保険料+所得税を引いた手取り金額の計算方法」をご覧ください。
| 社会保険料 | 算出方法 | 保険料率 |
|---|---|---|
| 健康保険料 | ボーナス支給額(1,000円未満切り捨て)× 労働者が負担する健康保険料率 | 企業が加入している健康保険組合ごとに健康保険料率は異なるが、 会社と労働者で折半して負担する。 |
| 厚生年金保険料 | ボーナス支給額(1,000円未満切り捨て)× 労働者が負担する厚生年金保険料率 | 厚生年金保険料18.3%を企業と折半するため、 労働者が負担する厚生年金保険料は9.15%となる。 |
| 雇用保険料 | ボーナス支給額 × 労働者が負担する雇用保険料率 | 労働者が負担する雇用保険料率は、 事業の種類が「一般」の場合は0.55%、 「農林水産・清酒製造」「建設」の場合は0.65%となる。 |
| 介護保険料 (40歳以上のみ) |
ボーナス支給額(1,000円未満切り捨て)×労働者が負担する介護保険料率 | 企業が加入している健康保険組合ごとに介護保険料率は異なるが、 会社と労働者で折半して負担する。 |
ボーナス(賞与)から引かれる所得税の計算方法
ボーナスから引かれる所得税は「所得税 =(ボーナスの支給額-社会保険料)× 所得税率」で求められます。詳しくは「ボーナスから引かれる所得税の計算方法」をご覧ください。
所得税率は、前月の給与から社会保険料を差し引いた金額と扶養親族の人数で決まります。国税庁が公表している「賞与に関する源泉徴収税額の算出率の表」に、社会保険料や扶養親族の人数を当てはめると料率が分かるので、計算してみてください。
ボーナス(賞与)の手取り金額シミュレーション例
ここでは、ボーナスの手取り金額のシミュレーション例を紹介します。詳しくは「年齢・シチュエーション別:ボーナスの手取り金額のシミュレーション例」をご覧ください。
質問者様の年齢である26歳を例に、シチュエーションは、独身・一般の事業・協会けんぽ(東京)・前月給与25万円・ボーナス支給額50万円でシミュレーションしていきます。
上記のシチュエーションから算出された各料率は、以下のとおりです。
- 健康保険料率:4.95%
- 厚生年金保険料率:9.15%
- 雇用保険料率:0.55%
- 介護保険料率:0%
- 所得税率:4.084%
各料率から、社会保険料の合計は73,250円、所得税は17,428円が算出されます。ボーナス支給額の50万円から社会保険料と所得税を差し引き、ボーナスの手取り額は409,322円ほどと考えられます。
ボーナス(賞与)に関するよくある質問
最後に、ボーナスに関するよくある質問を3つ紹介します。
ボーナス(賞与)の平均支給額は?
dodaが独自で調査した結果によると、2024年調査のボーナスの平均支給額は、年間で106.7万円となっています。2023年の調査では年間の平均支給額が107.1万円でしたので、0.4万円減少しました。内訳は、冬は50.4万円で前年から0.3万円減少、夏が51.0万円で前年から0.2万円増加という結果でした。
20代のボーナスの平均支給額は、年間で74.8万円です。2023年の調査では70.9万円でしたので、3.9万円も増加しました。この支給額は、月収の平均2.4カ月分という結果でした。内訳を見ると、冬は34.5万円で前年から2.2万円の増加、夏は36.1万円で前年から2.5万円の増加となっています。
ボーナス平均支給額の実態調査【最新版】(冬・夏、年代別、職種別の賞与)
ボーナス(賞与)は転職1年目でももらえる?
転職先のボーナス支給に関する規定によっては、転職1年目でもボーナスがもらえます。一般的に、賞与の支給対象期間(実際に勤務した期間)を設けており、その期間中の勤務実績に応じて支給額が査定されます。
例えば、冬季賞与の査定期間が4月から9月までの場合、7月に入社した人は査定期間が3カ月間となります。
この場合、本来支給されるボーナスよりも金額の少ない寸志という形で支給される可能性が高くなります。
ただし、企業によっては「在籍期間が一定以上でないと支給対象にならない」といった条件を設けている場合もあります。在籍期間の条件がある場合は、1回目のボーナスが支給されない可能性もあることを把握しておきましょう。
ボーナス(賞与)は退職予定でももらえる?
ボーナスは、支給後にすぐ退職する場合でも受け取る権利があります。ただし、賃金規定でボーナスについて定めていない場合は、減給されたり支給されなかったりする可能性もあります。また、ボーナスの支給条件も会社によって異なり、退職が決まっていると支給対象外となるケースもあるので、賃金規定で支給条件を確認しておきましょう。
【監修】弁護士法人大知 田中法律事務所(べんごしほうじんたいち たなかほうりつじむしょ)/代表 田中 芳太郎(たなか・よしたろう)
平成2年熊本県生まれ。東京大学卒。東京大学法科大学院在学中に司法試験に合格。司法修習を経て、弁護士法人大知 田中法律事務所に勤務。令和7年4月より、同事務所代表となる。熊本を中心に、多数の企業の顧問弁護士を務め、労務相談を受けている。
- 今のあなたの適正年収を調べてみよう(約3分)
- 年収査定をする
- あなたは何を大切にするタイプ?診断で適職探しのヒントを見つけよう
- 転職タイプ診断
- 転職活動しようかな…と思ったらまずは相談&転職の情報収集を
- エージェントサービスに申し込む(無料)
バックナンバー
- #すべて
- #給与
- #ボーナス
- #年金
- #雇用保険
- #健康保険
- #税金
- #退職一時金企業年金
- #手続き
- #その他の福利厚生
- 転職1年目でもボーナスはもらえる?入社後いつからもらえる?
- ボーナス(賞与)はいつ支給される?種類や金額の目安など基本の解説!
- ボーナス(賞与)の手取り金額の計算方法
- 慶弔休暇とはどんな制度ですか?誰でも取得できますか?
- 社会保険完備とは?求人における社会保険ありとの違いを解説!
- 住宅手当(家賃手当)とは?家賃補助との違いや支給条件、課税対象の範囲など詳しく解説!
- 特別徴収とは? 普通徴収との違いや転職時の住民税の切り替え方法は?
- 転職後、住民税の納付書が届いたのはなぜですか?支払う必要がありますか?
- 転職するとき、年金の手続きはどうすればよいですか?
- 離職期間中の国民年金はどうなりますか?失業中は免除制度があると聞いたのですが…
- 会社都合で退職する場合、失業手当(失業給付金)の給付の手続きはどうすればいいですか?失業保険の手当がもらえるのはいつから?
- 転職するとき、健康保険の手続きはどうすればよいですか?
- 転職先の健康保険の給付内容をチェックするときのポイントは?
- 失業期間中に病気やケガをした場合はどうなりますか?
- 社会保険料の計算方法は?年俸制と月給制では金額は変わるのでしょうか?
- 転職すると、退職後、今まで給与から控除されていた住民税はどうなりますか?
- 退職一時金にはどのような税金がかかりますか?計算方法を教えてください。
- 企業年金とは、どのような制度なのですか?
- 企業年金は、退職一時金にするのと企業年金のまま受給するのではどちらがよいですか?
- 退職給付制度にはどのようなものがあるのでしょうか?
- 退職すると確定拠出年金はどうなりますか?
- 転職すると財形貯蓄はどうなりますか?
- 転職すると持ち株会で購入した株式はどうなりますか?
- 転職すると給与天引きで加入していた団体保険はどうなりますか?
- 給与天引きで加入している団体扱い保険は、転職後どのような手続きが必要ですか?
- 転職すると今まで住んでいた社宅はどうなりますか?
- 「月給」「月収」とは?意味に違いはあるの?
- 「歩合制」ってどんな仕組み?メリット・デメリットを教えてください
- 「基本給」とはどういうもの?「月収」「月給」や「手取り」とどう違うの?
- 「定期昇給」って何?「ベースアップ(ベア)」との違いは?
- 転職時に年金の切り替え手続きを忘れてしまった…どうすればいい?
- 年収とは?年収を聞かれたら、総支給額・手取り額、どっちを答えたらいい?
- インセンティブとは?どんなものがあるの?簡単に教えてください。
- インセンティブと賞与(ボーナス)の違いって何?
- インセンティブには税金がかかるの?
- iDeCo加入中に転職した場合、手続きが必要ですか?必要な場合は何をしたらいいですか?
- 住宅ローン返済中に転職する場合、必要な手続きはありますか?
- 昇給とは?昇給の種類ってどんなものがありますか?
- 就業促進定着手当とは?どのような手当でしょうか?
- ベースアップ(ベア)とはなんでしょうか?分かりやすく教えてください。
- 給与(給料)明細の見方が分かりません。用語の意味や見るべき項目を教えてください。
- 深夜手当(深夜割増手当)とは?計算方法を教えてください。
- 広域求職活動費とは、どのような制度ですか?退職前の活動でも受給対象になりますか?